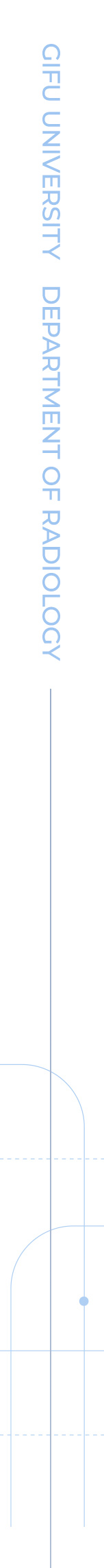心血管
心臓疾患や血管疾患を評価するためには、CT検査やMRI検査、核医学検査は非常に重要な手段です。特に造影剤を使ったCT検査やMRI検査では検査の性質上、造影剤を血管内に流すため心臓や血管の評価に優れます。
CT検査
CT検査では当院にある最新鋭のCT装置などを用いることで、低被曝で精度の高い綺麗な画像を作成することができ、質の高い検査・診断を心がけています。
冠動脈CT
冠動脈とは、心臓がポンプとして血液を全身に送るときに重要になる心臓の筋肉(心筋)を栄養する血管です。心臓から拍出される血液の5%が冠動脈の小さな3本の血管を介して心筋に栄養を送っています。従来は冠動脈の評価として、血管の中にカテーテルと呼ばれる細い管を挿入して検査を行う“冠動脈造影検査”が用いられていました。近年では、CT検査装置の進歩によって、比較的簡単かつ綺麗に冠動脈の評価が行えるようになり、本邦において冠動脈に病気のリスクがある人では、冠動脈CTが最初に行われる精密検査の一つに位置付けられています。
当院では冠動脈CTを複数名の放射線科医と循環器内科医で評価・検討し合うことで、より質の高い・より正確な診断を行うことを目指し、日々の検査を行っています。今までは冠動脈造影検査でしか測定ができなかった“冠血流予備能比(Fractional Flow Reserve)”と呼ばれる冠動脈病変の進行度を反映した所見も、冠動脈CTで計測できるため、より非侵襲的な検査が可能となっています。
大動脈CTなど
大動脈をはじめとする全身の主要な血管の病気にも造影CTが有用です。頻度の高い疾患として、大動脈瘤や大動脈解離、脳・内臓動脈瘤、血管奇形(動静脈奇形や静脈奇形など)などがあります。これらの疾患では射線科医や心臓血管外科医を含めた複数診療科との協力で診療を行っています。
腎機能低下があり造影剤が使用しにくい患者さんにおいても、先ほどのような病気で検査が必要になることがあります。通常では検査がしにくい状態であっても、当院では特殊な撮像方法(低管電圧撮像)を用いることで、造影剤の減量を実現しています。(The British journal of radiology, 94(1121), 20201276.)
MRI検査
近年はMRI装置の進歩により、動き続けている心臓や血流のある血管の評価が正確かつ素早く行うことができます。当院でも高性能なMRI装置を用いて、心臓の心筋症や弁膜症、内臓に生じる動脈瘤をはじめとした心血管系の病気に対して検査を行っています。
心臓MRI
心臓MRIはその名前の通り心臓をターゲットにした検査です。MRIはCTと異なり1枚の画像を作るためにある程度の時間が必要なため、従来は常に動き続けている心臓や血流の評価には限界がありました。近年では心臓の動きに合わせて撮影を行う方法が確立し(心電同期)によって、動き続けている心臓の評価も現実的になりました。
造影剤注入から遅いタイミングで病気のある(障害された)心筋に一致して造影剤が貯留する性質を利用した遅延造影検査が一般的に行われています。よく行われる心エコー検査と比較して心機能の定量評価(検査者の技術や患者さんの背景によらない評価)が可能なこともMRIのメリットです。またCTと異なり、造影剤を使用しないで血流の評価が可能なこともMRIの特徴といえます。このようにMRIにはCTにないメリットが複数あり、MRIが得意な心臓疾患(心筋が障害される疾患(心臓の筋肉の病気)や弁膜症(心臓の弁の病気))でMRI検査がよく行われます。
心臓疾患の診断には症状や様々な検査所見をあわせた評価が必要です。当院では心臓MRIを撮像した症例を放射線科医(画像のプロフェッショナル)と循環器内科医(臨床のプロフェッショナル)で個別に検討し、質の高い検査・診断を心がけています。
血管系MRI
MRIは造影剤を使用しないで血流の評価が可能であり、血管疾患の評価にも有用です。当院では様々な部位の動脈・静脈疾患の評価に留まらず、脳や体幹部の血管疾患の術前評価・術後評価にも用いられます。
内臓動脈瘤や脳動脈瘤、血管異常の治療には金属コイルを用いることが一般的ですが、CTと金属は相性が悪く、病気の部分を詳細に評価できません。MRIでは金属によるアーチファクトがCTより軽微なため、特に術後の経過観察にはMRIがよく用いられています(その際に造影剤を使用した検査を行うこともあります)。
核医学検査
心臓・血管系疾患の診断において、CTやMRIと同様に重要な放射線検査として、核医学検査があります。
心筋シンチグラフィ
心臓の機能評価や心筋虚血の有無や状態、範囲を評価する検査、特定の病気の有無に対する検査など様々な検査が存在しています。
心筋血流シンチグラフィは、安静時検査と薬剤(アデノシン)負荷時の検査が存在し、どちらも心臓の筋肉を栄養する血液が足りているか判断する検査です。前述の冠動脈CTや冠動脈造影とともに評価することで、より正確な心筋虚血の有無や状態が確認できます。
心筋脂肪酸代謝シンチグラフィは、心臓の筋肉の代謝状況を評価することができ、心筋が正常代謝(生きているか)かどうかが判断できます。
ピロリン酸シンチグラフィは一般的に心アミロイドーシスの診断で用います。心アミロイドーシスはアミロイド蛋白と呼ばれる異常な蛋白質が心臓に沈着することで異常をきたす疾患です。
肺血流シンチグラフィ
肺血流シンチグラフィとは、肺の毛細血管にトラップされる薬剤を注入することで、肺血流の分布に異常があるか確認する検査です。ほとんどが肺換気シンチグラフィと同時に行われます。肺動脈塞栓症(肺動脈に血栓が飛んでしまう病気;エコノミークラス症候群とも呼ばれる)や肺高血圧症の原因精査の時に行われます。
FDG-PET/CT
FDG-PET/CTはFDGと呼ばれる放射線製剤を投与して行う検査で、主に悪性腫瘍の転移再発診断に用いられることが一般的です。心臓領域ではサルコイドーシスという疾患に保険適応です。心サルコイドーシス目的のFDG-PET/CTは、通常の検査と異なり、絶食時間が長く、低炭水化物食などの検査前の対応が必要になります。