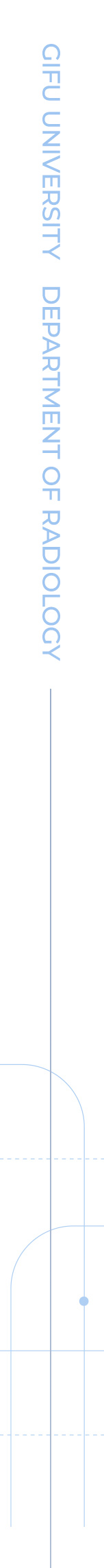小児
小児画像診断について
お子さまにやさしい画像診断を目指して
当院では、お子さまの健康を守るため、小児患者にも画像診断を提供しています。小児患者の画像診断では、成人患者同様に、画像を読影して主治医とともに患者さんの診療方針決定に関わるという大事な役割を担っています。また、あまり意識されない部分ですが、検査の質を担保するのも放射線科医の大事な役割です。小児患者は検査を嫌がる事が多く、必要な検査が施行できなかったり、目的の情報が得られないことがあります。無意味な検査を減らすために、放射線技師と連携してなるべくお子さまに負担がかからないような工夫を凝らしています。
小児画像診断の特徴
1. 画像診断の中心を担う単純X線撮影
単純X線撮影は1回あたりCT検査の約1/20の被ばく量で検査が施行できる検査です。その分CT検査と比べると得られる情報は限定的ではありますが、小児患者で多い肺炎、骨折、骨格の先天異常などは単純X線撮影でも十分に診断が可能です。身体への侵襲が少なく、検査が短時間で終わり、必要十分な情報が得られる可能性が高い単純X線撮影は、小児患者の画像検査の第一選択として活用されています。
また、ポータブル装置では場所を選ばず検査を行うことが可能です。お子さまが検査室まで来られない状態の時には病棟や救急外来などに出向いて検査を行います。
2. 被ばくを抑えたCT検査
当院には1回転で頭尾方向16cmの範囲を撮像できる最新のCT装置が導入されており、短時間で被ばく低減を意識した検査が可能です。
お子さまの体格に合わせた撮像プロトコルを使用し、被ばく低減を実現しています。しかし、ただ低線量撮像するだけでは粗い画像になってしまい、診断するにも十分な情報が得られません。当院では最新のDeep Learning Reconstruction(再構成)技術を使用し、低線量でも精細な画像を取得することが可能です。
必要に応じて造影剤を使用したCT検査が行われることがあります。この場合、複数回撮像を行うことになるので、その分被ばく量が増えてしまいます。当院では放射線科医が造影剤を使用するオーダーを全例チェックし、撮像回数や範囲を調整することで被ばく低減に貢献しています。
3. 安全で快適なMRI検査
MRIは放射線を使用しない検査ですが、撮影中は長時間動かずにいる必要があります。当院では、いくつかの工夫を行い、お子さまが安心して検査を受けられる環境を整えています。
体動による画像のブレを抑えるために、体格に応じた固定具を使用しています。また、小児科医の管理のもとで安全に鎮静を行い、ストレスなく検査を受けられるようにします。
また、検査中にアニメや好きな動画を視聴できるシステムを導入し、安心して過ごせるよう工夫しています。ただし対応する装置が限られますので、ご希望の際は小児科主治医に事前にご相談ください。
4. 核医学検査
核医学検査では放射性医薬品を投与し、その体内分布を取得することで、通常の形態画像ではわからない生体機能を可視化することができます。放射性医薬品を投与すると被ばくが生じますので、過量投与は避けなければいけません。当院では「小児核医学検査適正施行のためのコンセンサスガイドライン2020」に則り、お子さまごとに必要最小限の投与量となるよう調整を行っています。
診療内容
小児科医が臓器別ではなく全身を診療対象としているのと同様に、小児画像診断では画像診断可能な全身の疾患が対象となります。そのため、様々な疾患に対する幅広い知識を有し、次に行うべき検査を示したり、あるいは不要な検査は行わないように主治医に診療方針を示すのが放射線科医の役割となります。
対象となる疾患の例を以下に列挙します。
- 中枢神経疾患(先天奇形、頭部外傷など)
- 呼吸器・心疾患(肺炎、先天性心疾患など)
- 消化器疾患(腸重積症、先天性胆道閉鎖症など)
- 整形外科疾患(先天性股関節脱臼、骨折など)
- 悪性腫瘍(神経芽腫、白血病など)
小児科医や各分野の専門医と連携し、お子さまにとって最適な診断・治療が受けられるよう努めています。
お子さまの検査に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。