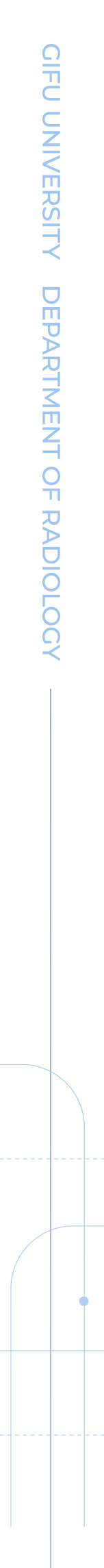外照射
放射線治療は近年、大きな進歩を遂げており、その要因の一つとして高精度な照射技術の発展が挙げられます。治療の精度を維持するために、治療姿勢を再現する技術や腫瘍の位置をリアルタイムで確認できるIGRT(Image-Guided Radiotherapy)の導入が、高精度な治療を支えています。
IGRT(Image-Guided Radiotherapy:画像誘導放射線治療)
IGRTとは、毎回の治療前や治療中に画像を撮影し、腫瘍や患者さんの体の位置を確認しながら行う放射線治療の技術です。放射線治療は通常、1日1回、数週間にわたって行われますが、その間に腫瘍の位置が変わることがあります。IGRTを活用することで、腫瘍の位置ズレを補正し、より正確で安全な放射線治療を実施できます。
IGRTの主な方法
- X線・CT画像による位置補正
治療直前にX線やCBCT(Cone-Beam CT)を撮影し、腫瘍の位置を確認しながら、必要に応じて微調整を行います。 - 腫瘍の動きを考慮した補正技術
肺や肝臓など、呼吸によって動く腫瘍に対しては、4DCT(4次元CT)やモニタリング技術を用いて動きを予測し、より正確に照射します。
IGRTの導入により、正常な組織への影響を最小限に抑えながら、がん細胞への効果を最大化できるようになりました。
IMRT(Intensity-Modulated Radiotherapy:強度変調放射線治療)
IMRTは、腫瘍の形状に合わせて放射線の強さや照射範囲を細かく調整できる治療法です。これにより、腫瘍への線量を最大限に保ちつつ、周囲の正常組織への被ばくを抑えることができます。その結果、従来の治療で起こりやすかった副作用の頻度や程度が軽減されています。
- 高精度な放射線照射
放射線の強さを細かく調整し、腫瘍に合わせた治療を行います。 - 副作用の軽減
隣接する正常な組織への影響を抑えられるため、副作用が軽減されます。 - 照射時間の短縮
近年ではVMAT(Volumetric Modulated Arc Therapy:強度変調回転放射線治療)という、装置が回転しながら照射を行う新しいIMRT法が開発されています。従来のIMRTと同様に、腫瘍の形に合わせて放射線の強さや方向を細かく調整しながら照射でき、VMATではさらに治療時間を短縮できるという特長があります。
IMRTは、前立腺がんや頭頸部がんを中心に使用されてきましたが、近年では多くのがん種に適応が広がっています。また、放射線治療を受けたことがある方でも、状況によっては再照射が可能な場合が増えてきました。
定位照射(SRS、SRT)
定位放射線治療は、腫瘍にピンポイントで高精度に放射線を集中させる治療法です。
腫瘍の種類や部位によって、以下のように呼ばれます。
- SRS(Stereotactic Radiosurgery):1回の照射で治療を完了する場合
- SRT(Stereotactic Radiotherapy):3~5回に分けて照射する場合
IGRT技術を活用し、脳では2mm以下、体幹部では5mm以下の精度で照射を行います。
脳の定位照射
- 固定器具として合成樹脂製のマスクを患者さんごとに作成し、治療時の動きを最小限に抑えます。
- 最新のHyperArc技術を搭載した装置を使用することで、複数の転移性脳腫瘍に対して、1回の治療で同時に照射できるようになりました。
肺の定位照射(SBRT)
- 4~10回程度の照射を行います。
- 呼吸に伴う腫瘍の動きを考慮した治療法を採用しており、息を止めた状態での照射や、軽くお腹を圧迫して呼吸の動きを抑えながら照射する方法などがあります。
- 高齢の方(80~90歳台)でも手術と同等の治療成績が報告されており、当院でも多くの実績があります。
その他
乳癌に対する深吸気息どめ照射
左乳がんの術後放射線治療において、心臓にも放射線が照射されてしまうことがあります。照射される放射線はわずかですが、治療後数年から20年間は心臓疾患の発症リスクが増加する研究報告があり、心臓の被ばく線量を減らすことが重要です。
このリスクを減らすためにDIBH(Deep Inspiration Breath Hold:深吸気息どめ)が導入されています。
- 息を大きく吸い込み、胸郭を広げた状態で放射線を照射することで、心臓と乳房の距離を離し、心臓の被ばく線量を減らします。
- 息どめの再現性が重要なため、患者さんにも事前に練習をしていただき治療を行います。
TBI(Total Body Irradiation:全身照射)
TBIは、全身に放射線を均等に照射する治療法で、主に造血幹細胞移植(骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植)の前処置として行われます。血液がん(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)の治療において、骨髄内のがん細胞を除去し、免疫抑制を行うことで移植の成功率を向上させる目的があります。
TBIは血液がんの治療において重要な役割を果たしており、特に移植医療の成功率向上に貢献しています。
緩和照射
腫瘍によって生じる苦痛を和らげ、生活の質(QOL)を改善することを目的とした放射線治療です。代表的なものとして転移性骨腫瘍による痛みの軽減・消失や、転移性脳腫瘍による脳神経症状(片麻痺や言語障害)・頭蓋内圧亢進症状(頭痛や嘔気)の改善が期待できます。そのほかの腫瘍による症状として、通過障害(食道がんや肺がんなど)や出血(胃がんや膀胱がんなど)などの改善も期待できます。短期間で症状緩和を図るため照射回数は1回から10回程度で行われることが多いですが、患者さんの状況に応じて一定の腫瘍の縮小と増大制御を考慮して回数を増やして行うこともあります。よく用いられる照射方法として、3Gy×10回、4Gy×5回、8Gy×1回などが挙げられます。
緊急照射
転移性骨腫瘍による脊髄圧迫や上大静脈(上半身の血流を心臓に返す血管)を閉塞する上大静脈症候群などの数時間から数日で大きく症状(麻痺や呼吸状態など)や今後のQOLが変化する可能性がある病変に対して行う緊急的な放射線治療です。
QUAD Shot
主に頭頸部がんに行われることが多い緩和照射です。通常の放射線治療は1日1回ですが、この照射方法は1日2回(朝と夕)を2日間かけて合計4回照射を1クールとして、4-6週間ごとに合計3クールまで行うことがあります。今まで行われていた頭頸部がんの緩和照射(3Gy×10回など)と比較して短期間の治療となるため、通院や入院の負担を少なくすることができます。また、過去に一度放射線治療を行なった部位にも2回目の放射線治療として照射することができ(再照射といいます)、副作用を軽減しながらも腫瘍縮小が期待できる治療です。
密封小線源治療
前立腺がんへのLDR-BT(low-dose-rate Brachytherapy:低線量率小線源治療)
当院ではヨウ素125シード線源永久挿入による前立腺癌密封小線源療法を東海地方ではいち早く開始しました。泌尿器科との密な連携の下、治療を行っておりこれまで16年間で581例の患者さんを治療しています。前立腺癌のリスク分類によって内分泌療法や外部照射も併用し、非常に良好な成績をおさめています。当院では外部照射を併用する場合、IMRTでの照射を行うことで、より質が高く、副作用の少ない治療を目指しています。この治療を行える施設は限られているため、他施設からも多くのご紹介をいただき治療を行っています。
婦人科がんへのHDR-BT(high-dose-rate Brachytherapy:高線量率小線源治療)
婦人科がんに根治的放射線治療をする際に必要な治療法です。代表的な疾患に子宮頸がんがあります。子宮頸がんは外部照射と腔内照射を組み合わせて治療を行います。早期がんでは放射線治療単独により手術と同等の良好な治療成績であり、進行がんであっても、抗がん剤と併用して放射線治療を行う化学放射線治療により十分に根治を目指すことが可能で、婦人科がんガイドラインでも手術より推奨度が高い標準治療です。子宮頸がんの根治照射における腔内照射は、タンデムとオボイドという器具を経腟にて挿入して治療します。回数はがんの進行度によって異なりますが、週に1回、合計2−4回治療を行います。最近は症例によっては組織内照射併用腔内照射を行うことがあります。従来の腔内照射だけでは十分に照射できなかった病変に針を挿入しその内部より照射する治療法が発展してきました。そのため今後更なる治療成績の向上が見込まれます。一方、子宮・腟内への治療器具挿入などの処置に対して不安や苦痛を感じる患者さんが多くいます。この不安や苦痛を和らげるために鎮静剤・鎮痛剤の投与が有効で、当院では患者さんの希望に合わせて投与を行います。
子宮頸がんに対する放射線治療では小線源治療が重要な位置を占めますが、この治療を行える施設は限られているのが実情です。岐阜県では当院でのみ行なっていますので、県内他施設からも多くのご紹介をいただき年間30-50例治療を行っています。
良性疾患
放射線治療はがん以外にも一部の良性疾患でも有効です。代表的なものに、甲状腺眼症(甲状腺機能亢進症(バセドウ病)に関連)やケロイドが挙げられます。甲状腺眼症は中等度から重症に対する治療として、内科的な治療と併用することがあります。ケロイドは皮膚科や形成外科と密に連携し、外科的切除後早期に開始することで再発を予防する効果があります。