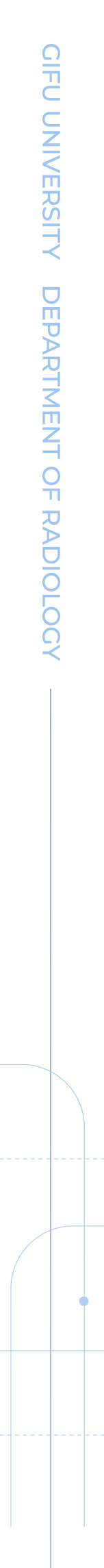学生・研修医教育
放射線科の業務は大きく、「画像診断」「放射線治療」「IVR(画像下治療)」に分かれており、それぞれ全く違う診療内容を扱っていますが、すべてに共通するのは「概ね全身が対象となる」点です。
岐阜大学では放射線科としてのコースの他に、一部他診療科のコースの中でも放射線科の講義が組み込まれています。各診療科での講義では概ね臨床的な内容が語られ、放射線科コースにおいてはそれに加えて放射線物理学や被ばく医療と言ったより総論的な内容が扱われます。また、学内臨床実習・選択臨床実習では実際の症例を通して、より実践的な形での学習ができるようにしています。
初期臨床研修では基本は「画像診断」に配属されますが、希望に応じ、「放射線治療」や「IVR」の研修にも対応可能です。研修においては実際の読影レポートを作成し、それを添削してもらうことで画像診断の基礎について研修してもらいます。
学生教育
3年次「循環器・呼吸器・腎尿路学」コース
主に腎・尿路系疾患の画像診断、放射線治療について講義を行っています。
3年次「消化器・検査・血液腫瘍学」コース
消化管、肝、胆・膵の基本的な疾患の画像診断、放射線治療、IVRに加え、消化管造影検査や大腸CT検査と言った特殊な検査について講義を行っています。
4年次「画像診断・放射線治療」コース
これまで各診療科の講義で扱われてきた様々な疾患の画像診断、放射線治療、IVRについて院内・院外の講師による講義を行っています。加えて、放射線物理学、被ばく医療、各モダリティの基本となる知識についても講義を行っています。
4年-5年次「学内臨床実習(ポリクリ)」
実際の症例を活用した画像診断、放射線治療、IVRの知識の習得や実践を行います。実際の症例画像を自分でカルテ画面を操作し、異常を指摘することで患者の病態を診断することを目指します。
5年-6年次「選択臨床実習」
実際の症例画像から異常を指摘する実学的教育の分野が学内臨床実習時より拡大する他、「画像所見を他の人にプレゼンテーション/説明する」という、医師に必要な臨床スキルの習得を目指します。また、胸部単純写真や症例画像集を用いた自学自習教材、ある疾患の画像所見などについてまとめて発表する症例提示なども行っています。
研修医教育
岐阜大学医学部附属病院プログラムの中で選択診療科の一つとして1年目、2年目共に選択可能です。また、他連携病院からも研修先として受け入れを行っています。基本的には実際の診療レポートを作成する形で画像診断の研修を行っていただきますが、希望に応じて放射線治療やIVRを主体とする研修も選択可能ですので気軽にご相談ください。
画像診断においては作成したレポートはすべて放射線科診断専門医によるダブルチェックを行った上で電子カルテ上に公開します。読影のコツや画像所見の表現などを症例ごとに指導していきます。沢山の症例を読影する必要は無いので1例1例をしっかりと読影してください。
放射線治療においては初診に同席してもらい放射線治療の適応や副作用などについて学んでもらう他、放射線治療計画の作成にも関与してもらいます。放射線を照射する範囲や照射線量を極力少なくするリスク臓器などをCT画像にマーキングする(contouring)ことで治療計画を行います。
IVRでは実際の手技を見学してもらいながら治療適応や手法を学んでもらいます。
放射線科で学んでほしいこと
放射線科での実習、研修を通じて学んでほしいことを各部門の先生に聞いてみました。
画像診断
まず大事にしてほしいのは各検査の撮像法や画像診断に必要な基礎知識です。例えば、CTではX線の吸収割合の差を用いて画像化していますがこれを評価する際に「CT値」や「ウィンドウレベル・ウィンドウ幅」と言った概念が重要です。MRIでは体内の水素原子の動きを画像化していますがそのパラメータ毎に組織の信号値が変化します。これらを踏まえなければ診断には結びつきません。また、「異常」を見つけるためには「正常」をよく知らなければなりません。解剖を含めた正常構造の知識、それが画像検査でどのように見えるのか、これをまずは理解してほしいです。その上で基本的な疾患・病態の画像診断を学習すると良いと思います。
放射線治療
様々ながんに対する集学的治療における放射線治療の立ち位置について知っておくことがまずは重要です。照射方法の違い(リニアック治療、陽子線治療、重粒子線治療)やその上で問題となる組織の耐容線量を含めた被ばくについての基本的な知識や被ばく医療についても合わせて勉強できると良いです。臨床的な話になると緊急照射の適応については知っておくべきでしょう。
IVR
IVRが対象とする疾患や治療方式、カテーテル治療の適応や画像誘導下の生検、ドレナージの方式、適応など実際の手技について理解しておくことが大事かと思います。こうした手技を行う上ではやはり、血管解剖、臓器解剖が重要です。これらを理解せずに手技を行うのは地図を持たずに旅に出るようなものです。臨床的な部分では緊急止血の適応となる疾患や画像所見を知っておくとスムーズなコンサルトにつながるのではないでしょうか。
放射線科での学習・実習・研修におすすめの教科書
昨今は医学教育の質が年々向上しており、専門書ばかりだった教科書にも初学者向け、学生向けの読みやすいものが増えてきました。今回ここに紹介するものはその一部ですが学習の一助としていただけますと幸いです。
画像診断
- 『CT診断一問一答』『MRI一問一答』(Gakken)
- 『医学生・研修医のための画像診断リファレンス』『レジデントのための画像診断の鉄則』(医学書院)
- 『レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室』(日本医事新報社)
- 『わかりやすい核医学』(文教堂)
- 『画像診断に絶対強くなる』シリーズ(羊土社)
- 『X発!10秒で読める画像診断』(金芳堂)
- 『クイズで学ぶ画像診断「1手詰」』(金芳堂)
放射線治療
- 『やさしくわかる放射線治療学』(Gakken)
- 『放射線治療基礎知識図解ノート』(金原出版)
- 『スイスイわかる放射線治療物理学』(Gakken)
IVR
- 『これから始めるIVR』(メジカルビュー社)
総論・その他
- 『放射線科研修読本』(MEDSi)
- 『画像診断を考える 第2版』(Gakken)