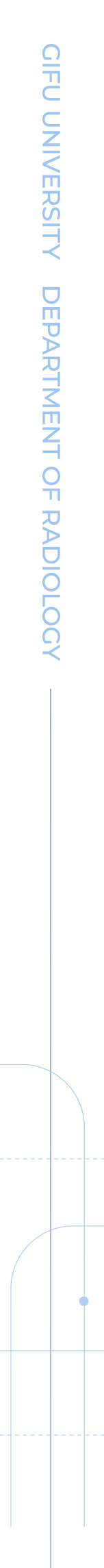教室の歩み
岐阜大学医学部放射線医学講座は1950(昭和25)年2月に開講された岐阜県立医科大学医学部放射線科学講座を前身とする、東海地区で最も歴史のある放射線科医局の一つです。現在は第5代教授・松尾政之先生の元、多くの医局員が日々の診療、研究、教育に従事しています。
歴代教授
初代教授・玉木正男(たまき・まさお)1950-1957
玉木正男先生は慶應義塾大学に学び、日本初の放射線科医として知られる藤浪剛一先生の門下として薫陶を受けた本邦における放射線科の源流を汲む先生の一人です。玉木先生と同教室入局第一号であった飯沼順二先生らは、自作の装置を用いて、造影剤の静脈内注入から右心系・左心系・大動脈までの連続血管造影撮影に日本で初めて成功し、さらに高安動脈炎や肺癌における血管造影所見を報告しました。また、1952(昭和27)年には名古屋大学泌尿器科・三矢辰夫教授らと現在の日本医学放射線学会中部地方会の前身にあたる日本医学放射線学会東海部会を創立しました。玉木先生はその後、長崎大学放射線医学教室教授、大阪市立大学(現・大阪公立大学) 放射線医学教室教授、日本医学放射線学会会長を歴任するなど、日本の放射線医学分野における先駆者としてその発展に大きく貢献されました。
岐阜市を流れる清流・長良川より名前を取られた御子息の玉木長良先生も放射線科医としてご活躍され、北海道大学核医学教室教授、同医学部長、京都医療科学大学学長などの要職を歴任されています。

第2代教授・石口修三(いしぐち・しゅうぞう)1958-1975
石口修三先生は倉敷中央病院放射線科主任を経て、1958(昭和33)年、第2代教授に就任されました。石口先生の専門は呼吸器画像診断であり、呼吸器疾患のX線診断学や気管支鏡検査における気管支造影検査に注力されました。1964(昭和39)年に岐阜県立医科大学は国立岐阜大学に移管され、当教室も1967(昭和42)年に国立岐阜大学に移管されました。石口先生は1967(昭和42)年から1969(昭和44)年に岐阜大学医学部附属病院病院長を兼任し、さらに1967(昭和42)年に第26回日本医学放射線学会総会の大会長も務めました。当時は教室員が少なかったようで、この転換期において当教室は多忙を極めたと伝えられていますが、岐阜市民会館で行われた第26回日本医学放射線学会総会は大成功を収めました。
国立移管に伴って設備投資費が投入されるようになり、様々な設備が整備され、1967(昭和42)年に当時急速に普及しはじめた核医学検査が当院でも開始されました。核医学検査における研究成果は今枝孟義先生らによって報告されています。また柴山麿樹先生・松井英介先生らによって開発された選択的気管支造影に併用する経気管支的肺生検法は、当時主流であった方法よりも安全かつ容易に行える方法として全国的に普及しました。1970(昭和45)年には放射線治療棟が完成し、コバルト60回転照射装置による放射線治療が開始されました。
御子息の石口恒男先生も放射線科医としてご活躍され、愛知医科大学放射線医学教室教授、同病院副院長を歴任されました。

第3代教授・土井偉誉(どい・ひでたか)1976-1995
土井偉誉先生は国立がんセンターを経て、1976(昭和51)年4月、第3代教授に就任されました。これまで臨床放射線を中心に発展してきた当教室に、臨床・研究・教育いずれの面でも有数の指導者である土井先生を迎え、当教室は飛躍的な発展を遂げることになりました。土井先生は国立がんセンターの草分け的存在で、消化器X線診断の世界的権威として知られており当教室においても消化管のX線透視の普及や画像診断に注力し、特に消化器癌がん健診の有効性・胃がんの早期検出について日本の先頭に立って調査および証明されました。この功績は『厚生省がん研究助成金による胃集団検診の死亡率減少効果と将来予測に関する研究』(土井班1989年~1991年),『厚生省がん研究助成金による高齢者の胃がん検診の評価とその効率向上に関する研究』(1992年~1993年)に発表されています。当時消化管内視鏡の名手であった秋田赤十字病院工藤進英先生のもとをはじめ、国内留学も盛んに行われるようになりました。また、医学部附属病院中央放射線部に初めての頭部用CT装置 (1976(昭和51)年)やMRI装置(1992(平成3)年)が設置されました。1985(昭和60)年には放射線治療棟が増築され、国枝武俊先生の運営下でスカンジトロニクス社製マイクロトロンMM-22が日本で3番目に設置されました。

第4代教授・星博昭(ほし・ひろあき)1995-2015
星博昭先生は、ハーネマン大学(アメリカ)やマギル大学(カナダ)へ留学後、宮崎医科大学放射線医学講座助教授を経て、1995(平成7)年4月、第4代教授に就任されました。星先生の専門分野は核医学であり、2007(平成19)年の当院における18F-FDG PET/CT検査導入をはじめ、核医学検査の啓蒙・定着に多大に貢献しました。
2004(平成16年)の医学部附属病院移転に伴い、放射線部門の改編が行われました。病院が岐阜市司町から同市柳戸に移転し、これを機に医用画像は従来のフィルムでの読影・保存から、モニター診断・サーバー内保存に変わりました。新たな放射線部門システムや読影レポーティングシステムの構築には星先生が主導して医局員・放射線部・医療情報部等が一丸となり、多大な苦労のもとに達成され、これが今日の画像診断環境の礎となっています。
技術革新によってCT・MRIの検査時間が短縮し、検査数が年々増加したため、放射線診断医の仕事は徐々に読影/画像診断が中心となりました。急速なコンピュータ技術の発達・進歩がこれらの変革の背景となり、画像データがデジタル化され、放射線科診断分野の研究のメインテーマとして画像解析やコンピュータ支援診断という分野が確立されていくこととなりました。このような時代の潮流にうまく乗り、工学系や情報系学部との医工連携を開始したのも星先生の大きな功績の1つです。このころから既に、CT画像における臓器や筋肉の自動抽出やマンモグラフィのコンピュータ支援診断等に取り組んでおり、第90回北米放射線学会(RSNA)では岐阜大学大学院医学研究科再生医科学専攻知能イメージ情報分野との共同研究はCertificate of Meritを受賞しました。また兼松雅之先生、五島聡先生を中心に腹部画像診断や造影CTにおける造影剤理論に関する研究が盛んに行われました。2004(平成16)年からはCT・MRIの画像診断のいろはを医局員に伝える夕方のデイリーカンファレンスが開始されました。現在全国的にも高い評価を受けている岐阜大学放射線科の専攻医教育の黎明期はこの頃です。
放射線治療部門は林真也先生を中心に運営され、1999(平成11)年には放射線治療装置としてマイクロトロンに替わりリニアック装置である東芝社製メバトロンが、2004(平成16)年にはVarian社製CLINAC21EXが新規導入され、同年には東海地区で初めて前立腺癌に対して永久挿入密封小線源療法が開始されました。

第5代・松尾政之(まつお・まさゆき)2015-
松尾政之先生は、当教室出身で、木沢記念病院(現・中部国際医療センター)放射線科部長、アメリカ国立衛生研究所(NIH)研究員、名古屋市立大学放射線医学分野准教授を経て、2015(平成27)年9月、第5代目教授に就任されました。松尾先生の人柄や当教室の教育体制、放射線科への時代のニーズの高まり等が相乗効果を生み、当教室への入局者数は年々増加し、岐阜県内の多くの関連病院に放射線科医の派遣が可能となりました。それでもなお、年々増加する検査数に対して放射線科医数は絶対的に不足している現状を打破すべく他県に先駆けて遠隔読影体制の構築に着手し、岐阜大学医学部附属病院を中心とした県内関連病院との遠隔画像診断による連携体制を構築しました。また、放射線治療分野についても遠隔による治療計画支援事業を計画しています。
また、松尾先生は自身がNIH留学中に学んだ超偏極MRIの将来性を確信し、超偏極MRIの生体応用研究を可能とする当時日本国内で2台目の最新装置を2018(平成30)年に導入しました。同キャンパス内に獣医学部や動物病院と研究用動物飼育施設を持つ強みを生かして密な連携体制を構築すると共に、東京大学、横浜市立大学、量子科学技術研究開発機構と共同研究を行い、多くの大学院生を抱えながらこれまでに数々の知見を報告しています。松尾先生は2020(令和2)年の国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学の統合(国立大学法人東海国立大学機構)に伴って発足した量子フロンティア産業創出拠点事業において、岐阜大学医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンター長を併任しています。

年表
| 1950年 | 岐阜県立医科大学放射線科学講座設立、玉木正男、初代教授就任。 |
|---|---|
| 1952年 | 日本医学放射線学会東海部会発足。 |
| 1958年 | 石口修三、第2代教授就任。 |
| 1964年 | 岐阜県立医科大学、国立岐阜大学に移管。 |
| 1967年 | 岐阜大学医学部放射線医学教室に移行。 |
| 石口修三教授、岐阜大学医学部附属病院病院長就任。 | |
| 第26回日本医学放射線学会総会開催。 | |
| 岐阜大学医学部附属病院での核医学検査開始。 | |
| 1970年 | 岐阜大学医学部附属病院に放射線治療棟完成。 |
| 西岡清春、慶應義塾大学放射線医学教室診断部門教授就任。 | |
| 1976年 | 土井偉誉、第3代教授就任。 |
| 岐阜大学医学部附属病院に頭部CT装置導入。 | |
| 1979年 | 第16回日本胃集団検診学会秋季大会開催。 |
| 1985年 | 放射線治療棟増築、カンジトロニクス社製マイクロトロンMM-22導入。 |
| 1989年 | 第28回日本消化器集団検診学会開催。 |
| 1993年 | 石垣武男、名古屋大学放射線医学教室教授就任。 |
| 1995年 | 星博昭、第4代教授就任。 |
| 1999年 | 東芝社製メバトロン導入。 |
| 2004年 | 岐阜大学医学部附属病院、岐阜市司町から同市柳戸へ移転。 |
| Varian社製CLINAC21EX導入。 | |
| 中央放射線部、改編。医用画像の電子媒体化。 | |
| デイリーカンファレンス、開始。 | |
| 2007年 | 18F-FDG PET/CT装置導入。 |
| 2015年 | 近藤浩史、帝京大学放射線医学教室教授就任。 |
| 松尾政之、第5代教授に就任。 | |
| 2016年 | 林真也、藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)放射線腫瘍科学教授就任。 |
| 朝の読影勉強会「金子塾」開始。 | |
| 2018年 | 超偏極MRI装置導入。 |
| 2019年 | 五島聡、浜松医科大学放射線診断学・核医学講座教授就任。 |
| 田中秀和、山口大学放射線腫瘍学講座教授就任。 | |
| 2020年 | 松尾政之教授、岐阜大学医学部附属量子医学イノベーションリサーチセンター長就任。 |
| 2023年 | 兵頭文紀、岐阜大学薬理病態学分野教授就任。 |