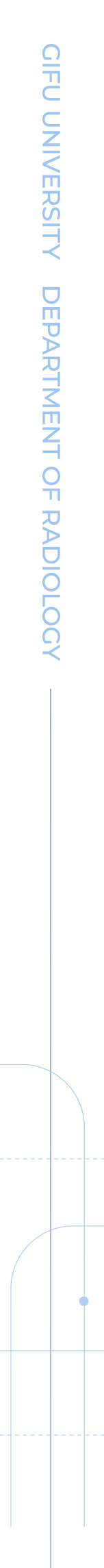放射線部の紹介
放射線部は、放射線診断および放射線治療を通じて、地域医療と高度医療の両立を目指しています。専門性の高いチーム医療の一員として、正確かつ安全で迅速な画像診断と、患者さんにやさしい放射線治療を行っています。
診療内容
画像診断部門では、一般エックス線(・特殊)撮影、X線透視撮影、X線CT検査、MRI検査、血管撮影・IVR、核医学(アイソトープ)など、幅広いモダリティーを用いて、病気の早期発見や正確な診断を支援しています。放射線治療部門では、直線加速器(リニアック)、密封・非密封小線源等を用いて、患者さん一人ひとりに最適な治療を設計・提供しています。
高度な機器と熟練した放射線診断専門医、診療放射線技師、看護師による連携で、質の高い医療画像を提供し、がんの根治や症状緩和を目的とした放射線治療を、安全かつ効果的に実施しています。
一般X線(・特殊)撮影
一般X線撮影部門では、胸部や腹部、骨などのX線写真(レントゲン)を撮影しています。これは、病気やけがの診断において、もっとも基本的で重要な検査のひとつです。
撮影は、専門の放射線技師が担当します。正確で見やすい画像を撮影するため、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、無理のない体勢や丁寧な説明を心がけています。撮影時間は通常数分程度で、痛みはありません。
当部門では、最新のデジタルX線装置を導入しており、被ばく線量を最小限に抑えながら、高画質な画像を撮影することが可能です。
また、乳がんの早期発見を目的とした乳房X線撮影(マンモグラフィ)や、骨の健康状態を調べる骨密度測定の特殊撮影も行っています。
X線透視撮影
X線透視撮影部門では、X線を使って体の中の動きや様子をリアルタイムで観察しながら行う検査を担当しています。たとえば、バリウムを使った胃の検査(胃透視)や、造影剤を使った消化管・尿路・関節などの検査、またカテーテルやチューブの位置確認など、さまざまな診断・治療を支えています。
また、内視鏡検査や処置において、必要に応じてX線透視装置を併用することがあります。特に胆道や膵管などの検査・治療(ERCPなど)では、内視鏡とX線を組み合わせることで、より正確で安全な診断・治療が可能になります。
X線CT検査
CT検査部門では、CT(コンピュータ断層撮影)装置を用いて、体の内部を詳しく調べる検査を行っています。CT検査は、X線を使って体の断面を撮像し、撮像したデータから臓器や血管、骨の状態を立体的に映し出すことができる検査です。病気の早期発見や、手術・治療の前後評価などに広く使われています。必要に応じて、造影剤(薬剤)を注射して、より詳しい画像を撮ることもあります。
当院では、最新のマルチスライスCT装置を導入し、短時間で広範囲を撮影できる環境を整えています。また、撮影中の被ばく線量を最小限に抑える技術を導入し、安全に配慮した検査を行っています。
MRI検査
MRI検査部門では、MRI(磁気共鳴画像)装置を用いて、体の内部を詳しく調べる検査を行っています。MRIは、磁石と電波を使って体の断面画像を撮影する検査で、放射線(X線)を使用しないため、被ばくの心配がありません。MRI検査は、脳や脊髄、関節、内臓、血管などの状態を詳細に描き出すことができます。脳梗塞や脳出血、腫瘍、脊髄や血管の病変、関節や靭帯の損傷など、様々な疾患を見つけるのに優れた検査です。トンネル状の装置の中に横になって入ります。検査中は、「トントン」「ガーガー」といった大きな音がしますが、痛みはありません。検査時間は通常20〜40分程度です。必要に応じて造影剤を使うこともあります。
当院では、高性能なMRI装置(1.5テスラ/3テスラ)を複数台導入し、検査時間の短縮や画像の高精度化に取り組んでいます。検査中は技師がモニターで常に様子を確認し、インターホンで声をかけながら安全に進めていきます。MRI検査は強い磁石を使うため、金属類は持ち込めません。体内に金属がある方(ペースメーカー、人工関節、脳動脈クリップなど)は、事前に医師やスタッフにご相談ください。
血管撮影・IVR
血管撮影・IVR部門では、血管撮影(アンギオグラフィ)や、X線透視装置を使って行う画像下治療(IVR:インターベンショナルラジオロジー)を担当しています。これらの技術により、開腹や切開をせずに、血管や臓器の病気を診断・治療することが可能です。血管撮影とは、血管に細いカテーテル(管)を挿入し、造影剤を使って血流や血管の状態を詳しく調べる検査です。脳や心臓、肝臓、足の血管などの病気の診断に役立ちます。画像はリアルタイムで撮影され、高精度な診断が可能です。
IVRは、X線やCT、超音波などの画像を見ながら行う低侵襲(からだに負担の少ない)治療です。
- 出血を止めるための動脈塞栓術
- がんに栄養を送る血管を遮断する肝動脈化学塞栓療法(TACE)
- 膿や体液を排出するためのドレナージ(管の挿入)
などが行われます。
検査や治療は、IVRの専門医と診療放射線技師、看護師が連携し、清潔で安全な専用の血管撮影室で行います。患者さんの体への負担をできる限り軽減しながら、確実で効果的な治療を提供します。
核医学(アイソトープ)
核医学(アイソトープ)部門では、微量の放射性医薬品を体内に投与し、その分布や働きを専用のカメラで撮影・解析することで、臓器や骨、がんなどの状態を調べる検査や治療を行っています。これを「核医学検査」と呼びます。体内の臓器や細胞の機能や代謝の様子を画像としてとらえることができるのが、核医学検査の特徴です。X線やCT、MRIではわかりにくい異常も、核医学検査で早期に発見できることがあります。
PET検査とは、PET-CT装置を用いたがんの診断・再発の確認・治療効果の判定などに非常に有効な検査で、全身のがんの状態を詳しく調べることができます。
核医学治療とは、放射性医薬品を「診断」だけでなく「治療」にも応用しています。これを「核医学治療」と呼び、放射性医薬品を体内に投与し、病気のある部分に放射線を当てて治療します。外科的な手術をせずに体の中からがん細胞などを攻撃する方法であり、体への負担が比較的少ないのが特徴です。
放射線治療
放射線治療部門では、がんや一部の良性疾患に対して放射線を使った治療を行っています。高精度な放射線を病変部に集中して照射することで、がん細胞を破壊し、正常な組織への影響を最小限に抑える治療です。放射線治療は、手術や薬物療法(抗がん剤・ホルモン療法など)と並ぶがん治療の三本柱のひとつで、身体への負担が少ないことが特徴です。通院で治療が可能な場合も多く、日常生活を送りながら治療を受けることができます。
最新の放射線治療装置を導入し、画像誘導放射線治療(IGRT)や強度変調放射線治療(IMRT)、定位放射線治療(SRT/SBRT)などの高精度な治療法を行っています。また、**全身照射(TBI)や小線源治療(前立腺がん・婦人科がんなど)**にも対応しています。
スタッフ概要
構成
| 診療放射線技師長 | 1名 |
| 副診療放射線技師長 | 4名 |
| 主任診療放射線技師 | 10名 |
| 診療放射線技師 | 33名 |
| 契約職員 | 2名 |
| 事務職員 | 4名 |
専門・認定資格
- 第1種放射線取扱主任者
- 衛生工学衛生管理者
- 医学物理士
- 放射線治療品質管理士
- 放射線治療専門放射線技師
- 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師
- 磁気共鳴専門技術者
- 核医学専門技師
- 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師
- X線CT認定技師
- 医療情報技師
- 救急撮影認定技師
- 放射線管理士
- 医用画像情報精度管理士
- 画像等手術支援認定診療放射線技師
- 診療放射線技師実習施設指導者
- NBC災害・テロ対策
- 原子力災害医療派遣チーム
- 原子力災害医療中核人材
- 甲状腺簡易測定
- ホールボディーカウンタ計測
- 災害支援認定診療放射線技師
技師長・副技師長の紹介



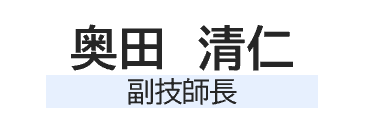


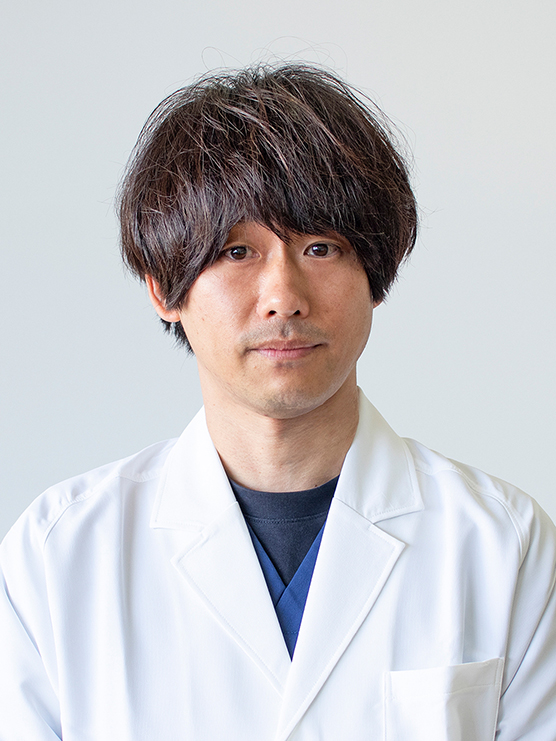


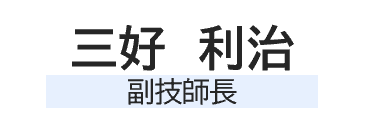
リクルート情報
岐阜大学医学部附属病院は地域の中核病院として、先端医療の提供・人材の育成・臨床研究の推進に努めています。そんな中で放射線部も臨床業務・教育・研究に励んでいます。
採用・募集
以下のURLを参照ください。
採用・募集 | 岐阜大学医学部附属病院
紹介
理念・基本方針
岐阜大学医学部附属病院は、『あなたとの対話が創る信頼と安心の病院』を理念とし、「患者中心のチーム医療の提供、人間性豊かな医療人の育成、先進医療の研究・開発・提供、地域との医療連携の強化」を基本方針として、日々業務に励んでいます。
放射線部は、『確かな医療技術に基づき、患者さんに信頼される安心な医療の提供』を理念とし、診断・治療業務に従事しています。
組織・体制
放射線部は、医師3名・診療放射線技師50名(再雇用・パート雇用者3名を含む)・看護師28名(光学診療部と併任)・技能補佐員4名で構成されています。
技術部門は診療放射線技師長を筆頭に副診療放射線技師長4名(学術・安全、教育・研修、放射線管理、庶務)、主任診療放射線技師10名(一般撮影、透視・手術室、CT、MRI、血管造影、核医学(アイソトープ)、治療、情報、安全管理、線量管理)で組織されています。
勤務体系
放射線部の勤務体制は完全2交替制を導入しています。平日日勤帯は管理職や専従技師(専門技師等)、再雇用技師を除く36名(主任4名を含む)が3~5部門をローテンション勤務しています。人員配置の内訳は、一般撮影・透視手術室:7名、CT:7名、MRI:6名、核医学:3名、治療:7名、血管造影:3名、ハイブリッド手術室:2名で運用をしています。情報・安全管理・線量管理部門は併任です。夜間・休日日勤帯はMRIおよび血管造影に対応可能な技師2名(全29名)が勤務しています。当院は、県内唯一の時間外のIVR対応可能施設であり、またドクターヘリの活躍により、年間の時間外IVRは70件(2020年実績)にのぼり、心臓・脳血管を合わせると年間214件、3日に2回のペースで血管造影検査があります。7年前より、血管造影およびMRIは夜勤従事者の必須要件としました。呼び出しや待機を要することなく、勤務者2名のみですべての業務に対応可能な現体制は、患者、医師、そして我々にとって非常に有益なシステムであると自負しています。
診療部門
一般撮影部門ではほぼすべての撮影にFPDを使用しています。頸部や胸腹部に挿入されたチューブ類の位置確認の撮影には、通常の胸部や腹部の画像に加え、より視認しやすいよう画像処理を施した画像も併せて配信しています。骨密度測定検査は通常の骨密度測定と合わせてソフトウェア上で骨構造解析を行うことができる海綿骨構造指標(TBS)を導入し、骨折リスク評価に微細構造を組み込むことが可能となっています。
乳房撮影部門ではトモシンセシス技術を搭載した装置を導入しています。またステレオガイド下吸引式組織生検も適宜施行し、診断能の向上に努めています。さらに放射線科読影医、乳腺外科医、診療放射線技師により構成される乳房画像カンファレンスを毎週開催し、画像所見の検討や治療方針に関する活発なディスカッションを行っています。診療科や職種の垣根を越えて、患者さん毎に最適な検査や治療を提供しています。
透視手術室部門は、2022年4月より新手術棟が完成し、手術室にHybrid OR 2室(バイプレーン1台、シングルプレーン1台)が稼働を始めました。主に脳神経外科による脳腫瘍摘出術、クリッピング手術、血管内治療や心臓血管外科による大動脈ステント留置術、整形外科の側彎症固定術、循環器内科のTAVI、耳鼻科の光免疫療法、放射線科のTAE等が使用し、さらに高次救命救急など緊急手術の使用が期待されています。
X線CT検査部門は64列MDCT/ 1台、256列ADCT/ 2台(令和5年に装置1台を更新)の合計3台のCT装置を運用し年間35000件ほどの検査を行っています。3台のCT装置全てがDual Energy 撮影を行うことが可能であり、それに加え64列の装置では光逐次近似応用画像再構成を、256列のCT装置では深層学習を用いた人工知能画像再構成を行うことが出来ます。これらの最新技術を臨床活用する手法を模索するために、放射線科医師と連携を密に取りながら日々臨床研究活動を活発に行っています。
MRI検査部門では「安全で快適な検査環境の提供」と「高効率かつ高画質な画像提供の実現」を目標に、年間15000件以上の検査を実施しています(3.0T,1.5T各2台)。安全性と快適性の向上は、検査前の説明や更衣の介助、金属チェック等を専門で行う技能補佐員の配属と大型モニターの映像を検査中に鑑賞できるAmbient Experienceシステムの設置により実現しています。またMRI検査予習システムの活用や放射線科読影医との密なディスカッションを通じた知見の共有に加えて、撮像プロトコルの最適化や最新技術の積極的な臨床応用により、高効率と高画質の両立を日々模索しています。
血管造影・IVR部門では全身の多岐にわたる手技(検査・治療)に携わっています。医師や看護師、臨床工学技士など多職種間で密に連携し、医療安全に寄与するよう努めています。放射線管理や放射線防護の最適化にも注力し、患者さんだけでなく術者にも安全安心な医療が提供できるよう心掛けています。
核医学部門ではデリバリーFDGを使用したPET-CT検査を年間2000件施行しています。さらに半導体検出器を搭載した装置が2022年7月より稼働開始し、高分解能と高感度を両立した新装置は画質のみでなく、投与量低減・CTによる低被ばくを実現しています。また当院は放射性医薬品による内用療法の入院対応が可能な県内唯一の施設です。常に安全で質の高い治療を提供できるよう、放射線科医、看護師と連携し、定期的にカンファレンスを行っています。
放射線治療部門では、2台のリニアックを有しており、そのうち1台が令和4年度に更新され、これにより両装置での画像誘導放射線治療、高精度放射線治療が可能となりました。また診療科と連携し、子宮頸癌に対する腔内照射(RALS)、前立腺癌に対するヨウ素125シード線源永久刺入による前立腺癌密封小線源療法を東海地区で最初に始めました。
研究・教育
当院では副技師長や主任を専従もしくは専任として各モダリティに配置し、他の勤務者が数ヶ所のモダリティを日替わりでローテーションする方式を採用しています。勤務表の作成が少々煩雑になるものの、この方式は各種モダリティへの造詣が特に深い者と裾野の広い知識を持つ者の養成を両立できる点が秀逸です。各診療科の治験や研究には専従(専任)者が中心となって柔軟に対応し、全国規模での学会発表や講演をはじめ、原著論文の著者や国際学会での発表者も部内から輩出しています。またローテーション勤務にて懸念される診療レベルの低下については、研修計画/実施報告書や個人目標シートを活用し、主任との面談や成果の記載を通じて各々の長所の把握と弱点の克服に努めています。学生の教育については毎年30名程度の病院実習生の受け入れと100名程度の医学生対応を実施し、知識や技術は勿論、将来的な医療人としての心構えを含めた人材育成を目指しています。