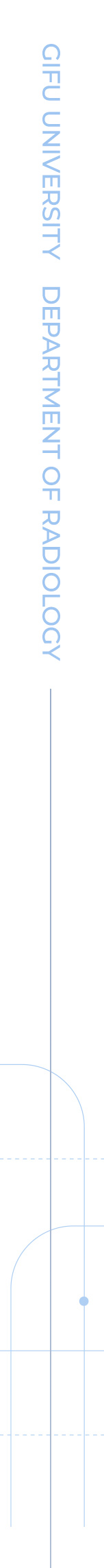血管系
一般事項
血管系IVRでは、CTやX線透視装置、エコー(超音波)といった画像装置を使いながら、血管やリンパ管にカテーテルを挿入し、病変の治療を行ったり、治療に必要な器具を留置したりする手技を行います。
当科では頭部・心臓以外の胸部・頸部・腹部・骨盤部・四肢などの体幹の全身の各領域の病変に対し、関連各診療科との密接な連携を保ちつつ、検査・治療を実施しています。外科手術に比べて小さな傷で実施出来る低侵襲な治療を提供しています。緊急時の救命処置を行うこともあります。
手技別・疾患別の実際
緊急止血術
当院は中部地区でも最大級の高次救命治療センターを有し、ドクターヘリも所持していることから、県内全域は勿論近隣県からも重症な患者さんが搬送されてきます。
中には外傷や内臓疾患により動脈が破綻し、大量出血を来している患者さんが搬送されてくることもあります。
このような患者さんを救命するためには造影CTを中心とした高度な画像診断技術で出血点を素早く同定し、IVRの技術を使って、カテーテルを出血点まで進めて止血を行う必要があります。
時にはステントグラフトを用いて、臓器血流を温存しつつ、止血を得ることもあります。
これらを実施するには経験を有したIVR専門医が必要であり、複数のIVR専門医が所属している施設は県内では当院に限られており、当科では高次救命治療センターをはじめとした各診療科医師との密接な連携のもと、県内最後の砦として24時間 365日体制で緊急IVRが実施出来る体制を整えています。
特に産後の出血に対する血管塞栓術は高次救命センターや産婦人科との連携の元で、日本有数の症例数(9年連続日本一)を誇り、多くの妊産婦の救命に寄与しています。
主な対象疾患
- 外傷性出血 (肝損傷、腎損傷、脾損傷、骨盤骨折など)
- 産科出血・周産期出血
- 腹部内臓動脈瘤破裂
- 腫瘍破裂による出血
- 術後合併症にともなう出血(膵液瘻に伴う仮性動脈瘤など)
腹部内臓動脈瘤に対する血管塞栓術
腹部大動脈から腹腔内の各臓器に向けて栄養を送るために複数の分枝が枝分かれしており、それらの動脈を総称して腹部内臓動脈と呼びます。具体的には肝臓や脾臓、腎臓、消化管などに向けた分枝を指し、それぞれ臓器名をつけて、肝動脈、脾動脈などと名前がつけられています。
これら腹部内臓動脈にも動脈瘤が形成され、時に破裂し、命に関わることがあります。
近年はCTやMRI等の機器の発達もあり、偶発的に指摘されるケースも増加しています。
多くの腹部内臓動脈瘤が20mmを目安に治療適応とされていますが、部位や瘤の形態等も加味し、他診療科とも連携を取りながら治療適応を判断しています。外科手術を行うこともありますが、近年では低侵襲な血管塞栓術(カテーテル治療)を行うケースが大半を占めます。当科では県内全域から腹部内臓動脈瘤のある患者さんをご紹介頂き、血管塞栓術を実施しています。
主な対象疾患
- 脾動脈瘤
- 腎動脈瘤
- 膵十二指腸動脈瘤
体幹部血管奇形に対する血管塞栓術
動静脈奇形とは動脈と静脈の間に異常なつながりが出来てしまう疾患です。本来体の中を流れる血流は心臓から動脈を介して全身に送られ、各臓器・細胞の周囲に張り巡らされた毛細血管を介して栄養や酸素のやりとりを行い、静脈を介して心臓まで戻っていきます。動静脈奇形の部分は多くは先天的な原因で、毛細血管を介さずに連続してしまうことで様々な問題を引き起こします。この異常な連続を「短絡(シャント)」と呼びます。
動静脈奇形は弧発性の事が多いですが、稀にオスラー病と呼ばれる遺伝性疾患(遺伝性出血性毛細血管拡張症:HHT)をお持ちの患者さんには複数の臓器に多発することもあります。
当科では主に体幹部に発生する血管奇形、特に動静脈奇形・動静脈瘻に対する血管塞栓術を実施しています。
オスラー病の患者さんに対する加療も行っています。
- 参考ページ③:難治性血管腫・血管奇形 薬物療法研究班情報サイト
- 参考ページ④:難病情報センター 「オスラー病(指定難病227)」
- 参考ページ⑤:HHT Japan HP
主な対象疾患
- 肺動静脈奇形 (Sporadic/Oslar病に伴う多発動静脈奇形)
- 腎動静脈奇形
- 骨盤動静脈奇形
大動脈瘤に対するステントグラフト治療・ステントグラフト内挿術後の合併症に対する血管塞栓術
当院では2009年より血管外科との協力体制のもと、的確な画像診断に基づいた腹部および胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術を施行しております。
大動脈瘤は動脈硬化の進行等により、徐々に血管径が増大し、そのまま放置していると破裂して、死に至る疾患です。当院では開腹せず、小さな傷で治療可能なステントグラフト内挿術を破裂時の緊急対応も含めて積極的に施行しており、東海地方でも有数の症例数を誇っています。また最新のCTおよびMRI撮像技術を用いてより正確に、血管解剖を把握し、合併症の少ない、質の高い治療を提供しています。
前述のステントグラフト内挿術の治療後に経過観察を行っていると中には追加治療が必要な患者さんがいらっしゃいます。その多くは治療後の動脈瘤腔に既存の大動脈分枝から血液が逆流したり、ステントグラフト接合部からの血液漏出する等、「エンドリーク」と呼ばれる現象(合併症)が原因で、瘤内圧低下が得られず、場合によって瘤径増大を来すことがあります。特に元々の動脈瘤から分岐する動脈分枝からの逆流がその原因となることが多く、それに対し、経動脈的に塞栓術を行うことで瘤径拡大を防ぐ治療があります。
当院では、複数のカテーテルを組み合わせるなど最先端の技術を取り入れ、確実な治療を実現しています。
局所進行上顎洞癌に対するRADPLAT (放射線治療併用動注化学療法)
上顎洞とは複数ある副鼻腔と呼ばれる頭部に存在する空洞の中で最大のもので、頬の内側にあります。ここから発生した癌を上顎洞癌とよび副鼻腔がんの中では発生数の多い疾患です。副鼻腔炎を来す部位でもあり、初期症状では見過ごされやすく、発見されたときには進行しているケースもしばしば見られます。眼球や顎骨など重要な臓器の近傍に発生する悪性腫瘍であり、進行癌の場合、大変大きな手術になると共に様々な機能が障害され生活の質が低下することが懸念されます。
近年局所で進行した上顎洞癌に対し、標準的な放射線治療とIVRの技術を用いて抗がん剤を動脈に注入する動注化学療法を組み合わせたRADPLATと呼ばれる治療が注目されています。この治療はStageT3やT4とされる進行した場合が適応とされ、根治も目指せる治療になります。日本で実施しされた大規模な臨床試験(JCOG1212試験)でも、その有効性が報告されています(参考文献参照)。
当科では耳鼻咽喉科・頭頸部外科と協力し、県内でも数少ないRADPLATを実施している施設です。
- 参考文献:Homma A et al, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2024 Apr 1;118(5):1271-1281.
門脈系IVR・胃静脈瘤に対するBRTO (バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術)
肝臓には通常どの臓器にも存在する動脈、静脈の他に、主に消化管から栄養を集め、肝細胞の多くを栄養する門脈という特殊な血管が存在します。ウイルス性肝炎などにより生じる肝硬変や自己免疫性肝炎などにより門脈圧が上昇すると、胃静脈瘤をはじめとする様々な静脈の異常が発生し、時に命に関わることがあります。
胃静脈瘤に対するBRTO(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術)は日本で開発された血管内治療で、内視鏡的に治療困難な胃静脈瘤に対し、血流に逆らうように風船付きカテーテルを挿入し、塞栓物質を注入して静脈瘤内を血栓化させることで治療効果を得る治療です。胃静脈瘤が破裂した場合には緊急で実施することもあります。胃静脈瘤以外にも直腸や十二指腸などの腸管に関わる静脈に静脈瘤を形成し、出血を来したり、消化管静脈などを介して門脈と体循環に短絡(シャント)を生じ、肝性脳症などを来す場合があり、これらの病態にもBRTOの技術を応用するなど血管内治療を実施することがあります。
また肝腫瘍が存在し、外科手術(肝切除術)を行う際に、術後合併症としての肝不全を予防するために門脈自体を塞栓する(門脈塞栓術)を実施することがあります。経皮的に肝臓に向かって針を穿刺し、門脈にカテーテルを挿入することで塞栓術を実施します。
当科では当院では消化器内科・消化器外科と密に連携を取り、IVRの技術を活用してこれらのBRTOをはじめとする門脈系IVRを実施しています。
CVP留置術
中心静脈カテーテルポート(CVP)は中心静脈と言われる太い静脈に挿入されたカテーテルとポートと呼ばれるタンクを接続し、皮下に埋め込むことできる医療機器です。CVPを皮下に埋め込むことで、容易かつ安全に中心静脈への定期的な薬剤投与を可能にします。悪性疾患に対する全身化学療法の進歩、高齢化に伴う在宅医療の拡大、患者の質の高い生活への意識の高まり等の医療環境の変化や、各施設における医療安全への取り組みの中で、CVPの重要性は高まっており、留置術へのニーズも高くなっています。
当科では全身化学療法として、定期的に化学療法を実施している患者さんを中心に、様々な診療科の主治医から依頼を受け、画像ガイド下で安全にCVP留置を実施しています。
留置後には遠隔期にわずかながらトラブル(合併症)を生じることがありますが、当科では留置後のトラブル対応も一手に引き受けており、留置後からその管理まで重要な役割を担っています。
末梢点滴が取りにくいが、重要な点滴を継続的に行う必要がある場合も適応になることがありますので、不明な点があれば、お問い合わせください。
原発性アルドステロン症に対する副腎静脈サンプリング
原発性アルドステロン症は、腎臓の上にある左右の小さな内分泌臓器である副腎からナトリウムを貯留するアルドステロンというホルモンが多く分泌されて高血圧症や低カリウム血症を来す疾患です。高血圧のみを発症する場合もあります。
通常の高血圧症患者と比較しても、脳卒中や心筋梗塞などの心血管系合併症のリスクが高いとされている疾患で、積極的治療を検討すべき疾患です。腕の血管から採血(末梢採血)し、体内を循環している血中にアルドステロンが異常に分泌されていることを証明することで診断されます。
治療としては降圧剤の内服による内科的治療の他に、外科的治療として副腎摘出術を実施することがあります。
外科的治療を考慮する場合にはアルドステロンを異常に分泌している副腎が左右どちらであるか(あるいは両側か)を同定する必要があります。しかし末梢採血のみでは左右の副腎どちらから主にアルドステロンが産生されているかが分からないため、その判別のために実施する検査が副腎静脈サンプリングになります。
副腎静脈サンプリングは足の付け根の静脈(大腿静脈)からカテーテルを挿入し、左右の副腎静脈から別々に採血することで、アルドステロンを異常に産生している副腎を同定する検査です。そのため内科的治療を実施する場合には必ずしも実施する必要はありませんが、外科的治療を考慮する場合には実施することが強く推奨されています。
当科では内分泌内科と密に連携し、副腎静脈サンプリングを実施しています。
リンパ漏に対するリンパ管造影・リンパ管塞栓術
体内にはリンパ管が無数に張り巡らされており、リンパ液を全身に循環されています。リンパ管は静脈とつながっており、血管と密接な関係があります。
外科的手術や交通事故などの外傷によってリンパ管が損傷すると、リンパ液が持続的に漏出(リンパ漏)してしまい、胸腔や腹腔、皮下などに異常に貯留してしまうことがあります。
リンパ液は免疫や栄養維持にも重要な役割を果たしているため、リンパ漏が発生し、改善しないと栄養が維持できなくなったり、感染症にかかりやすくなってしまうことから命に関わることがあります。
原因がわからず、突然リンパ漏が発生することもあります(特発性)。
これらは長年有効な治療法がないとされていました。
2010年代から米国を中心に、IVRの技術を応用してリンパ節を穿刺して特殊な造影剤を注入することで、リンパ漏の診断を容易にし、さらにリンパ管内にカテーテルを挿入して塞栓術(本邦では現状保険適応外)を行い、患者さんを救命することが出来る事が明らかとなってきました。これらの手技を総称してリンパ系IVRと呼ぶこともあります。
当科でも特に術後合併症としてのリンパ漏を中心に、難渋する患者さんにIVRの技術を提供しています。