朱牟田夏雄訳『トリストラム・シャンディ』より、
引用はすべてロレンス・スターン作、朱牟田夏雄[しゅむた・なつお]訳『トリストラム・シャンディ』全3巻(岩波文庫、初版1969年)からのものです。この版は長く品切重版未定になっていましたが、「復刊ドットコム」での復刊運動などの成果が実り、2006年7月に重版再開されることになりました。
なお、引用の中の……は省略箇所、[ ]内はルビを示します。傍点「ヽ」によって強調されている語句は、便宜的に斜体字で表わしました。また、引用の前後にある[ ]内の文章は、引用された場面の背景を説明するために私(内田勝)が補足したものです。
われ筆を使ふにあらず、筆われを使ふなり
[語り手トリストラムは、前の巻で予告した哀切きわまりない「ル・フィーヴァーの物語」を、読者をさんざんじらせた後でいよいよ語り始めるのだが、例によってたちまち脱線し、トリム伍長の膝の話を延々続けてしまう。]
ル・フィーヴァーの物語
連合軍がデンダモンドを占領した、その同じ年の夏のある日でした——これは私の父が田舎に引っこんだのより七年ほど前で——叔父トウビーとトリムとが、ヨーロッパでも指折りの堅固な城を築いた都会のいくつかに、これまた指折りのみごとな包囲の陣を敷くべく、ひそかに私の父の都の家を出奔したのよりは、同じく七年ほど後のことになります——ある晩のこと叔父トウビーは夜食をとっており、トリムは小さな脇づくえを前に、叔父の後方に腰をおろしていました。——腰をおろして、と申すのは——伍長の膝がわるいのを考慮して(時としてこれは激痛を与えるのでした)——叔父トウビーは晩餐にしろ夜食にしろ一人で食事をするときは、伍長が立って侍[はんべ]ることを絶対にゆるさなかったのです。一方この伍長が主人に対して抱く尊敬の念というのはこれがまたたいへんなものでしたから、叔父トウビーのほうにしてみると、適切な砲兵隊の援軍をえてデンダモンドの城を打ちやぶるほうが、トリムにこの点を承服させる労にくらべればまたしも楽なくらいでした。現に叔父トウビーは、伍長が脚をやすませているものと思ってふとふり返ってみると、自分のうしろにうやうやしい不動の姿勢で直立しているのを見つけるということが、何度もあったのです。これがもとで両者の間に小さないさかいが起った回数は、二十五年の間に他の原因によって起った不和の回数を総計したよりも多いのでした。——がこれは本題とは関係のないこと——なぜこんなことを書きつける気になったのか——それは私のペンに聞いて下さい——ペンが私を支配するので——私がペンを支配しているわけではありませんから。
(中巻 pp.258-9[原著の第6巻第6章])
園中に堡寨を築いて敵なきの防戦に余念なく
[股ぐらに傷を受けて退役になり、兄ウォルターのロンドンの屋敷で療養生活を送るトウビー・シャンディ大尉は、部屋にこもり、城郭都市の地図と書物に埋もれて築城術の研究をしている。しかし部下のトリム伍長はもっといい方法を提案する。]
——私の考えでは——とトリム伍長です——……こうやってこの紙きれの上で見ますと、せっかくの三日月堡も稜堡も幕堡も、角堡も、まったく情ないあわれな貧相なものにしか見えません。そこにゆくともし隊長殿と私とが、二人だけで田舎に住まって、どうなりと好きなように使ってよい地面を一ルードか一ルード半も手に入れたと致しますと、二人の手でどれだけのものが作れることでしょう!……。
叔父トウビーの顔は、トリムの話が進むにつれて朱を注いだように真赤になりました。……叔父はトリム伍長の提案なりその説明なりにもう夢中でした。……われわれが事をはじめるのは、トリムがつづけます、国王陛下と陛下の連合軍とが行動を開始するその同じ日にしてもよいと思います。そして町から町へと敵を粉砕してゆくのも、これまた陛下と——トリム、もう何もいうな、叔父トウビーが言います。——隊長殿は、トリムがつづけます、こういうよい天気ですから、その安楽椅子に(と現物を指さして)かけていて下さい、そして指図さえして下されば、あとは私が——もう何もいうな、トリム、叔父トウビーが言います。——それに隊長殿は、単になぐさみごとや面白い暇つぶしが得られるだけでなく、——澄んだ空気や、運動の機会や、ひいてはすぐれた健康も得られましょう。——隊長殿の傷などは一カ月でなおってしまうでしょう。——トリム、もうそれ以上言う必要はない——叔父トウビーが言います……おまえの提案はこの上なく気に入ったよ。
(上巻 pp.164-7[原著の第2巻第5章])
さて町もそのとりでも全部完成すると、叔父トウビーと伍長は第一線の平行壕を掘りにかかりました——それも、出たらめや行きあたりばったりではありません——連合軍が彼らの平行壕を掘りにかかったのと同じ地点、同じ距離からはじめるのです。そして毎日の新聞から叔父トウビーが受ける情報をもとにして、自分たちの進撃を規制しつつ——包囲戦の全期間にわたって、連合軍と完全に歩調を合わせながら進軍してゆくのです。
モールバラ公爵が橋頭堡を作ったといえば——叔父トウビーも橋頭堡を作りました。——ある稜堡の前面が粉砕された、あるいはある防塁が破壊されたといえば——伍長は鶴嘴[つるはし]をふるって同じだけのことをしました——それをくりかえしつつ——一歩一歩と前進し、つぎつぎととりでを占領して行って、結局は町そのものが二人の手に落ちるのでした。
ひとの楽しそうな様子を見てよろこぶという人にとっては、——モールバラ公爵が敵の本城の一部に進入可能の突破口をつけたという時の、郵便配達日の朝以上にすばらしい見ものは、到底あり得なかったでしょう。——そういう時にあのしでの木の生垣のかげに立ってさえいれば、私の叔父トウビーが、トリムをうしろに従えて、猛烈な勢いで出撃してゆくのが見られたのです。——一人はガゼット新聞を手にしています——もう一人は鋤を肩にして、新聞の報道通りを実行して行きます。——城壁に進み寄ってゆく叔父トウビーの表情に、何というすなおな勝利の色が浮かんでいることでしょう! 伍長の上に立ちはだかるようにして、営々と鋤をふるっている伍長が誤って突破口の幅を一インチでもひろげ過ぎることがないようにと——あるいはまた一インチでもせま過ぎることもないようにと、報道の文章を十遍もくり返して読んできかせている叔父の眼に、何という熱烈な喜びが踊っていることでしょう!——が降服を知らせる太鼓が打ちならされ、伍長が叔父に手を貸して突破口をよじ登らせ、さらにそのあとにつづいて伍長自身も軍旗を手に踊りこんで、城壁の上にその軍旗を押し立てたとき——ああ、天よ! 地よ! 海よ!——いや、こんなものに呼びかけて見たところで何の役に立ちましょう——地水火風、水分のあるのもないのもすべていっしょにして見たところで、これほどにも感激的な一瞬を作り上げることはこの手合いの手ではとてもできないのです。
(中巻 pp.306-7[原著の第6巻第22章])
一瞥老士官を悩殺せる孀婦「ウワドマン」
[トリストラムは、読者がウォドマン夫人の姿を絵に描くための白い紙を、本の中に用意している。]
そういうわけで、恋が何であるかはさておくといたしまして——私の叔父トウビーはその恋に落ちたのでした。
——いえ、事によると、やさしい読者がたよ、あれだけの誘惑に接するとなったら、——あなた方にしても同じことになられるかも知れません。あなた方の目が、あるいはあなた方の貪欲な色欲が、この世であのウォドマンの後家以上に色欲をそそり立てる対象にぶつかったことは決してないのですから。……。このことを正しく認識していただくために——どうぞペンとインクをとりよせて下さい——紙はお手もとに用意してあります。——そこでどうぞお席におつきになって、この女性の姿をお心のままにここに描いてみて下さい——できるだけあなたの恋人に似せてでも——奥さんにはあなたの良心がゆるすかぎり似せないようにでも——それはどっちだって私はかまいませんが——ただあなたの空想だけは満足させて上げて下さい。
——やっ! 自然界にかくも甘美なものがあろうか! かくも美しいものが!
——それならば、皆さん、どうして私の叔父トウビーにそれに抵抗する力があったでしょう?
(中巻 pp.344-6[原著の第6巻第38章])
[やがてウォドマン夫人はトウビーを誘惑するために、目に入ったゴミを見てほしいと言って近づく。トウビーは「太陽の黒点をさがし求めたガリレオの二倍くらいの善意さで」ゴミをさがそうとするが見つからず、夫人の目の中に「ゆらゆらと静かに燃えている甘い炎」を見るばかりである。]
奥さん、あなたの眼の中には、叔父トウビーは申しました、何もはいってなどいませんよ。
白眼じゃないんですのよ、ウォドマン夫人は言いました。叔父トウビーは全力を傾注して眸の中をのぞきこみました——
古往今来この世に創り出されたありとあらゆる眼の中で——それは奥さん、あなたの眼からはじめて上[かみ]はあの、人間の顔に宿った最も欲情的な眼にちがいないヴィーナスその人の眼までを含めて——今叔父トウビーがのぞきこんでいるその当の眼以上に、叔父の心からやすらぎを奪うという目的にかなった眼は考えられません——その眼はキョロキョロ廻転する眼ではありません——はねまわるいたずらずきの眼でもなければ——キラキラとかがやく眼でもなし——すねた眼でも権柄ずくの眼でもなし——高飛車な主張やものすごい要求をつきつける眼でもありません。もし万が一にもそんな眼だったら、叔父トウビーの胸にみなぎるミルクのような人情味は、たちまちコチコチに固まってしまったでしょう——その眼にみちあふれていたものは、やさしい挨拶であり——柔らかな応答であり——つまりそれはものいう眼だったのです——と申してもそこらにある出来そこないの楽器の一番高い音みたいな、お粗末なキーキー声で会話をする眼というのにも私はたくさんお目にかかりましたが、ああいう類とはまるでちがいます——いわば柔らかにささやく眼でした——ちょうど瀕死の聖者の、いよいよご臨終という時のような低い声音で、その眼はささやきました——「どうしてシャンディ大尉さま、あなたは慰めもないおひとりきりの暮しなどしておいでになれるのでしょう——そのおつむりをもたせかけるふくよかな胸もお持ちにならず——胸のご心配を打ち明ける相手もないままで?」
ああ、その眼こそは——
がこれ以上一言でも書きつづければ、私自身がその眼のとりこになってしまうでしょう。
(下巻 pp.177-8[原著の第8巻第25章])
彼等は皆自家随意の空気中に生息し
——かの偉大なクナストロキウス博士は、暇さえあれば驢馬[ろば]の尻尾[しっぽ]を櫛[くし]ですいて、老廃した毛を見つけると、毛抜きは常にポケットに持っているのに、自分の歯でそれを抜きとることに無情のよろこびを感じたというではありませんか。いや、そういう話になれば、あらゆる時代を通じていかなる賢者といえども、それはソロモンその人さえ例外でなく——それぞれの道楽を持っていたではありませんか。——馬を走らせたり——貨幣や帆立貝の貝殻を集めたり、さては太鼓やラッパや提琴だったり、パレットだったり、——あるいは蛆虫[うじむし]だったり蝶々だったり。——そして、ひとがその道楽の馬にまたがって、天下の大道をおだやかに静かに走らせて、あなたや私にこのうしろに乗れなどと強制しないかぎりは、——そりゃ、あなた、それはあなたや私とは何の関係もないことじゃありませんか。
(上巻 p.48[原著の第1巻第7章])
ある人間とその道楽馬とが、魂と肉体との相互作用とまさしく同じような作用、反作用をお互いに及ぼし合うとまでは言えないとしましても、それでもやはり両者の間には一種の通い合いがあることは疑問の余地がなく、私の意見では、この二者の関係には、電気を帯びた物体同士のそれに似たものがあるように思います。——それは、乗り手の体の、道楽馬の背中に直接接触する部分が、熱せられることで起るようです。——長い間馬を走らせ、摩擦が重ねられてゆくうちに、ついには乗り手のからだがはち切れんばかりに馬的要素で充満することになる——その結果は、馬のほうの性質をはっきりと記述することさえできれば、それだけで乗り手の天分なり人柄なりが、かなり正確に把握できるということになるわけです。
(上巻 p.137[原著の第1巻第24章])
吾が数(しばし)ば話頭を転じて、言説多岐に渉るは、諸君の知る如く少しも不都合なき事なり
余の話頭は転じ易し、されども亦進み易し
……現在私がはからずも迷いこんでしまったこの長い脱線ですが、ここには私のすべての脱線の場合と同じく……、脱線術としての入神の妙技が秘められているのです。がそういう秘術を残念ながら読者諸賢は終始見おとしておいでらしい——それは何も諸賢に洞察の力がないからというのではなく——ただ、このような神技が脱線というものに普通予想も期待もされないからにほかなりません。——それというのはこういうことです。たしかに私の脱線ぶりは、諸賢も御覧の通り公明正大なものであり、自分の従事している仕事をそっちのけに、大英帝国のいかなる文士にも負けぬほどに、遠いかなたまで、またそれも機会あるごとに、逸脱してしまっているにはちがいありませんが、それでいて私は、私の留守中といえども私の本来の仕事が歩みをとめてしまわないような布石だけは、一瞬も忘れていないのです。
たとえば私はつい先刻も、わが叔父トウビーのこの上なく気まぐれな性質について、その大きな輪郭をお伝えする仕事にかかっていました——そこに突如として私の大伯母ダイナーと例の馭者が飛びこんで来て、われわれを何百万マイルのかなた、わが太陽系のまっただ中までも拉[らっ]し去ってしまいました。にもかかわらず叔父トウビーの性格の描写は、その間も絶えず静かにつづけられていたことは諸賢もお認めでしょう——なるほど大きな輪郭のほうではない——それはとうてい不可能でした——しかしあちらでちょっと砕けた一筆、こちらでかすかにほのめかす暗示という類が、脱線話の途中でも随所に叔父の性格に添加されて、その結果は皆さんは私の叔父トウビーについて、前よりもはるかに知見を肥やしていらっしゃるわけです。
このような工夫によって、この私の著作の仕組みはまことに無類独特のものになっております。二つの相反する動き、お互いに両立はできないと考えられた動きが、この著作に持ちこまれて、しかも融和している——一言でいうならば私の著作は、脱線的にしてしかも前進的——それも同時にこの二つの性質を兼ね備えているのです。
(上巻 pp.129-30[原著の第1巻第22章])
「ヨリック」の最期
ヨリックが最後の息を引きとる二、三時間前に、ユージーニアスは最後に一目逢って永の別れも告げようと、その室に入ってゆきました。彼がヨリックのベッドのカーテンを引いて、気分はどうだい? とたずねますと、ヨリックは友の顔をまともに見上げて、その手を握り、——いろいろと生前に見せてくれた友情の数々に例を述べ、もしあの世でも再び君と逢うめぐり合わせになるならば、——その時はまたくり返しくり返しお礼を言いたいと言ったあと、——もう二、三時間のうちに敵の奴らを永久にまいてやることになるよ、と言いました。——そんなことはあるもんか、ユージーニアスは涙をハラハラと流しつつ、男としてこの上はないような親身な口調で答えました。——そんなことがあるもんかね、ヨリック。——ヨリックはまたそれに答えようと、顔を上げ、ユージーニアスの手をやさしく握りしめましたが、それっきりでした。——ユージーニアスは心をかきむしられる思いで、おい、おいどうした、ヨリック! と、涙をぬぐいつつ心中の勇気をふるい起して、——クヨクヨしてはだめだ!——この、勇気と剛毅の一番必要な時に、そんなに意気地のないことでどうする!——まだまだどういう救いの手が用意されているかわからないし、神の力はまだまだ君のために何をして下さるかわからないじゃないか? と言いました。——ヨリックは手を胸において、静かに頭をふりました。——ぼくとしては、ヨリック君、ユージーニアスははげしく泣きながら言葉をつづけました——君と別れるなんて思いもよらないことだ、——まだまだ君には主教[ビショップ]にくらいなれるだけの気力は残っているはずだし、また君がそうなるのをいずれはこの目で見届けられるという望みを捨てたくないのだ——そうユージーニアスは声をはげまして言いました。——お願いだからユージーニアス——ヨリックは左手で辛うじて寝帽[ナイトキャップ]をぬぎつつ言いました——右手はまだユージーニアスの手に、しっかり握られたままだったのです——お願いだからちょっとぼくの頭を見てくれないか。——別にどうもないじゃないか、とユージーニアスが答えます。それじゃ言うけどね、とヨリック、ぼくの頭は××××や××××やそのほかの連中に卑劣にもくらやみで襲われたおかげで、ひどく傷がつき形もかわってしまった、だからサンチョ・パンサの言い草ではないが、かりにぼくが回復して、「主教のかぶりものが天上からわが頭に霰[あられ]のごとく一面に降りそそぐことがあろうとも、その一つとしてこの頭に合うものはありゃしないのさ」——ヨリックがこう言った時、その呼吸はふるえる唇の上に、本当にこれが最後の一吸いになるかのようにおぼつかなく動いていました。——でもこの言葉だけは多少ともセルバンテス流の皮肉な口調で発されました。——またそれを言ったとき、その目にもチラリと光る一条の火が一瞬きらめくのをユージーニアスは認めました。——それは(ヨリックの先祖についてシェイクスピアが言ったように)「生前満座を爆笑させる習わしだった」あの機智の閃めきを、かすかに伝えるものだったのです。
ユージーニアスはこの事から、友の心がすでに打ち砕かれたものと確信しました。彼は友の手を握りしめ、——それからさめざめと涙を流しつつ静かに部屋を出てゆきました。ヨリックはユージーニアスの姿を、扉のところまで目で送りました——そしてその目をとじましたが、——その目はそれっきり開かれませんでした。
(上巻 pp.74-6[原著の第1巻第12章])
「スラウケンベルギウス」の話
[ある夏の日の夕暮れ、騾馬に乗ってシュトラスブルグの町の門に現われた、とてつもなく大きな鼻を持つ旅の男は、一カ月後にまた戻ってくることを告げると、フランクフルトへ向かって去っていった。]
男がフランクフルトにむけて一マイルとは進まないうちに、シュトラスブルグの町は町をあげて、男の鼻のことで大さわぎになりました。夕の祈祷を告げる鐘の音がちょうど鳴りひびいて、市民たちに祈りを忘れるな、祈りで一日の仕事にしめくくりを、と呼びかけていましたが——町中のだれ一人、そんなものに耳を貸すものはありません——まるで町中が蜂の巣をつついたようでした——男も女も子供たちも(夕の祈祷の鐘はその間も鳴りひびいていましたが)右往左往——片方のドアから走りこむと他方のドアからとび出す——あちらへ行きこちらへ行き——縦に横に——一丁目をかけのぼって二丁目をかけ下る——こっちの横丁へとびこんであっちの横丁からかけ出る——そして口々に言う言葉は、見たか? 君は? 見た? 本当に御覧になった?——だれが見たの? 見たのはだあれ? だれが見たのか本当に教えて!
(中巻 pp.11-2)
その鼻がシュトラスブルグの人々の夢想の中にひき起した騒動と混乱は、まことに町全体にゆきわたりました——シュトラスブルグの人々の頭は、その全能力をこの鼻のために完全にまた圧倒的に支配されました——まことに数かぎりのない不思議な事どもが、それもどっちを見ても負けず劣らずの自信にみちて、またどの方角からも相譲らない能弁で、この鼻について語られもし、断言もされて、町中の会話の流れ驚嘆の流れが、ことごとくその鼻のほうにと方向をかえました——一人残らずの人間が、善人も悪人も——金持ちも貧乏人も——学のあるのも学のないのも——学者も学生も——恋を知った女も恋を知らぬ乙女も——紳士も野人も——シュトラスブルグ中の尼さんの生身[なまみ]も俗人女の生身も、その鼻についての情報を聞くことに時をつぶしました——シュトラスブルグ中の目という目が、その鼻を一目みたいと恋いこがれました——指という指、手という手が、ちょっとでもその鼻にさわりたいとじりじりしました。
(中巻 p.19[原著の第4巻「スラウケンベルギウスの物語」])
[なおトリストラムは第3巻で、「鼻」という言葉が読者にいかなる不純な誤解も与えないように、「鼻」が意味するところの明確な定義を下している。]
さて私は、この「鼻」という言葉を敢えてふたたび使用する前に——そのことで予想されるさまざまの論議に混乱の生ずるのを防ぐために、この私の物語のまさに佳境に入ろうとするこのあたりで、私自身の意味するところを説明し、この「鼻」という語に私がどういう意味をもたせていると理解されたいのかを、可能なかぎり正確精密に定義しておくことも、徒事ではないと考えます。……。
……天も証人になってくれると思いますが、曖昧な批評のはびこる余地をこの私が多く残しておいたことが——また私が終始、読者の心中に不潔な想像の働くことなどないものとすっかり頭から信じていたことが——どれほど世間に、私に対して手痛い復讐[しかえし]をさせる原因になったことでしょう! ……。
私は鼻という言葉をこう定義して一つにきめます——ただあらかじめ読者諸賢に、それは男女、年齢、肌の色、身分等の如何を問わず、すべての読者に、懇願もし懇請もしたいのは、後生ですから悪魔の誘惑やほのめかしから身を護っていただきたい、悪魔がたとえどんな秘術や奸計を用いようとも、私がこれから定義の中で申す以外の解釈を皆さんの頭の中に吹きこませないように、ということです。——というのは「鼻」という言葉によって、鼻についてのこの長い章の全体を通じて、また「鼻」という語の出て来る私の著作の他の部分においても、ここに私ははっきり宣言しますが、その言葉によって私が意味するものは、鼻そのものでこそあれ、それ以上でも以下でも決してないのですから。
(上巻 pp.342-4[原著の第3巻第31章])
悽楚なる「ル、フェヴル」の逸事
翌朝の太陽は村中のだれの眼にもあかるく映りましたが、ル・フィーヴァーと、悲嘆の中にいるその息子との眼にはそれも別の映り方をしました。死の手がすでに重く中尉のまぶたをおさえていたのです。——さて、ふだんより一時間も早くベッドを離れた私の叔父トウビーは、井戸の釣瓶[つるべ]をまき上げる輪が一まわりまわり終えたか終えないうちに——中尉の室にはいって来、前おきも挨拶も抜きでベッドのかたわらの椅子に腰をおろすと、作法やらしきたりやらは一切おかまいなしに、古なじみの将校仲間がするだろうようなやり方でベッドの帷[とばり]をついと引きあけて、早速気分はどうかとたずねにかかりました。——昨夜はよく眠れたかどうか——何か訴えたいことはないか——どこか痛くはないか——何かこのわたしにできることはないか、と問いを連発して——そのどれかに答えるだけの暇などを与えればこそ、さらに言葉をつづけると、前夜中尉のために伍長と案を練り合っていた、ちょっとした計画を話しはじめました。——
——ル・フィーヴァー君、叔父トウビーは言いました、君は今すぐわしの家に引きとることにする——そうしたら医者をよんでどこが悪いのかを調べさせる——薬屋もちゃんとよぶし——伍長を君の看護人にする——それからわしは、ル・フィーヴァー君、君の召使役だ。
叔父トウビーの飾り気のなさは——これは親しさの結果ではなくて、むしろその原因になるものですが——たちまち相手に自分の心の奥をひらいてみせ、天性の善良さをさとらせます。それに加えて、叔父の顔つき、声、態度などに具わる何かしらも、悲運に泣く人たちにむかって、きたってこの人の庇護を受けよと永遠に手招きしているおもむきがあります。そういうわけで叔父トウビーが父親のほうに誘いかけた親切な申し出を半分も言い終えないうちに、息子のほうは思わず知らず叔父の膝にひしとすり寄ると、叔父の上着の胸をつかんで、自分のほうに強く引きよせていました。——ル・フィーヴァーの体内ではその血液も生気も、すでに冷たくまた緩慢になりかけて、その最後の砦である心臓のほうに退却を開始していましたが——ふたたび陣容を立てなおしました——眼をおおいかけていたもやのような膜も一瞬また晴れ上りました——中尉は希望にみちた眼を叔父トウビーの顔のほうに上げ——それから自分の息子に一瞥[いちべつ]をむけました——その三者をむすんだえにしの糸は、ごく細いものであったとはいえ——ついにたち切れることはなかったのです。——
生気はあっという間にふたたび引きはじめました——眼のもやも、もとにもどりました——脈がみだれました——とまりました——また打ちました——トントントンと打って——またとまりました——また打った——またとまった——もっと書きつづけましょうか?——〈いえ、もう結構です〉
(中巻 pp.275-6[原著の第6巻第10章])
噴飯すべき栗の行衛
[フュータトーリアスが気づかないうちに、焼けた栗が一つ、彼のズボン穴の中へ転がり込んだ。]
栗のもたらしたほどよい暖かさは、最初の二十秒ないし二十五秒の間は不快なものではなく——フュータトーリアスの注意を局所のほうにおだやかに誘う以上のものではありませんでした。——しかし熱さは次第に上昇して、もう数秒たつうちには、おだやかな快さなどという程度は通り越し、つづいてたいへんな速力で苦痛の領域に進入しましたから——そこでフュータトーリアスの魂は、頭の中の思想、考察力、注意力、想像力、判断力、決断力、慎重さ、推理力、記憶力、空想のことごとくを動員、さらには十個大隊の動物精気をも率いて、それぞれ別々の隘路や迂回路を通り、危険に襲われたその局所へと、喧々囂々[けんけんごうごう]雲霞[うんか]のごとく群がり下りました。その結果は上のほうの諸地域が、まるでこの私の財布のごとくに空っぽになってしまったことは、ご想像に難くないところです。
しかしながら以上のような多数の使者がもたらし帰ることのできた最上の情報を検討してみても、フュータトーリアスは一体下のほうで何がはじまっているのかの秘密をうかがい知ることができず、何がどうなったのやら何の臆測を下すこともできません。とはいえ、真の原因がどういうところにあるのかはわからないなりに、今自分が置かれている状況にあっては、これは禁欲主義者のごとくに可能なかぎり堪え忍ぶのが最も賢明な態度だと彼は考えました。また事実、顔をしかめたり唇をキュッと結び合わせたりの応援の下に、この努力は大いに続けられて、もしこれで想像力さえ中立の態度を守ってくれたなら、必ず成功したことだったでしょう。——がこういう場合に想像力が抜け駆けにとび出そうとするのは、おさえ切れるものではありません——一つの考えがたちまち彼の頭に駈け上ります——たいへんな熱さの感覚はたしかにあるけれども、でも事によるとこれは火傷でなくて、何かに咬[か]まれたという可能性もある。だとするとこれはあるいはいもりとかやもりとか、何かそういう恐ろしい爬虫類が下からしのび込んで、歯を立てているのかも知れない。——そういう恐ろしい考えが頭に伝達されたのと、ちょうどまたその瞬間に新しい焼けつくような痛みが栗から発生したのとが一緒になって、フュータトーリアスは突如恐慌におそわれ、そこから来る瞬間的なものすごい感情の混乱のうちに、かつて三軍を叱咤する名将たちの上にも同じことが起ったように、フュータトーリアスもまったくわれを忘れました。——その結果が彼があっという間に突ったち上って、それと同時に、あの大いに論議の種となった驚きのさけび声を発するということになったわけです。
(中巻 pp.110-1[原著の第4巻第27章])
われ出鱈目に此篇を書かんと思う念頻なり
私は今度のこの章を、きわめてノンセンス式に切り出して見たいという強い誘惑を感じます。また、そういう思いつきのさまたげはしたくない——となるとこんな書き出しはどうでしょうか。
もしもモーマスのガラスが、あの大あらさがし屋先生の修正提案どおりに、人間の胸にとりつけられた場合を考えて見ますと——まず第一にはつぎのような馬鹿馬鹿しい結果が生じましょう——それは、人間の中のどんな賢者でもどんな謹厳居士でも、生涯を通じて来る日も来る日も、何らかの形で窓[まど]税を払わされたにちがいないということです。
次に二番目には、そのようなガラスが胸にはめこまれたとしたら、ある人間の性格をよみとるためになすべき仕事といったら、ただ椅子を一つ持って、中ののぞける蜜蜂の巣箱にでも近づくように、そーっとそのそばに寄って中をのぞきこむ、——そうして素っ裸の魂を仔細に吟味する——その動き工合やからくりのすべてを観察する——蛆虫[うじむし]然としたさまざまの気まぐれが、最初に生まれるところからモソモソ匐[は]い出すまでをつぶさに跡づける——魂が勝手気ままにはねたり踊ったり飛びまわったりするのを眺め、さらに、そうやってはねたり踊ったりしたあとの多少鹿爪らしい振舞も多少は斟酌[しんしゃく]したあとで——さて今度はペンを執[と]って、自分で見たこと、絶対まちがいなしといえることだけを書きつける——という以外には何も必要ない、ということになってしまうでしょう。——しかしこういうことはこの地球上に棲[す]む伝記者にゆるされそうな特権ではありません。
(上巻 pp.132-3[原著の第1巻第23章])
[なお、モーマス(Momus)はギリシア神話のあら探しと嘲弄の神。人間の胸に窓がなくてその中の秘密を探ることができないのを不満とした。そのエピソードはギリシアの諷刺作家ルキアノス(Lucianos, 120頃-180頃)の対話篇『ヘルモティモス』で語られているが、おそらくスターンはこの話をバートンの『憂鬱の解剖』から拾ってきている。また、イングランドでは1695年から1851年まで、窓に税が課されていた。]
「ヨリック」時としては其乱調子なる様子を以て
時としてこの男は独特のはげしい口調で、糞まじめな奴はとんでもない大悪党だ、と言いました。——それも、狡猾なだけに実に油断のならぬ悪党なんだ、とつけ加えました。——こういう手合にだまされて金品をまき上げられる正直な善意の人々の数は、一年間で、すりや万引きにやられる人数の七年分よりも大いにちがいない、ともいいました。陽気な心の持主がむき出しに本性を見せるのには、何も危険はない——彼はよく言いました——あるとすれば自分自身への危険だけだ。——そこへゆくと糞まじめの本質は陰謀だ、したがって偽りだ、——自分が持ちもしない分別や知識を、持っているかのように世間に信じこまそうとする、手のこんだトリックだ、——ずいぶん前にあるフランスの智恵者が、糞まじめを定義して「頭の欠陥をおおわんために見せる玄妙不可思議な身のかまえ」といったが、ずいぶんもったいぶってこしらえてはいても、実際、この定義以上ではない、いや、時には以下でさえある、——そういってはなはだ軽率にもヨリックは、この糞まじめの定義は金の文字で大書しておく値打がある、などというのでした。
が、率直にいって、この男はきわめて世事にうとい未熟者で、この糞まじめ論議だけではなく、どんな話題の場合にも、すこしはおのれを抑制するのが得策とされるような時でも、やはり無思慮な愚かな言辞を弄しました。何ごとによらず、物事から受けるヨリックの印象といえば一つだけ、それは、話題になっている人の行為の本質からの印象でした。そういう印象をヨリックは、通例何の衣[きぬ]も着せずに簡明な日常語に翻訳する——それもあまりにもしばしば、相手や時や所の見さかいもなしに、です。——したがって、たとえば誰かのあわれむべき卑劣なやり口が話題になれば——この男は、その話題の主[ぬし]が誰なのか——どういう身分の人物なのか——その人物が後になってどれだけ自分に復讐する力があるのか、等を瞬時も考えてみようとはせず——もしそれが下劣な行為であれば——あとさき見ずの単刀直入——「あいつは下劣な野郎だ」となります。——その上、この男の評言は、通例不幸にもピリッとした警句に終るか、さもなければ話中至るところに剽軽[ひょうきん]なユーモアに富んだ字句が躍動するので、それがまたヨリックの無思慮をあちこちに伝播することになる。……。
そういうことの結果がどうなったか、それがどうヨリックの悲劇的最期をもたらしたかは、次の章で御覧下さい。
(上巻 pp.68-9[原著の第1巻第11章])
心を以て tabula rasa に比したる哲学者あるを聞きぬ
一つ伺いますがあなたは、今までいろいろの読書をして来られた中で、ロックの『人間悟性論』という書物をお読みになったことがありますか?——いえいえ、軽率なご返事はなさらんで下さい——というのは、読んでいないのにこの本を引用する人がたくさんある、——また、読んだのだがわかっていないという人も少くない。——もしあなたもそのどちらかならば、私は教化のために筆をとる身ですから、その本がどういう本か、ごく簡単に申上げましょう。——これは記録の書物です。——〈記録だって! 誰の? 何の? どこの? いつの?〉——まあ、あわてないで下さい。——記録といってもこれは、(こう申すと世間にこの本を推奨することになるかと思いますが)人間の頭の中に起ることの記録なのです。もしあなたがこの書物のことをこれだけおっしゃって、あと一言もつけ加えないで置かれれば、形而上学者の仲間で笑いものにされる危険は絶対にありませんね。
(上巻 p.150[原著の第2巻第2章])
——父がその生涯の多年にわたって掟としていたのは、——どの月もどの月もきまって第一日曜の夜に……裏の階段のてっぺんにおいてあった大時計のねじを、自らの手でまくということでした。……父はこの時計のことのみでなく、ほかにも母親だけを相手のこまごました用事なども、だんだん同じ時期にかためるようにしていました。それというのも……すべてを一ぺんに片づけてしまって、あと一カ月の間はそういうことに煩わされずにサッパリとしていようがためだったわけです。
それはよいとしまして、これにはただ一つだけ不幸がともなうことになりました。……その不幸というのはほかでもありません。本来お互いに何の脈絡もない観念同士の不運な連合の結果として、ついには私の母親は、上述の時計のまかれる音をきくと、不可避的にもう一つのことがヒョイと頭に浮かんで来ずにはいない、——その逆もまた同じ、ということになってしまったのです。——あの賢いロックは、明らかにこのようなことの本質を大概の人よりもよく理解していた人で、かかる不思議な観念の結合が、偏見を生み出すもとになる他のどのような源にもまさって、多くのねじれた行為を生み出していることを確言しております。
(上巻 pp.41-2[原著の第1巻第4章])
吾説話の方法は頗る不規則にして頗る曲折せり
さてこのあたりからいよいよ話の本筋にはいってゆくわけですが、……これからは私の叔父トウビーの物語を、ついでに私自身の物語も、かなり直線に近い形で進められることを私は信じて疑いません。ふりかえって見ますと、
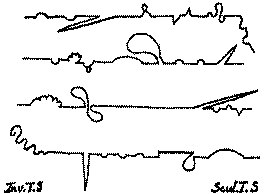
これがこの本の第一巻、第二巻、第三巻、第四巻でそれぞれ私が動いてきた線でした。——第五巻はたいへんうまく行って、——あそこで私がたどった線は、まさに次のようなものでした。
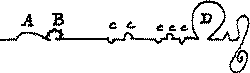
……この調子で私が進歩してゆくならば……今後はつぎのような模範的な進み方に到達することさえ、決して不可能ではありません。
これは私があるお習字の先生のものさしを借りて(わざわざこのために借りたのですが)、右にも左にもそれないように、できるかぎりまっすぐに引いてみた線です。
(中巻 pp.348-51[原著の第6巻第40章])
是免る可らざるの数なり、「マグナ、カータ」の第一条なり
哲学というものは森羅万象のすべてに立派な言葉を用意しています。——死ということに対しては、特に豊富に取りそろえてあります。困ったのはむしろ、それらが一斉に父の頭に殺到して来た結果、それらを適当につなぎ合わせて多少とも首尾一貫した体裁らしいものをそれらに与えることが困難だったことです。——父は殺到して来る奴を手あたり次第にとり上げました。
「これは必然の運命だ——マグナ・カルタの第一条だ——国会の定めた永遠の法令なんだ、トウビーよ——すべてのものは死すべきものなんだ。
「もしわしの息子が死なないとしたら、そのほうこそ奇蹟というものだろう——死んだことがじゃなくてだ。
「王侯君主といえどもわれらと同じ輪を作って踊っているのだ。
「——死とは自然というものに人間が支払うべき偉大な負債あるいは貢物だ。墳墓とか記念碑とかは、われらの記憶を永久にさせようと建てるものだが、これら自身もまたそういう貢物は支払わねばならない。それらの中でも、富と学問の粋をつくして建てた最も誇り高きピラミッドでさえも、すでにその頂上部を失って、旅人が歩を進めてゆく地平線上に、頭をちょん切られたまま立っているのだ」(父はずいぶんと気が楽になったことに気づき、さらにつづけました)——「王国も、州、県も、町村も、都市も、みなそれぞれの寿命を持っているではないか。そしてそれらを最初結合させ創建した主張とか権力とかも、それぞれの機動力を出しつくしおわれば、やはり屈する時がくるのだ」——兄上、と叔父トウビーが、機動力という言葉を聞きとがめて、パイプを下におきながらいいました——いや機動力ではない、発動力というつもりだったんだ、父が申しました——本当に冗談じゃない! 発動力というつもりだったんだよ、トウビー——機動力じゃばかげている——ばかげているなんてことがあるもんですか——叔父トウビーは申します。——でもこんな場合にこういう話の腰を折るなんてのはばかげているじゃないか? 父はさけびました、——頼むから——なあトウビー、と父は叔父の手をとってつづけました、頼むから——頼むからひとつ、この大事なところで話の腰を折るようなことはやめにしてくれ。——叔父トウビーはパイプを口にもどしました。
「トロイもミケネーも、テーベもデロスも、またペルセポリスもアグリゲンツームも今いずこにありや」——父は一度下においていた例の駅馬車路線の本をとりあげながらつづけました。——「ニネヴェーやバビロンや、キツィクムやミティレネーは、トウビーよ、一体どうなったのだ? かつては太陽の照らす最も美しい町だったものが、今は姿を消してしまった。名前だけはわずかに残っているが、その名前とても(もう今ではその多くは綴りを誤まられているし)徐々にバラバラに崩れ去って、時のたつうちには忘れ去られ、すべてのものとともに常闇の夜に埋もれてしまう。この世界そのものだとて、弟トウビーよ、いつかは——いつかは終末を迎えねばならないのだ。
「アジアよりの帰途、わが船のアエギナを後にメガラのかたにむかいし時」(一体いつの話なんだな、これは? 叔父トウビーは思案しました)「われはおもむろに四辺の陸地に目をやりぬ。アエギナはわが背後にあり、メガラは前方にあり、ピレーウスはわが右手、コリントはわが左なり。——さしもに栄華を誇りし幾多の都市が今地上に打ち伏してあるにあらずや! やめよ! やめよ! われは心中ひそかに思えり、かくも大いなりしものがわが前に恐ろしくも埋もれてありというに、うつし世の人の身が子を失いて心をかき乱す愚かさは!——忘るるなかれ、われはふたたび心に思いぬ——忘るるなかれ、汝、ただ人の身に過ぎざるを」——
さて私の叔父トウビーは、この最後の一節が、キケロを慰めようとセルウィウス・スルピキウスが書いた手紙から抜いて来たものとは、知りませんでした。——正直者ではあっても、古代の文書などには全然たしなみがなく、この断片の場合もそれは同じことだったのです。——それに私の父がむかしトルコ貿易に従事していたころ、三度か四度レヴァントに行っていたことがあり、そういう中の一度は、ザンテ島にまる一年半も滞在していたので、当然のことのように叔父トウビーは、父がそういう滞在期中のどの時かに、多島海をわたってアジアに旅行を試みたもの、そしてこのアエギナを背後に、メガラを前方に、ピレーウスは右手にあり云々という舟行の件も、父自身の航海と思索とが本当にたどった道にほかならないと判断したわけでした。——いかにも叔父らしい話ですし、それに、野心満々の批評家で、これにも及ばない基礎工事の上にこれより二階分くらい高い空中楼閣を築き上げてしまいそうな人物だって少くはないのです。——ちょっと伺いますが兄上、叔父トウビーはおだやかに話をちょっと休止してもらおうと、パイプのさきで父の手をつついておいて——しかし父の話の終るまで待った上で申しました——これは主の紀元何年のことだったのです?——主の紀元なんかじゃありゃしないよ、父が答えます。——そんなばかな! 叔父トウビーはさけびました。——阿呆な奴だな! 父は申しました——キリストのお生まれになる四十年前のことさ。
(中巻 pp.160-3[原著の第5巻第3章])
此人日夕身を築城学の研究に委ねて、中々其道の達人とぞ聞えし
——まことに、際限のないのは真理の探究です!
私の叔父トウビーは、砲弾がどういう道を通らないかの理解ができると、途端に知らず知らずせき立てられるようにして、それではどういう道を通るかをしらべて突きとめてやろうと心中に決心しました。そのためには新しくマルテュから出発する必要を感じて、熱心にその著書を研究しました。——次にはガリレオとトリチェリに進んで、そこに正確な弾道が抛物線——あるいは双曲線であることが、ある幾何学の原則を使って、絶対に疑問の余地なく明記されているのを知りました。また、その弾道の円錐曲線のパラメーターあるいは通径は、砲弾の飛量とその射程に正比例すること、ちょうどその全曲線と、砲身の尾部が地平面に対してなす発射角を二倍したもののサインとの関係と同じであり、またその半パラメーターは——よして下さい、トウビー叔父さん!——よして下さい! そういうとげだらけの、滅茶滅茶に入りくんだ道には、もうこれ以上一歩も踏み入らないで下さい——どこに足の踏み場所があるのかわからない! この上なくいり組んだ迷路じゃないですか! そんな魔法のわなのような「知識」などという幻を追ってゆけば、叔父さんの身の上にどんな厄介な面倒ごとが降りかかるかわかったもんじゃありません。——叔父さん、叔父さん、蛇から逃げ出すように逃げ出していらっしゃい。——第一、叔父さん、そんな鼠蹊部の傷なんか抱えながら、そんなに熱病やみみたいに血眼[ちまなこ]になって、来る晩も来る晩も徹夜して、血をたぎらせたりして、からだにいいと思ってるんですか?——そんなことしてたら、叔父さんの病気はますます悪化し——汗はとまり——精気は抜け、——動物的体力は消耗し——自然にあるべき体内の水分は乾いてカラカラになり——便秘の習慣は抜けなくなり——健康は滅茶滅茶になって——老衰の徴候が一度にどっと出て来ちまいますよ。——ねえ叔父さん、トウビー叔父さんったら!
(上巻 pp.156-7[原著の第2巻第3章])
「ウォルター」の時間を論ずる条
時間とは何であるか、ついでながらこれがわからないと無限ということも決して理解できない、というのは後者は前者の一部なのだからな、——この時間というものを正しく理解しようと思えば、われわれはまず腰を落ちつけて、われわれがもつ時間の経過という観念はどういうものであるかを真剣に考え、どうしてそういう観念がわれわれのものになるかについて、納得のゆく説明を試みる必要がある。——そんなことはどうだってよいではないですか、叔父トウビーが申しました。*もしおまえが目を内部にむけて自分の心中をかえりみ、父はかまわずつづけました、そこで丹念に観察するとすると、その時おまえも気づくだろうが、たとえばこうやっておまえとわしがおしゃべりをしながらいろいろ考えたりいっしょにパイプをくゆらしたりしている間、あるいはわれわれがいろいろな観念をつぎつぎに頭に受け入れてゆく間、われわれはその間自分が存在しているということを知るわけだ。そこでわれわれは自分のそういう存在を、あるいは自分自身の存在の継続を、あるいはまたそのほかのすべてを測るのに、われわれの頭の中に連続して生ずる観念に、あるいはわれわれ自身の経過に、あるいはまたわれわれの思考とたまたま共存する何でもいいほかのものの経過に、照らし合わせて測るということになる。——従って、規準としてあの先入主的な——何のことやら、私には死ぬほど退屈だな、叔父トウビーがさけびました。
* ロック参照のこと。
——そういうことのために、父は応じました、われわれは時間というものを測定するのに、すっかりもう分[ふん]とか時間とか週とか月とかいうものになれっこになってしまっている——つまり、時計というものに(このイギリスの王国中に時計なんてものが一つもなかったらどんなによいことか)たよって、われわれの、あるいはわれわれの親しい者たちの、それぞれ時間のわけ前を計算してもらっている——今後は、われわれの頭に相ついで生ずる観念というものが、多少とも時間を測る規準として役に立つようになったらよいだろうと思うのだがなあ。
ところで、われわれ自身が観察しようがしまいが、私の父はつづけました、すべて健全な人間の頭には、いろいろな種類の観念というものが規則正しくつぎつぎと発生して、それがあとからあとから列をなしてつづく有様はまるで——大砲の列よろしくですかな、叔父トウビーが申しました。——列などは何の列だってかまやせんが——と父は言って——とにかくあとからあとからと一定の距離を置いてわれわれの頭の中につづくところはといったら、蝋燭の熱でぐるぐる廻る走馬燈の内部のいろいろなものの影絵によく似ている。——私の場合などはさしずめ、叔父トウビーが申しました、走馬燈などよりも台所で肉を焼くときの焼き串まわしですな。——そういう与太ばかり飛ばすなら、トウビー、もうおまえにはこれ以上この話はせんわい、私の父が申しました。
(上巻 pp.299-300[原著の第3巻第18章])
愛といふ情をいろは順で並べたらば斯(こう)も有(あろ)うか
——恋とはまごう方なく、少くともいろは順にならべて申すかぎりは、
いざこざの多い
ろくでもない
はらのたつ
にがにがしい、等の点ではこの上なしの——
ほねの折れる
へんてこらいな
とほうもない
ちからのはいる
りくつ抜きの(ぬとるは飛んで)
をろかしい、などというも愚かで、同時に
わけのわからぬ
かなしい
よをまどわせる
たよりない(れはまたなしの)
つみの深い
そそっかしい——きわみのものなのです。もっともつよりはそが先に来べきところですが——
(下巻 pp.133-34[原著の第8巻第13章])
一匹の蠅は無遠慮にも、老士官の鼻頭に留りぬ
——行け——ある日の食事の時、叔父は、食事の間中鼻のまわりをブンブン飛びまわって散々に自分を悩ました、やけに大きな一匹の蠅——いろいろ苦労したあげくにそばを飛び過ぎるところをやっとつかまえたその蠅にむかって言ったものです。——おれはおまえを傷つけはしないぞ、叔父トウビーは椅子から立上って、蠅を手にして窓のほうに歩みながら言いました——おまえの頭の毛一すじだって傷つけはしないぞ——行け、と窓を上のほうに押しあげて、手を開いてにがしてやりながら——可哀そうな奴だ、さっさと飛んで行くがよい、おれがおまえを傷つける必要がどこにあろう、——この世の中にはおまえとおれを両方とも入れるだけの広さはたしかにあるはずだ。
これは私が僅か十歳の時の出来事でした。……私の全身が、誠に快い感動で一つになってふるえたのは、この行為そのものが、成人の後とはちがってあの涙もろい年ごろの私の神経にピッタリするものだったからかどうか——叔父の態度なり言葉なりが私を感動させるのにどこまでの力があったのか——また、声の調子にもなだらかな身のこなしにも慈悲の気持がゆきわたっていたことが、どの程度まで、またどういう人知れぬ魔力で、私の心に通ったのか——そういうようなことは私にはよくわかりません。——私にはっきりわかっているのは、その時叔父トウビーによって教えられ刻みこまれた、万物に善意をもって対すべきだという教えが、以後今日まで決して私の頭から消えていないということです。私は、大学で授けられた古典の学問がその点で私の力になってくれたことを低く評価するものでもなければ、またその後国内国外で私が受けた高価な教育のいろいろな助けを信用しないのでもありませんが、——にもかかわらず私の博愛の心の半分は、あの一回の偶然事の印象のおかげだと、私はしばしば考えるのです。
(上巻 pp.188-9[原著の第2巻第12章])
察する所此女は四十七歳の時四人の小児を残して其夫に先き立たれて
——この老婆、もとは四十七歳で夫に先立たれて、三、四人の小さな子供を抱えて悲嘆にくれる後家さんであったようです。ただその当時も身のこなしの淑やかな、——品行も生まじめな人物で——それに口数のすくない女であり、おまけにその立場は同情の的、深い悲しみと、さらにはその悲しみに黙々と堪えるさまとが、心ある者にいよいよ親身の助力を惜しまぬ気持ちをおこさせたわけで、その教区の牧師の細君がまず惻隠の情に動かされました。この人は、かねがね夫の教区民たちが、六、七マイルという長い道のりを馬でかけつけるより近いところには、たとえどんなに火急の場合でも、資格や程度は問わず、かりにも産婆と名のつく者がひとりもいないために、長年たいへんな不便にさらされているのを嘆きとしていました。その七マイルという長い道のりを暗夜にゆくのは、何しろそのあたりの土質ときたら深い粘土ばかりですし、道路も惨澹たるもので、ほとんど十四マイルくらいに匹敵した、ということは結局のところ、時によってはどこにも産婆がいないのと同じことだったのです。そこでこの細君の頭には、この気の毒な未亡人に産婆術の初歩の原理くらいを少々学ばせて、そのほうで身を立てるようにしてやったら、未亡人自身のためはもちろんのこと、教区民全体にとっても、はなはだ時を得た親切というものだ、という考えがひらめきました。
(上巻 pp.46-7[原著の第1巻第7章])
父は倚子を掻い遣りぬ、立ちぬ、帽子を被りぬ、戸の方に進む事四歩なり、
何とも残念なことだ、私の父がある冬の夜、三時間ばかり骨を折ってスラウケンベルギウスを訳してきかせていたあとで、さけびました——何とも残念なことだ、そういって、父は、母の、糸を包んだ紙を、目印に本にはさみました、真実というものが、なあトウビーよ、こうも難攻不落のとりでの中にピッタリと閉じこもってしまって、これだけ手段のかぎりをつくしての城攻めにも、頑としていっかな降参の様子もみせないというのは。——
この時たまたま叔父トウビーの空想は、こういうことは前にもしばしばあったのですが、父が自分にむかってプリニッツの説明をしてくれている間——何しろその話のほうには何も叔父をひきつけるものはないのですから、ちょっとすきを見て例のボーリングの芝生のほうに飛んで行っていました。——いや、できれば体のほうもそっちへ行って一まわりして来たいくらいのところでした。……。が今、父の比喩の中の「城攻め」という言葉が、まるで呪文の魔力のように、叔父トウビーの空想を引きもどしました。ひびきの声に応ずるようなすばやさでした——叔父は耳をすませました——父は、叔父がパイプを口から離し、かけている椅子をテーブルに引きよせ、一語も聞きのがすまいとするかのような様子を見てとると、——大よろこびでふたたび言葉をはじめました—— ……。
何とも残念だよ、父は言いました、……あれだけ大勢の学のある人たちが、みなそれぞれの才智をしぼっているのだから、鼻のことももっと解けて来るとよいんだが。——なに、鼻が溶けたりするんですか? 叔父トウビーが申しました。——
——父は椅子をうしろに押しやりました——立ち上りました——帽子をかぶり——大股に四歩、ドアのところまで行き——ドアを勢いよく開いて——頭を半分、外へつき出しました——それからまたドアをしめ——蝶番の工合の悪いのなどには目もくれず——テーブルのところにもどり——スラウケンベルギウスの本から母の糸包みの紙を引き抜きました——いそいで書き物卓[づくえ]に近より——今度は糸を包んだ紙を親指にクルクルまきつけながら、ゆっくりともとにもどりました——チョッキのボタンをはずし——糸の紙を火に投げこみ——母の繻子[しゅす]の針さしを歯でかみ切り、口じゅうをもみがらだらけにし、そこで悪態を一つつきました——
(上巻 pp.373-5[原著の第3巻第41章])
日に焦けたる労動の娘は群中より出でゝ余を迎へたり
私が連中のほうに歩み寄って行くと、野良仕事に日焼けした娘が一人、一群の中から立ち上りました。ほとんど黒といってもよい濃い栗色の髪が、きつくゆわえられて、ほとんど一束のようになってたれていました。
男の踊り手が足りないのです、娘はそういうとこの手をとれといわんばかりに両の手をさしのばしました——うん、踊り手に加わって上げよう、私も言ってその手を両方ともしっかりと握りました。
ああ、ナネット、あの時のおまえが公爵夫人のような装いをしていたらなあ!
——でも残念なことに、あのおまえのペチコートの隙間がねえ!
ナネットはそんなことにはとんと無頓着でした。
あなたにおいでいただけなかったらはじめるわけに行きませんでしたわ、娘はこういうと、だれに教わったのでもない自然のしとやかさで片手をふりほどき、もう一つの手で私を引っぱってゆきました。
脚の悪い若者が一人、その代償にアポロ神から笛の才を授かっているらしく、さらには本人が自発的に小太鼓まで加えて、堤に腰をおろすと、踊りの前奏曲を浮き立つように奏でます——この垂れている髪をいそいでゆわえちゃって頂戴、ナネットは言って、短い紐を私の手にわたしました——それに勇気づけられて私は、自分が異国人であることを忘れました——たばねてあった髪が全部パラリと落ちます——あとはもう、七年も前からの知り合いのようでした。
若者は小太鼓で曲をかなで——さらにその笛がつづいて、われわれも勢いよく踊りはじめました——「ペティコートの隙間などどうでもなるがよい!」
若者の妹が、天上から盗んで来たような美しい声で、兄とかわるがわる歌います——ガスコンの村踊り唄でした。
よろこびは とこしえに!
かなしみは 七里けっぱい!
娘たちが声をそろえてこれに和し、若い衆らも一オクターヴ低く声を合わせます——
私は、あそこさえ綴[と]じつけてもらえるのなら一クラウンくらい出してもよいのにと思いました——ナネットはそんなことにはまったくの無頓着です——「よろこびはとこしえに!」娘の唇が歌いました——「よろこびはとこしえに!」娘の眼も言っていました。つかの間の友情の火花が、虚空を切って二人の間に飛びかいました——ナネットは好意にみちた顔をしています!——なぜこのおれも、このままここに住んでここで生を終えてはいけないのだろう? ああ、われらのよろこびも悲しみも公平に配分される天の神よ、私はさけびました、人間はなぜここに限りない満足のうちに腰をおちつけてはいけないのでしょうか?——踊り、歌い、祈りを上げ、そして天に上る時までもこの胡桃のような褐色の肌をした娘といっしょにということがなぜゆるされないのでしょう? 気まぐれのように娘は首を片方にまげて、そそのかすように踊り寄って来ました——
(下巻 pp.106-8[原著の第7巻第43章])
[「七里けっぱい」(七里結界)とは、何かをひどく嫌って近くに寄せつけないこと。]
床上に臥したる吾父は、
——この点については、奥さま、私はあなたと議論をする気はありません——そうときまっているのですし——私は百パーセント確信しているのです。つまり、「男女のいずれを問わず、苦痛や悲しみにたえるには(その点、私の知るかぎり、快楽の場合も同じだと思いますが)、水平の姿勢が最適だ」ということです。
私の父は階上の自分の室に入るやいなや、これ以上は想像もできないほどの取り乱した姿で、ベッドにパッタリとうつぶせに身を投げ出しました。しかしそれと同時に父の姿は、古来憐憫の眼によって一掬の涙をそそがれた中でもこれ以上は考えられないほどのいたましい、悲しみにうちひしがれたものでもありました。——父が最初にベッドに崩れるように身を横たえた時、父の右手の掌はその額をささえて、両の眼の大部分をおおっていましたが、次第に少しずつ頭とともに下[さが]って行って(肱がだんだん弱って腹のほうに寄って行ったのです)、とうとう鼻が敷蒲団についてしまいました。——左の腕はダラリとベッドの外にたれて、指の関節のあたりが、ベッドの垂れ布の下からのぞいているしびんの柄[え]のところにさわろうとしていました——右の脚も(左脚は胴体のほうに引き寄せてありました)、なかばベッドの外にはみ出して、ベッドのへりがその脛骨を圧迫していましたが——本人はそれを感じませんでした。顔のしわの一つ一つにも、深い動かしようのない悲嘆が刻みこまれており——父は溜息を一度つき——胸を何度か大きくふくらませましたが——言葉は一言も発しません。
(上巻 pp.339-40[原著の第3巻第29章])
最終更新日:2006年5月22日
ページ制作者:内田勝
(c) Masaru Uchida
2003
このページの先頭に戻る
夏目漱石『トリストラム、シヤンデー』本文に戻る
『電脳空間のローレンス・スターン』に戻る