[ロビンソン・クルーソー] [ガリヴァ旅行記] [トリストラム・シャンディ] [フランケンシュタイン] [自負と偏見]
放送大学岐阜学習センター 平成17年度2学期 面接授業 内田勝(岐阜大学地域科学部)
翻訳で読む18世紀イギリス小説 第3部 (2005年12月10日 15:40-17:55)
スターンの『トリストラム・シャンディ』
引用文中の「……」は省略箇所、[ ]内は原文のルビ、【 】内は私の補足です。
==============================================================================
[1]【『トリストラム・シャンディ』は】全編ギャグ、ギャグ、ギャグ。今でもあらかたのギャグ作家なんて大したことないと思わせちゃう。なにしろ上、中、下巻の中あたりにならないと主人公が出てこない(笑)。急にページが真っ黒になったり、変な図が出てきたり、18世紀のイギリスでポストモダンやってるんだもん。しかも書いたのはキリスト教の坊さんでさ。そりゃあモンティ・パイソンも出てくるよね、イギリスには。これが小説の始まりだって言われてたりもするくらいだから、勿体ぶって壊すとかなんとか言わなくても最初から壊れてるんだよ、小説って(笑)
(いとうせいこう「私の好奇心」『朝日新聞』2003年9月26日、http://book.asahi.com/topics/index.php?c_id=94、現在はページが消滅)
[2]スターン Laurence Sterne [1713—68] イギリスの作家、聖職者。11月24日、アイルランドのクロンメルに生まれる。曽祖父[そうそふ]にケンブリッジ大学の学寮長[マスター]やヨークの大主教を歴任した著名人をもつが、父親はのんき者の貧乏陸軍少尉で、母との結婚も、従軍商人であった彼女の継父に対する借金を帳消しにしてもらうためであったという気まぐれな男であった。スターンは、国の内外にわたる父の勤務地、駐屯地を転々として貧しく育ち、父の死後、親戚[しんせき]の援助でケンブリッジ大学に学んだ。1737年卒業し、ヨークの近在で聖職につく。以後死のときまで30年余を聖職者で送った。41年結婚。こののち約20年は、ときに牧師間の生臭い勢力争いに巻き込まれたり、教養のない母親との確執に悩まされたりしつつも、ヨークの社交界の空気を楽しみ、また大学時代の友人ホールの書斎でその蔵書、ラブレー、モンテーニュ、エラスムス、セルバンテス、バートン、スウィフトなどに読みふけったりして、比較的平穏な田舎[いなか]紳士の生活が続いた。ただし健康は、大学卒業のころ最初の喀血[かっけつ]をみてから、つねに持病の肺患に付きまとわれた。
1759年、ふとしたことから文才を自覚して、『トリストラム・シャンディの生涯と意見』の執筆を始めたが、60年1月、その第1、2巻が出版されると、思いがけない大好評で、一躍ロンドン社交界の寵児[ちょうじ]となり、各方面から引っ張りだこのありさまであった。この作は以後すこしずつ書き継がれて、結局スターンの死で未完に終わった。ほかに68年出版のいっぷう変わった紀行文『センチメンタル・ジャーニー』、60年から死後にかけて出版の『説教集』七巻などの著作がある。……。68年3月18日ロンドンで没。(朱牟田夏雄「スターン」『日本大百科全書』[小学館、有料サイト『ジャパンナレッジ』(http://www.japanknowledge.com/)より])
[3]これが英文学の中でも、いや、世界文学全体に範囲をひろげてみても、屈指の型やぶりの作であることは天下に名高い。パラパラとめくってみただけでも、真っ黒に塗りつぶしたページがある、逆に真っ白な空白のページもある、極彩色のマーブル・ペーパー【墨流し模様のページ】というページもある……。妙な不規則な曲線が四、五本ならべて描いてあるから何だろうと思うと……、第一巻から第五巻までの進行の具合を図にしたものだと説明がついている。この訳書では割愛したが、片面ラテン語、片面英語が印刷してあって、左右対訳になっている部分もある。名目上主人公であるべきトリストラムの、誕生ではなくて受胎のところから書き出されるが、話がはじまると脱線また脱線の連続で、何が話の本筋なのか、生まじめな読者ははぐらかされてばかりいる思いがするかもしれない。それでも辛抱して読んでゆくと、第三巻の終り近くになってやっと主人公が誕生するけれども、第六巻あたりでもまだ子供であって、『紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見』という標題でありながら、「意見」のほうはともかく、その「生涯」に至ってはいつになったらそれらしくなって来るのやら見当もつかない。第三巻の第二十章あたりになって、作者もやっと小閑を得たからと、突如として「作者自序」というのが飛び出して来たりもする。まず形式だけからいっても思いつくかぎりの奇抜さをとり入れて、読者を唖然とさせることを目標としているかの如くである。(朱牟田夏雄「訳者まえがき」スターン『トリストラム・シャンディ』上巻 pp.11-12)
[4]脱線の連鎖の中で、語り手トリストラム自身やその家族の趣味や嗜好が次第に明らかになっていく。トリストラムの父ウォルター・シャンディ(Walter Shandy)は饒舌な理論家で、「一族が繁栄するためには、家長の鼻が大きくなければならない」といった奇妙な仮説を次々に立ててはその研究に没頭する人間である。叔父のトウビー・シャンディ(Toby Shandy)は温厚な性格をした退役軍人だが、屋敷のボーリング用芝生に巨大なミニチュア戦場を作り、部下のトリム伍長(Corporal Trim)とともに日々大真面目で戦争ごっこに興じている。
そうしたエピソードが断片的に少しずつ、時間的に前後しながら、かつ途中で他のエピソードへと脱線しながら語られていく。内容が気まぐれな順序で語られる断片的エピソードの集積という実験的なものであることに加え、書物としての体裁の面でも、なぜか第3巻の途中に突如出現する序文、「ゴチャゴチャしたこの作品の象徴」として挿入される極彩色墨流し模様のページ、意図的に一章分欠落しているページ番号、何も書かれていない空白だけの章、脱線だらけの語りの進行状況を説明するために挿入されたジグザグの曲線など、通常の印刷本の形態からできる限り逸脱しようとする実験的な試みがなされている。この小説は全9巻を通じてさんざんふざけ回ったあげく、叔父トウビーの恋愛をめぐるドタバタ騒ぎの最中に、登場人物の一人の口を借りて自らを「最高にできのいいでたらめ話」と定義すると、突然終わってしまうのだ。(内田「『トリストラム・シャンディ』はハイパーテキスト小説か」p.204)
[5]父ウォルター・シャンディの道楽馬【スターンの造語で、「オタク的な興味の対象」の意味】は学問というか知識、そして本の世界である。何かが起るたびに古代ギリシア・ローマの典籍に当り、そうしたものの引用でこの人物の「意見」は埋ってしまう。生き字引とか歩く百科事典とかいう言葉は彼のためのものだ。(高山「もう結構な話」p.113)
[6]考えてみると我々人間は別に精神とか知性とかいったものだけでできているわけではない。それを肉体という名の不透明でわけのわからぬ媒質がとり巻いているのだ、というのがこの小説の一番いいたいことである。本の中の世界では万能のウォルター・シャンディが扉のちょうつがいひとつどうにもできないで苦しむ逸話は、いろいろ偉そうなことをいっても胃薬がないと生きていけない『吾輩は猫である』の苦沙弥先生そっくりだ。十八世紀英国文学研究者でもある夏目漱石が小説を書こうとした時、彼に……インスピレーションを与えたのがスターンのこの小説だったというのも、実によくわかる。(同、p.114)
[7]物語が首尾一貫、むだなく一本の線にそって語られていくやり方を人間の精神の側が喜ぶなら、人間の肉体の側に即した語り方は首尾一貫性を欠いた混沌をこそ工夫した語り方でなければならない。そうなると多分一番直線的にきちんと——つまり年表的に——語られるべき伝記ないし自伝というジャンルをわざわざ選んで、自伝を支えるべき直線的秩序をスターンは徹底的にこわしてみたかったということになる。(同、p.117)
[8]だめな人間がいろいろ経験して賢くなったことの報告を自伝というものに期待する読者は、てき面に裏切られるだろう。時間は線にそって流れず、物語の流れは次々に繰りだされる脱線また脱線でぶつぶつに切りきざまれる。「何を話していましたっけ」と語り手その人が呆然とすることしばしば。そして最後には作家自身が今までの話は全部「コック・アンド・ブル・ストーリー」【でたらめ話】でしたといって「落とす」。……物語に線にそった「成長」だの「意味」だのを求めるタイプの読者は「モウ・ケッコー」と音[ね]をあげるかもしれない。(同、p.117)
[9]では何の「意味」もないかといえばとんでもない。すべてに知的な意味での「意味」を求める性急な感覚の人に、もう少し人間の広い、そしてルースな肉体に即しながらゆっくり世間や言葉をみつめましょうや、といっているのである。答だ、結論だということに意味を求める型の頭人間が文化の中心を占めだした十八世紀中葉期に、それを病として斥[しりぞ]けようとした悠々たる作品だ。……究極的には人が余りにも頭だけで意味を追求することのもたらす病を癒す本だ。(同、p.118)
==============================================================================
[10]私めの切な願いは、今さらかなわぬことながら、私の父か母かどちらかが、と申すよりもこの場合は両方とも等しくそういう義務があったはずですから、なろうことなら父と母の双方が、この私というものをしこむときに、もっと自分たちのしていることに気を配ってくれたらなあ、ということなのです。(スターン『トリストラム・シャンディ』上巻 p.34)
[11]「ねえ、あなた」私の母が申したのです。「あなた時計をまくのをお忘れになったのじゃなくて?」——「いやはや、呆れたもんだ!」父はさけびました。さけび声はあげながらも、同時にその声をあまり大きくしないように気をつけてはいました——「天地創造の時このかた、かりにもこんな馬鹿な質問で男の腰を折った女があったろうか?」え? 何だって? 君のおやじさんは何て言ったんだって?——いえ、それだけです、ほかには別に何とも。(同書、上巻 p.35)
【最後のほうで「え? 何だって?」と口をはさんでくるのは、なんとこの本の読者なのだ。作者と読者が語り合う!】
[12]父がその生涯の多年にわたって掟としていたのは、——どの月もどの月もきまって第一日曜の夜に……裏の階段のてっぺんにおいてあった大時計のねじを、自らの手でまくということでした。……父はこの時計のことのみでなく、ほかにも母親だけを相手のこまごました用事なども、だんだん同じ時期にかためるようにしていました。それというのも……すべてを一ぺんに片づけてしまって、あと一カ月の間はそういうことに煩わされずにサッパリとしていようがためだったわけです。(同書、上巻 p.41)
[13]本来お互いに何の脈絡もない観念同士の不運な連合の結果として、ついには私の母親は、上述の時計のまかれる音をきくと、不可避的にもう一つのことがヒョイと頭に浮かんで来ずにはいない、——その逆もまた同じ、ということになってしまったのです。——あの賢いロック【ジョン・ロック】は、明らかにこのようなことの本質を大概の人よりもよく理解していた人で、かかる不思議な観念の結合が、偏見を生み出すもとになる他のどのような源にもまさって、多くのねじれた行為を生み出していることを確言しております。(同書、上巻 p.42)
[14]この世の中には書物などすこしも読まない善男善女も大勢いらっしゃると同時に、読書ずきのお方もたくさんおいでになる——そしてそういう中には、人の身の上に関することなら、はじめから終りまで細大もらさず、どんな秘密でも打ち明けてもらわないとどうにも落ちつかない、という人物があるものです。
私が、ここまですべてをきわめて事こまかに記してまいったのも、そのような方々の気持ちに快く応じようため、また、どなたにもせよ人さまを失望させまいとする私の性分からのことにほかなりません。(スターン『トリストラム・シャンディ』上巻 p.39)
[15]とはいえ、そう根源にさかのぼってこのようなことを知りたくはないといわれるお方々には、私のさし上げうる最上の忠告は、どうぞこの章のこれから先の部分はお読みとばし下さるようにということです。あらかじめ宣言しておきますが、これから先は好奇心の強いお方、せんさく好きのお方のためのみに書くのですから。
——————————————扉をしめて下さい—————————————— (同書、上巻 p.40)
[16]だんだん私といっしょに進んで下されば、今二人の間に芽ばえかけているかすかな相識【そうしき、知り合っていること】の関係は、進んで親近感となり、そのまた親近感は、あなたか私がどちらかが失策でも犯さぬかぎりは、最後は友情にもなることでしょう。——ああ、そのすばらしき日!——そうなればこの私の身にすこしでもかかわりのあることは、もとより些細とは思われず、聞いて退屈とも思えぬでしょう。(同書、上巻 p.45)
[17]——どうしてまあ奥さま、あなたはすぐ前の章をそんなにうわの空で読んでいらしたのです? 私の母はカトリック教徒ではなかったと、申上げたではありませんか。——カトリック教徒ですって! そんなことはおっしゃらなかったわ!——失礼ですが奥様、もう一度はっきり申上げます。私はそのことを、すくなくともそこの言葉から直接推定できる程度にははっきりと、申上げておいたはずです。——それじゃ私、一ページほど抜かして読んだのか知ら?——いいえ奥さま、一語だって抜かしてなんかいらっしゃいません。——じゃ眠っていたんだわ、きっと。——そんな逃げ口上は奥さま、私の自尊心がゆるせません。
——それじゃ、そんなことは、一言だって記憶がなくってよ、本当のところ。——だからそれを、奥さま、奥さまの責任だと申すのです。そこでその罰として、今すぐ、ということはこの次の文章の切れ目のところに辿り着き次第、もう一度前の章にもどって、十九章全体を読み返していただきます。(同書、上巻 pp.110-111)
[18]—— 一体何をしてるんだな、二階では?——父が言いました——お互いの話さえ聞きとれやしない。
さよう——叔父トウビーはパイプを口から離して、その火皿のところを二、三度、左の親指の爪に打ちつけながら口を切りはじめました——さよう——けれどもこの時の叔父トウビーの気持に正しく入りこんでいただくためには、まず叔父の人柄にすこしばかり立ち入っていただかねばなりません。そこでまずそのほうのほんの輪郭を手短かにお話し申して、そのあとで叔父と父の対話のつづきを申上げてもよろしかろうと考えます。(同書、上巻 p.118)
【ここから長い長い脱線が始まる。文庫本で50ページ強に及ぶ脱線の後、やっと元の場面に戻って次の台詞がこれ】
[19]——さよう、叔父は答えました、——ベルを鳴らして聞いてみてもいいですな。(同書、上巻 p.170)
【召使いを呼ぶためにベルを鳴らしてまたまた脱線が続く。二階で何をしているのかはいつ分かることやら。】
[20]現在私がはからずも迷いこんでしまったこの長い脱線ですが、ここには私のすべての脱線の場合と同じく……、脱線術としての入神の妙技が秘められているのです。がそういう秘術を残念ながら読者諸賢は終始見おとしておいでらしい——それは何も諸賢に洞察の力がないからというのではなく——ただ、このような神技が脱線というものに普通予想も期待もされないからにほかなりません。——それというのはこういうことです。たしかに私の脱線ぶりは、諸賢も御覧の通り公明正大なものであり、自分の従事している仕事をそっちのけに、大英帝国のいかなる文士にも負けぬほどに、遠いかなたまで、またそれも機会あるごとに、逸脱してしまっているにはちがいありませんが、それでいて私は、私の留守中といえども私の本来の仕事が歩みをとめてしまわないような布石だけは、一瞬も忘れていないのです。
たとえば私はつい先刻も、わが叔父トウビーのこの上なく気まぐれな性質について、その大きな輪郭をお伝えする仕事にかかっていました——そこに突如として私の大伯母ダイナーと例の馭者が飛びこんで来て、われわれを何百万マイルのかなた、わが太陽系のまっただ中までも拉[らっ]し去ってしまいました。にもかかわらず叔父トウビーの性格の描写は、その間も絶えず静かにつづけられていたことは諸賢もお認めでしょう——なるほど大きな輪郭のほうではない——それはとうてい不可能でした——しかしあちらでちょっと砕けた一筆、こちらでかすかにほのめかす暗示という類が、脱線話の途中でも随所に叔父の性格に添加されて、その結果は皆さんは私の叔父トウビーについて、前よりもはるかに知見を肥やしていらっしゃるわけです。(同書、上巻 pp.129-130)
[21]このような工夫によって、この私の著作の仕組みはまことに無類独特のものになっております。二つの相反する動き、お互いに両立はできないと考えられた動きが、この著作に持ちこまれて、しかも融和している—— 一言でいうならば私の著作は、脱線的にしてしかも前進的——それも同時にこの二つの性質を兼ね備えているのです。(同書、上巻 p.130)
[22]脱線は、争う余地もなく、日光です。——読書の生命、真髄は、脱線です。——たとえばこの私の書物から脱線をとり去って御覧なさい——それくらいならいっそ、ついでに書物ごとどこかに持ち去られるほうがよろしい——あとに残るのは各ページ各ページを支配する一つづきの冷たい永遠の冬です。今度は脱線をふたたび作者に返して御覧なさい——作者は新郎[にいむこ]にたとえられた太陽のごとくに進み出て——すべての者に祝福をおくり、多彩の変化を現出させ、何人[なんびと]の食欲をも飽かしめることがないでしょう。(同書、上巻 p.131)
[23]文章とは、適切にこれをあやつれば(私の文章がその好例と私が思っていることはいうまでもありません)、会話の別名に過ぎません。作法を心得た者が品のある人たちと同席した場合なら、何もかも一人でしゃべろうとする者はないように、——儀礼と教養の正しい限界を理解する作者なら、ひとりで何もかも考えるような差出がましいことは致しません。読者の悟性に呈しうる最も真実な敬意とは、考えるべき問題を仲よく折半して、作者のみならず読者のほうにも、想像を働かす余地を残しておくということなのです。……。ところで、今は読者の持ち場です。——私はスロップ医師のいたましい落馬と、また同医師の裏の居間へのいたましい出現とを、詳細にお話ししました。——今度は読者の想像力に、しばらくその先を考えていただかないと困ります。(同書、上巻 pp.182-183)
[24]こうして、語り手としてのトリストラムは読者に対して敬意を払い、読者が読んでいる小説を構成するのを手伝わせている。語り手がわき道にそれて読者を話の本筋から引き離すと、その分だけ我々は語り手に対する親密感を感じて単に読んでいるのではなくて対話しているように感じるのである。
(ボルター『ライティング スペース』p.231)
[25]私は十二カ月前の今ごろ、つまりこの著作にとりかかった時にくらべまして、ちょうどまる一カ年、年をとっております。そして、今、御覧の通り第四巻のほぼまん中近くまでさしかかっているわけですが——内容から申せば、まだ誕生第一日目を越えておりません——ということはとりも直さず、最初に私がこの仕事にとりかかった時に比べて、今日の時点において、これから書かねばならぬ伝記が三百六十四日分ふえているということです。従って私の場合は、今までせっせと骨を折って書き進めて来たことによって、普通の著作家のようにそれだけ仕事が進行したというのではなく——逆に、四巻書けばちょうどその四巻分だけうしろに押しもどされたことになるのです——それは私の生涯の毎日毎日がもしもこの日のように忙しい日ばかりというのならですが——そうでないという保証はどこにもありますまい——また、それをいちいち記録して意見まで述べてゆくのには、何しろ今の調子ですと私のペンの速さの三百六十四倍の速度で私は生活してゆくわけですから、まさにそれに匹敵するだけの記述は必要になる理窟ですし——それを短く切り詰めてよいという理由はどこにもないでしょう?——そこで必然的に結論できることは、諸賢のおゆるしをいただいて申してしまえば、私が書き進めば書き進むほど、書かねばならぬことはそれだけふえてゆくということ——また当然諸賢のほうは、読み進めば読み進むほど、読まねばならぬことがそれだけふえてゆくということになります。(スターン『トリストラム・シャンディ』中巻 p.68)
[26]さてこのあたりからいよいよ話の本筋にはいってゆくわけですが、……これからは私の叔父トウビーの物語を、ついでに私自身の物語も、かなり直線に近い形で進められることを私は信じて疑いません。ふりかえって見ますと、
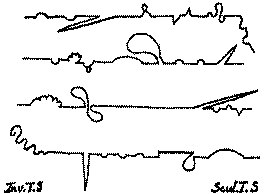
これがこの本の第一巻、第二巻、第三巻、第四巻でそれぞれ私が動いてきた線でした。——第五巻はたいへんうまく行って、——あそこで私がたどった線は、まさに次のようなものでした。
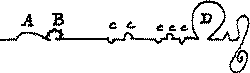
……。この調子で私が進歩してゆくならば……今後はつぎのような模範的な進み方に到達することさえ、決して不可能ではありません。
これは私があるお習字の先生のものさしを借りて(わざわざこのために借りたのですが)、右にも左にもそれないように、できるかぎりまっすぐに引いてみた線です。(同書、中巻 pp.348-351)
[27]本を読んで下さいよ、本を、本を、本を! どうぞ無学の読者諸公、もっと本を読んで下さい——いやそれよりも……はじめからはっきり言っちゃいましょう、今すぐそんな本などはお捨てになるほうがよろしい——と申すのは、つけ焼刃の読書くらいでは、というのは申すまでもなくつけ焼刃の知識ではという意味ですが、この次に出て来る墨流し模様のページの教える教訓など、とてもあなたにわかるものじゃありませんからね(このページこそ、私のこの著作のゴチャゴチャした象徴なんですがね!)
(同書、上巻 p.356)
【ここで二ページ(紙一枚分)にわたって極彩色の墨流し模様が挿入されている。初版ではこの部分は一枚一枚手作業で染められたので、一つとして同じ模様をもった本はない。墨流し模様とは、桶の水面ではっきりとした形を持たずグニョグニョとうごめく絵具の動きをとらえたものだが、この本ではそれが整然と綴られた本のページにきちんとはめこまれていて、他のページと同じように四隅に余白が取られ、わざわざページ番号まで判で押してある。】
[28]そういうわけで、恋が何であるかはさておくといたしまして——私の叔父トウビーはその恋に落ちたのでした。
——いえ、事によると、やさしい読者がたよ、あれだけの誘惑に接するとなったら、——あなた方にしても同じことになられるかも知れません。あなた方の目が、あるいはあなた方の貪欲な色欲が、この世であのウォドマンの後家以上に色欲をそそり立てる対象にぶつかったことは決してないのですから。……。このことを正しく認識していただくために——どうぞペンとインクをとりよせて下さい——紙はお手もとに用意してあります。——そこでどうぞお席におつきになって、この女性の姿をお心のままにここに描いてみて下さい——できるだけあなたの恋人に似せてでも——奥さんにはあなたの良心がゆるすかぎり似せないようにでも——それはどっちだって私はかまいませんが——ただあなたの空想だけは満足させて上げて下さい。
——やっ! 自然界にかくも甘美なものがあろうか! かくも美しいものが!
——それならば、皆さん、どうして私の叔父トウビーにそれに抵抗する力があったでしょう?
(同書、中巻 pp.344-346)
【なんとトリストラムは、読者が自由に絵を描くためのスペースまで、本の中に用意している!】
[29]本というのは、しょせん、どんな本もすきまだらけなのだ。誤読や偏見もひっくるめて、そのすきまで読者が思いっきり自由にふるまうのが読書。(津野『新・本とつきあう法』p.41)
==============================================================================
[30]典型的なハイパーテキスト小説【コンピュータの画面上で読むために書かれた、短い文章をリンクでつないでネットワーク状にした小説。読者は自らリンクをたどって自由な順序で読む】とは異なり、断片的なエピソードを読む順番は読者に委ねられていない。そもそも『トリストラム・シャンディ』の読者には、【コルタサルの】『石蹴り遊び』の読者やゲームブックの読者のように、本のページを前後に繰りながら断片的なエピソードを読み継ぐことが許されていない。この作品はあくまで1ページ目から順番に読まれなければならないのだ。(内田「『トリストラム・シャンディ』はハイパーテキスト小説か」p.209)
[31]作者による脱線は、読者が作者の指定した順序通りに読んでくれるからこそ可能なのだ。トリストラムがさまざまなエピソードを語る順序にどれほどこだわっているかを示す場面を引用してみよう。トリストラムの誕生に立ち会った産科医は誤って赤ん坊の鼻を潰してしまい、あわてて綿と鯨骨で鼻柱(bridge)を作って潰れた鼻を高くしようとするのだが、その事件の報告を聞いたトウビーが、"bridge"という単語を自分のミニチュア戦場に取り付けるための跳ね橋のことと誤解する、という場面である。(同、p.210)
[32]このわが叔父トウビーの失策の蓋然性を正しく知っていただくためには、私としてははなはだ不本意ながら、トリムの演じたある失策に多少ともふれないわけにはまいらぬのです。はなはだ不本意と私が申しますわけは、ほかでもありません、その話をここに持ちこむのはある意味では明らかに場ちがいだからです。この話が当然出て来るべき場所は、そこではトリム伍長も重要な一役を勤めた叔父トウビーとウォドマンの後家との情事に関する挿話の中か——そうでなければ、ボーリング用の芝生でのトリムと叔父トウビーの攻防戦のところか——この二つならどちらにもまことにピッタリなのですが——しかしまたこの件を、私の物語に右の二つのどちらかが登場してくるまでとっておくとしますと、——今お話しかけの話のほうがだめになってしまう——そうかといってここで申上げてしまえば——話の先まわりをすることになって 、先のほうがだめになってしまう。
——読者の皆さんはこの場合、私にどうせよというご意見でしょうか?
〈それはシャンディ君、ぜひその失策というのを聞かせたまえ〉——〈トリストラム、ここでそれを話しちまうなんて、君は阿呆だよ〉
(スターン『トリストラム・シャンディ』上巻 pp.325-326)
[33]トリストラムは読者の意見を尋ねてはいるが、もちろん決定を下すのは彼自身である。結局トリムと跳ね橋のエピソードは、トウビー叔父の恋物語や戦争ごっこのエピソードとは切り離して、この引用箇所の直後に語られることになる。
この引用箇所が興味深いのは、ここに描かれているのが、複数のリンクから一つを選択するという作業にほかならない点である。ハイパーテキスト小説の読者が行うべき作業を、ここでは語り手が(つまりはその背後にいる作者が)行っているのだ。(内田「『トリストラム・シャンディ』はハイパーテキスト小説か」p.210)
[34]作品全体を通じて、トリストラムはハイパーテキストの読者のように振る舞っている。それはまるで彼が手元に『原トリストラム・シャンディ』とも呼ぶべきハイパーテキストを持っていて、気の向くままにリンクをたどりながら断片から断片へと渡り歩いているような感じだ。われわれ読者は、トリストラムにハイパーテキスト的読書のデモンストレーションを見せられているような印象を受ける。(内田「『トリストラム・シャンディ』はハイパーテキスト小説か」p.210)
[35]『トリストラム・シャンディ』をハイパーテキスト小説と呼ぶことはできないが、その小説内世界は多分にハイパーテキスト的なものである。語り手トリストラムは自分の頭の中にあるハイパーテキスト状の記憶をたどって、その結果をそのまま読者に読まれるべきテキストとして提出する。……。……この作品を統括する作者の特権的な地位には揺るぎがない。読者は作者の定めた通りに頭から順番にページを繰ることで、トリストラムが行うスリリングな〈読み=書き〉体験を追体験するのみである。(同、p.211)
[36]【ウォドマンの後家の屋敷に愛の告白をしに行ったはずの叔父トウビーとトリム伍長がなかなか家に入っていかない。遠くでそれを見ていた父は、「一体あいつらは何をやってるんだ?」と母に尋ねる。】
私の察しますところでは、母が言い出しました——だが待って下さい、読者の方々——母が今の場合何を察したか——また父がその時何を言ったかは——それにまた母が答えたこと、父がさらにやり返したことなどともども、いずれ別の章でとり上げることにしますから、後世の方々はそこで味読するとも熟読するとも、あるいはご銘々の解釈なり批評なり敷衍[ふえん]なりを加えるとも——一言で簡単に言ってしまえば手垢でよごれるまでいじくりまわしていただいて結構です——私は今、後世の方々と申しました——それはもう一度くり返しても一向かまいません——私のこの書物をたとえば『モーゼは神の使者』【当時の有名な主教の著書】や『桶物語』【『ガリヴァー旅行記』で有名なスウィフトの諷刺作品】にくらべて見て、これがあの二書とともに「時」の溝の中をフラフラ流れて行くわけにゆかないようなことを何かしでかしているでしょうか?(スターン『トリストラム・シャンディ』下巻 p.230)
【こうして『トリストラム・シャンディ』について書かれる後世のすべての文章は、ことごとく『トリストラム・シャンディ』の一部になっていく。】
[37]【おそらく全編でただ一箇所、語り手トリストラムあるいは作者スターンが、マジになって創作の苦労を訴えている場面】
私の生涯のどんな意見にせよどんな一時にもせよ……それまで書いていた章をねじまげてその次に来る章に平仄【ひょうそく、辻褄】を合わせるのに、今のこの場合くらい私の頭が途方にくれたおぼえは、ただの一度もありはしません。人によっては私がこのようなせっぱつまった立場におちこんだのは、わざと求めてしたことであって、それというのもそこからどうして脱出するかの新しい実験をしてみるのが楽しみなばっかりなのだと、思うお人もあるかも知れません——ああ、何という思慮の足りない人間であろう、おんみは! 本当に何ということ! 文士としてまた一個の人間としてのおんみの、四方八方をとりかこんでいるこれだけの避けがたい悲しみでは——本当に、トリストラムよ、それだけではまだ足りなくて、おんみはまだこの上にも厄介な奴を身のまわりに作り出さなくては気がすまぬと言われるのか?
おんみが借金で首がまわらず、第五巻と六巻が荷車に十台ほどもまだ——まだ売れ残っていて、どうしたらそれがさばけるか、ほとほとおんみの智恵も出つくしてしまった、というだけではまだ不足だというのか。(同書、下巻 p.122)
【最後のところ、「読まれない本の悲しみ」に注目。】
[38]【読者のあなたと語り手の私で】二人してソロリソロリとまいる間に、私とともに笑おうとも、あるいは私めを笑いのたねになさろうとも、要するに何をなされようとも一向にかまわぬが——ただ短気だけは起こさずにいていただきたいのです。(同書、上巻 p.45)
【読者が怒るか飽きるかして本を投げ出してしまったのでは、さすがのトリストラムも存在できなくなってしまう。】
==============================================================================
【引用した文献】
● ロレンス・スターン作、朱牟田夏雄[しゅむた・なつお]訳『トリストラム・シャンディ』全3巻(岩波文庫、初版1969年)[原著1760-67年]
[この岩波文庫版は現在絶版だが、朱牟田訳『トリストラム・シャンディ』は、たいていの公共図書館の文学全集の棚に置かれている『筑摩世界文学大系21(古い版では76)・リチャードソン/スターン』でも読むことができる。]
● 内田勝「『トリストラム・シャンディ』はハイパーテキスト小説か」『岐阜大学地域科学部研究報告』第1号(1997年)201-16ページ
● 高山宏「もう結構な話」大岡信他編『世界文学のすすめ』111-8ページ(岩波文庫、1997年)
● 津野海太郎『新・本とつきあう法——活字本から電子本まで』(中公新書、1998年)
● ジェイ・デイヴィッド・ボルター著、黒崎政男・下野正俊・伊古田理訳『ライティング スペース——電子テキスト時代のエクリチュール』(産業図書、1994年)[原著1991年]
【その他の参考資料】
● Sterne, Laurence. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Ed. Melvyn New and Joan New. London: Penguin Books, 2003.[ペンギン版『トリストラム・シャンディ』。原書で読むならこれ。ISBNは0-14-143977-7。]
● Tristram Shandy Online (https://www1.gifu-u.ac.jp/~masaru/TS/)[『トリストラム・シャンディ』英語原文の電子テキスト。]
● Nelson, Theodor H. "Dream Machines," Computer Lib / Dream Machines. Redmond, WA: Tempus Books of Microsoft Press, 1974, Revised Edition 1987.
● Rowson, Martin. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Penguin USA, 1997.[漫画版『トリストラム・シャンディ』。原作の忠実な漫画化というよりは、現代の文学研究者たちを痛烈に皮肉った諷刺漫画の傑作。]
● 朱牟田夏雄訳『トリストラム・シャンディ』の紹介(https://www1.gifu-u.ac.jp/~masaru/quotations.html)
● 高山宏『表象の芸術工学』(工作舎、2002年)[『トリストラム・シャンディ』の文化史的背景を知りたい方にはおすすめ。同じ著者の『奇想天外・英文学講義』(講談社選書メチエ、2000年)も面白い。]
● 夏目漱石『トリストラム、シヤンデー』(https://www1.gifu-u.ac.jp/~masaru/soseki/)[『トリストラム・シャンディ』を初めて本格的に日本に紹介した夏目漱石の評論(1897)に注釈を付けたもの。]
● 『復刊ドットコム』[絶版書の復刊を求めるサイト]に置かれた、岩波文庫版『トリストラム・シャンディ』のページ
(http://www.fukkan.com/vote.php3?no=9154)
==============================================================================
【なおこの小説は、今年(2005年)イギリスのマイケル・ウィンターボトム監督によって Tristram Shandy: A Cock and Bull Story というタイトルで映画化され、来年(以降?)には全世界で順次公開されるはずである。これは奇書『トリストラム・シャンディ』を映画化しようと悪戦苦闘する監督や俳優たちの大騒動を描いたコメディーだという。】
(c) Masaru Uchida
2005
ファイル公開日: 2005-12-14
ファイル更新日: 2009-4-22(他講義へのリンク追加)
[ロビンソン・クルーソー] [ガリヴァ旅行記] [トリストラム・シャンディ] [フランケンシュタイン] [自負と偏見]
講義資料「映画で読むイギリス小説」へ /講義資料「文化を研究するとは、たとえばどういうことか」へ / その他の授業資料へ