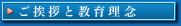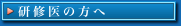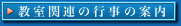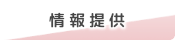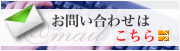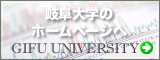岐阜大学医学部附属病院|精神科
Neuropsychopharmacology Reports (NPPR)はJSNP機関誌・日本神経精神薬理学雑誌をリニューアルした英文オープンアクセス誌になります。大井一高 准教授はNPPRに投稿された論文の査読者としての貢献が評価されNPPR Reviewer Awards 2025を受賞されました。
https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=222
日本精神神経学会の英文機関誌であるPsychiatry and Clinical Neurosciences (PCN)は、1933年創刊の歴史ある精神医学専門誌になります。PCNの世界的な評価は年々高まり、PCNの世界的な評価は年々高まり、2024年のImpact Factorは6.2と、5年連続Q1(トップ4分の1)を維持したことに加え、Psychiatry 288誌中21位と、精神科領域でトップ10%の雑誌になっています。
大井一高 准教授はPCNに投稿された論文の査読者としての貢献が評価されPCN Reviewer Awards 2024を4年連続受賞されました。
『JMA Journal』は、日本医師会(Japan Medical Association)が日本医学会と協力して発行する、オープンアクセスの英文総合医学雑誌です。
本論文は、大井准教授が2024年度の日本医師会医学研究奨励賞を受賞した研究内容をもとに取りまとめられた総説になります。精神疾患の研究において「エピジェネティクス(環境や生活習慣などが遺伝子に与える影響)」が注目されており、その中でも新しい解析方法である「メチル化リスクスコア(MRS)」を紹介し、今後の精神医療・研究への可能性について解説しています。
当教室では、このような研究を通じて、精神疾患の理解やより良い治療の発展に寄与できることを目指しています。
https://jams.med.or.jp/e-news/jams_enews_no010.pdf
2024年11月1日に開催された日本医師会設立77周年記念式典並びに医学大会において、大井一高 准教授が2024年度の日本医師会医学研究奨励賞を受賞しました。
日本医師会医学研究奨励賞は、昭和37年に創設された歴史ある賞です。当科では、昭和44年に難波益之前教授が同賞を受賞されています。岐阜大学全体としての受賞は、他科を含めても昭和58年、平成22年以来の受賞となります(https://www.med.or.jp/etc/igakusyo/ichiran.pdf)。
食習慣は、統合失調症(SCZ)および双極症(BD)の予防および疾患管理に影響を与える可能性があり、遺伝的および環境的要因がこれらの習慣と疾患の両方に影響を及ぼすことが考えられます。本研究では、生活習慣病を持つ高齢者における現在の食習慣に対するSCZおよびBDの遺伝的素因の影響を検討しました。何らかの生活習慣病と診断された、もしくはその疑いのある高齢患者730名を対象に、味噌汁、緑茶、緑黄色野菜、淡色野菜、果物、漬物、肉、大豆の8つの食事カテゴリーについて現在の摂取頻度を評価しました。さらに、同時に採取した血液から、SCZおよびBDのリスクに対するポリジェニックリスクスコア(PRS)、BDのタイプIおよびII、SCZとBDの共有リスク、SCZとBDの判別に関するPRSを、大規模なゲノムワイド関連研究(GWAS)のデータを利用して算出しました。
結果、SCZおよびBDのリスクに対するPRSが特定の食習慣に大きく影響を与えることが明らかになり、特に淡色野菜や大豆などの栄養価の高い食品の摂取量の減少していることが確認されました。また、BD IとBD IIのPRSにおける食事への影響には顕著な差異が見られ、BDではより強い影響が認められました。さらに、SCZとBDの共有遺伝的要因は、味噌汁、緑茶、淡色野菜、大豆の摂取量の減少と相関していました。一方、SCZとBDの区別に関するPRSと食事パターンとの間には有意な相関は認められませんでした。
本研究結果は、個人が保有しているSCZおよびBDに対する遺伝的リスクが高齢者の食習慣に影響を及ぼす可能性を示唆しており、食習慣の見直しが、SCZおよびBDの発症予防や、これらの疾患を持つ、またはリスクを有する個人の治療に有効かもしれないことを示しています。
統合失調症の患者さんでは、記憶をはじめとする認知機能の障害がよくみられますが、その改善は容易ではありません。統合失調症薬物治療ガイドラインでは、抗精神病薬の単剤治療が推奨されていますが、実臨床においてガイドラインに沿った処方がどの程度実践されているか、またそれが患者さんの記憶機能にどのように関係しているかについては、これまで十分に検討されていませんでした。我々は、各患者さんの処方内容と統合失調症薬物治療ガイドラインとの一致度を0~100%で数値化する「Individual Fitness Score(IFS)」という指標を用いて、精神科医のガイドライン遵守度と記憶機能との関係を検討しました。記憶機能は、ウエクスラー記憶検査(WMS-R)を用いて評価しました。
その結果、ガイドラインとの一致率(IFS)が高いほど、言語記憶、注意力、遅延再生(思い出す力)といった記憶機能が良好であることが明らかになりました。特に、治療抵抗性ではない統合失調症患者さんにおいて、その傾向がより強くみられました。
<今回の結果を踏まえ、精神科医師のみなさまに以下の実践を提案します>
統合失調症の薬物治療においては、従来の心理社会的支援に加えて、ガイドラインに基づいた適切な薬物治療を実践することが、記憶をはじめとする認知機能の維持・改善に寄与する可能性があります(https://byoutai.ncnp.go.jp/eguide/ifs-top.html)。
2025年3月24日、医学部医学科6年生(現・研修医)の鳥居叶愛さんが医学部長賞を受賞しました。鳥居さんは、大井一高准教授の指導のもと、在学中に以下の2本の学術論文をまとめ上げ、その研究業績が高く評価されました。
筆頭著者論文:“Tissue-specific gene expression of genome-wide significant loci associated with major depressive disorder subtypes”
(Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry誌)
共著者論文:“Differences in subcortical brain volumes among patients with schizophrenia and bipolar disorder and healthy controls”
(Journal of Psychiatry & Neuroscience誌)
なお、精神医学教室からの受賞は、2024年に受賞した福田仙一君および坂井田有哉君に続く栄誉となります。
精神医学教室では、学生による自主的な研究活動を積極的に支援しており、参加希望者を随時募集しています。
統合失調症(SCZ)、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)は、国際的な診断基準により別々の疾患として区別されていますが、臨床症状や遺伝的要因に部分的な重複を認めており、SCZが臨床的にも遺伝的にも異種性であることを示唆しています。本研究では、ASDとADHDを区別する大規模ゲノムワイド関連研究(GWAS)に基づくPolygenic risk score (PRS)が、SCZ患者の認知機能や皮質構造と関連するかどうかを検討しました。
168名のSCZ患者(45.1±13.6歳,男性76名,女性92名)を対象とし、公開されているGWASデータセット[ASDvs.ADHD]をDiscoveryサンプルとして、PRS解析を行いました。認知機能評価は、WAIS-Ⅲ(Wechsler Adult Intelligence Scale, third edition)を実施し、言語理解(VC)、知覚統合(PO)、作業記憶(WM)、処理速度(PS)の4項目を測定しました(n=145)。脳形態評価は、頭部MRIを用いて全脳の3次元撮像を行い、脳画像データはFreeSurfer v6.0を用いて、34の脳領域における皮質表面積および皮質厚を抽出しました(n=126)。
PRSが低い(ASDリスクが高いことを示す)ことは、特に左内側眼窩前頭領域の皮質表面積と有意な負の相関を示し、PRSが高い(ADHDリスクが高いことを示す)ことは、WMの障害と有意に関連していました。一方、左内側眼窩前頭領域の皮質表面積とWMは、有意な相関関係にはありませんでした。
本研究結果は、ASDとADHDを区別するPRSが、左内側眼窩前頭領域の皮質表面積の減少を介して社会的機能障害に寄与している可能性を示唆しています。SCZは、SCZ以外の他の神経発達症や精神疾患に関連する遺伝的要因に由来する可能性があります。
最新情報
2025年10月10日
「論文発表」「受賞」を掲載しました。
2025年6月13日
「論文発表」「受賞」を掲載しました。
2025年1月16日
「社交不安症専門外来」のQ&Aを更新しました。
2025年1月16日
「受賞」を掲載しました。
2024年10月8日
「社交不安症専門外来」のQ&Aを更新しました。
2024年10月8日
「論文発表」を掲載しました。
2024年10月8日
「スタッフ紹介」を更新しました。
2024年8月29日
「論文発表」「受賞」を掲載しました。
2024年8月29日
「社交不安症専門外来」を掲載しました。
2024年8月9日
2024年8月9日
情報提供に「社交不安症専門外来のお知らせ」を掲載しました。
2024年5月24日
「医局説明会のお知らせ」を掲載しました
2024年5月20日
情報提供に「「妊産婦の精神状態が母子に及ぼす影響の研究」への
協力のお願い」を掲載しました。
2024年5月20日
「スタッフ紹介」を更新しました。
2024年5月20日
「入局実績」を追加しました
2024年5月7日
「論文発表」を掲載しました。
2023年12月21日
情報提供に「精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの
効果に関する研究」を掲載しました。
2023年12月21日
「論文発表」を掲載しました。
2023年8月3日
「受賞」「論文発表」を掲載しました。
2023年4月19日
「論文発表」を掲載しました。
2023年4月3日
「論文発表」を掲載、「スタッフ紹介」を更新しました。
2023年3月2日
「論文発表」「受賞」を掲載しました。
2022年9月13日
「大井一高准教授らの論文発表」を掲載しました。
2022年9月7日
2022年8月3日
「大井一高准教授の受賞」を掲載しました。
2022年6月17日
「医局説明会のお知らせ」を掲載しました
2022年5月10日
「大井一高准教授らの論文発表、受賞」を掲載しました。
2022年5月10日
「スタッフ紹介」 「入局実績」 「教室の業績」を更新しました
2022年2月17日
岐阜大学医学部寄附講座「妊産婦と子どものこころ診療学講座(岐阜県)」の設立を求める請願署名ページを掲載しました
2022年2月1日
「大井一高准教授らの論文発表、受賞」を掲載しました。
2021年11月16日
「深尾 琢助教らの論文発表」を掲載しました。
2021年11月16日
2021年11月10日
「杉山俊介助教らの論文発表」を掲載しました。
2021年10月25日
「スタッフ紹介」を更新しました
2021年10月25日
「入局実績」を追加しました
2021年7月16日
「医局説明会のお知らせ」を掲載しました
2021年7月16日
「教室の業績」を更新しました
2021年4月1日
トップページに「論文発表」を掲載しました
2021年4月1日
「スタッフ紹介」を更新しました
2021年3月18日
トップページに「論文発表」を掲載しました
2020年12月23日
トップページに「採択」「論文発表」を掲載しました
2020年10月15日
「スタッフ紹介」を更新しました
2020年7月16日
「医局説明会のお知らせ」を掲載しました
2020年2月21日
「【受賞】 大井一高 准教授が第49回日本神経精神薬理学会年会において2019年度学術奨励賞および第6回アジア神経精神薬理学会大会においてJSNP Excellent Presentation Awardを受賞しました。」を掲載しました。
2019年10月11日
「スタッフ紹介」を更新しました
2019年7月5日
「平成31年度 第2回医局説明会のお知らせ」を掲載しました
2019年7月5日
「入局実績」を更新しました
2019年7月5日
「教室の業績」を更新しました
2018年7月5日
「スタッフ紹介」を更新しました
2019年2月19日
「第11回 日本不安症学会学術大会」の案内を掲載しました