朱牟田夏雄訳『トリストラム・シャンディ』の紹介
2002年6月3日 内田勝
いかにもこの作品らしい箇所をいくつか抜き出してみました。引用はすべてロレンス・スターン作、朱牟田夏雄[しゅむた・なつお]訳『トリストラム・シャンディ』全3巻(岩波文庫、初版1969年)からのものです。〔2006年5月22日付記:この版は長く品切重版未定になっていましたが、「復刊ドットコム」での復刊運動などの成果が実り、2006年7月に重版再開されることになりました。〕
なお、引用の中の……は省略箇所、[ ]内はルビを示します。
[1]
私めの切な願いは、今さらかなわぬことながら、私の父か母かどちらかが、と申すよりもこの場合は両方とも等しくそういう義務があったはずですから、なろうことなら父と母の双方が、この私というものをしこむときに、もっと自分たちのしていることに気を配ってくれたらなあ、ということなのです。……。
「ねえ、あなた」私の母が申したのです。「あなた時計をまくのをお忘れになったのじゃなくて?」――「いやはや、呆れたもんだ!」父はさけびました。さけび声はあげながらも、同時にその声をあまり大きくしないように気をつけてはいました――「天地創造の時このかた、かりにもこんな馬鹿な質問で男の腰を折った女があったろうか?」え? 何だって? 君のおやじさんは何て言ったんだって?――いえ、それだけです、ほかには別に何とも。
(上巻 pp.34-5[原著の第1巻第1章])
|
小説の冒頭です。この本は田舎紳士トリストラム・シャンディの自伝という設定なのですが、自分の半生を語るにあたって誕生の場面から始めるならまだしも、さらに時間をさかのぼって両親が自分を「しこむ」最中の場面から始めてしまうというところが、徹底しています。最後のほうで「え? 何だって?」と語り手トリストラムに質問しているのは、読者です。全編を通じて、男女数名の読者代表がトリストラムの語りに口をはさんできます。
[2]
……この世の中には書物などすこしも読まない善男善女も大勢いらっしゃると同時に、読書ずきのお方もたくさんおいでになる――そしてそういう中には、人の身の上に関することなら、はじめから終りまで細大もらさず、どんな秘密でも打ち明けてもらわないとどうにも落ちつかない、という人物があるものです。……。
とはいえ、そう根源にさかのぼってこのようなことを知りたくはないといわれるお方々には、私のさし上げうる最上の忠告は、どうぞこの章のこれから先の部分はお読みとばし下さるようにということです。あらかじめ宣言しておきますが、これから先は好奇心の強いお方、せんさく好きのお方のためのみに書くのですから。
――――――――――――――扉をしめて下さい――――――――――――――
(上巻 pp.39-40[原著の第1巻第4章])
|
こんなふうに言われてしまえば、ぜひとも扉の中に入ってトリストラムの話の続きを聞いてみたいと思ってしまいませんか?
[3]
だんだん私といっしょに進んで下されば、今二人の間に芽ばえかけているかすかな相識の関係は、進んで親近感となり、そのまた親近感は、あなたか私がどちらかが失策でも犯さぬかぎりは、最後は友情にもなることでしょう。――ああ、そのすばらしき日!――そうなればこの私の身にすこしでもかかわりのあることは、もとより些細とは思われず、聞いて退屈とも思えぬでしょう。
(上巻 p.45[原著の第1巻第6章])
|
相識[そうしき]とは「知り合い」のことです。この本を読んでいて不思議なのは、いつのまにか十八世紀の田舎紳士トリストラムが、自分のすぐそばにいる、仲のいい友達のように思えてくることです。原著がロンドンで出版されたのは1760年から67年にかけてのことなんですが、とても二百数十年前に書かれた文章とは思えない生々しさです。もちろんそれは朱牟田さんの訳文の効果でもあるのですが。
[4]
――どうしてまあ奥さま、あなたはすぐ前の章をそんなにうわの空で読んでいらしたのです? 私の母はカトリック教徒ではなかったと、申上げたではありませんか。――カトリック教徒ですって! そんなことはおっしゃらなかったわ!――失礼ですが奥様、もう一度はっきり申上げます。私はそのことを、すくなくともそこの言葉から直接推定できる程度にははっきりと、申上げておいたはずです。――それじゃ私、一ページほど抜かして読んだのか知ら?――いいえ奥さま、一語だって抜かしてなんかいらっしゃいません。――じゃ眠っていたんだわ、きっと。――そんな逃げ口上は奥さま、私の自尊心がゆるせません。――それじゃ、そんなことは、一言だって記憶がなくってよ、本当のところ。――だからそれを、奥さま、奥さまの責任だと申すのです。そこでその罰として、今すぐ、ということはこの次の文章の切れ目のところに辿り着き次第、もう一度前の章にもどって、十九章全体を読み返していただきます。
(上巻 pp110-1[原著の第1巻第20章])
|
ある女性読者がトリストラムに叱られている場面です。自分までいっしょに叱られているようで、ちょっとドキドキします。
[5]
……現在私がはからずも迷いこんでしまったこの長い脱線ですが、ここには私のすべての脱線の場合と同じく……、脱線術としての入神の妙技が秘められているのです。がそういう秘術を残念ながら読者諸賢は終始見おとしておいでらしい――それは何も諸賢に洞察の力がないからというのではなく――ただ、このような神技が脱線というものに普通予想も期待もされないからにほかなりません。――それというのはこういうことです。たしかに私の脱線ぶりは、諸賢も御覧の通り公明正大なものであり、自分の従事している仕事をそっちのけに、大英帝国のいかなる文士にも負けぬほどに、遠いかなたまで、またそれも機会あるごとに、逸脱してしまっているにはちがいありませんが、それでいて私は、私の留守中といえども私の本来の仕事が歩みをとめてしまわないような布石だけは、一瞬も忘れていないのです。
たとえば私はつい先刻も、わが叔父トウビーのこの上なく気まぐれな性質について、その大きな輪郭をお伝えする仕事にかかっていました――そこに突如として私の大伯母ダイナーと例の馭者が飛びこんで来て、われわれを何百万マイルのかなた、わが太陽系のまっただ中までも拉[らっ]し去ってしまいました。にもかかわらず叔父トウビーの性格の描写は、その間も絶えず静かにつづけられていたことは諸賢もお認めでしょう――なるほど大きな輪郭のほうではない――それはとうてい不可能でした――しかしあちらでちょっと砕けた一筆、こちらでかすかにほのめかす暗示という類が、脱線話の途中でも随所に叔父の性格に添加されて、その結果は皆さんは私の叔父トウビーについて、前よりもはるかに知見を肥やしていらっしゃるわけです。
(上巻 pp.129-30[原著の第1巻第22章])
|
とにかく脱線だらけの小説で、上巻の半分を過ぎても主人公のトリストラムがまだ生まれてこないくらいです。とはいえ確かに上の引用が主張するとおりで、めまぐるしく脱線する話の中でも、主要登場人物それぞれの性格は少しずつ着実に描かれていきます。
[6]
脱線は、争う余地もなく、日光です。――読書の生命、真髄は、脱線です。――たとえばこの私の書物から脱線をとり去って御覧なさい――それくらいならいっそ、ついでに書物ごとどこかに持ち去られるほうがよろしい――あとに残るのは各ページ各ページを支配する一つづきの冷たい永遠の冬です。今度は脱線をふたたび作者に返して御覧なさい――作者は新郎[にいむこ]にたとえられた太陽のごとくに進み出て――すべての者に祝福をおくり、多彩の変化を現出させ、何人[なんびと]の食欲をも飽かしめることがないでしょう。
(上巻 p.131[原著の第1巻第22章])
|
「読書の生命は脱線にあり」なんて、名言ですね。
[7]
文章とは、適切にこれをあやつれば(私の文章がその好例と私が思っていることはいうまでもありません)、会話の別名に過ぎません。作法を心得た者が品のある人たちと同席した場合なら、何もかも一人でしゃべろうとする者はないように、――儀礼と教養の正しい限界を理解する作者なら、ひとりで何もかも考えるような差出がましいことは致しません。読者の悟性に呈しうる最も真実な敬意とは、考えるべき問題を仲よく折半して、作者のみならず読者のほうにも、想像を働かす余地を残しておくということなのです。……。
ところで、今は読者の持ち場です。――私はスロップ医師のいたましい落馬と、また同医師の裏の居間へのいたましい出現とを、詳細にお話ししました。――今度は読者の想像力に、しばらくその先を考えていただかないと困ります。
(上巻 pp.182-3[原著の第2巻第11章])
|
「文章とは会話の別名にすぎない」というトリストラムの言葉はこれもまた名言だけれど、これから先の展開を読者が自分で考えろと言われても、困りますよね。なお「スロップ医師」は産科医で、トリストラムの誕生に立ち会います。途中ぬかるんだ道で馬から落ち、全身泥まみれの姿でシャンディ屋敷に到着したところです。
[8]
本を読んで下さいよ、本を、本を、本を! どうぞ無学の読者諸公、もっと本を読んで下さい――いやそれよりも……はじめからはっきり言っちゃいましょう、今すぐそんな本などはお捨てになるほうがよろしい――と申すのは、つけ焼刃の読書くらいでは、というのは申すまでもなくつけ焼刃の知識ではという意味ですが、この次に出て来る墨流し模様のページの教える教訓など、とてもあなたにわかるものじゃありませんからね(このページこそ、私のこの著作のゴチャゴチャした象徴なんですがね!)
(上巻 pp.356[原著の第3巻第36章])
|
原著の初版(および初期のいくつかの版)では、ここで二ページ(紙一枚分)にわたって極彩色の墨流し模様が挿入されました。一冊一冊につきこのページだけは手作業で染められたので、一つとして同じ模様をもった本はないことになります。本来の「墨流し模様のページ」がどんな色をしていたかは、初版本の画像をご覧になるか、またはグラスゴー大学図書館所蔵本の鮮明なカラー画像でご覧ください。なるほど、まさにこれこそ『トリストラム・シャンディ』の象徴という感じで、ページの余白という枠の中にとどまりながらも、つねにグニョグニョ動いているかのようですね。ちなみに、残念ながら岩波文庫版では白黒の印刷です。
[9]
私は十二カ月前の今ころ、つまりこの著作にとりかかった時にくらべまして、ちょうどまる一カ年、年をとっております。そして、今、御覧の通り第四巻のほぼまん中近くまでさしかかっているわけですが――内容から申せば、まだ誕生第一日目を越えておりません――ということはとりも直さず、最初に私がこの仕事にとりかかった時に比べて、今日の時点において、これから書かねばならぬ伝記三百六十四日分ふえているということです。従って私の場合は、今までせっせと骨を折って書き進めて来たことによって、普通の著作家のようにそれだけ仕事が進行したというのではなく――逆に、四巻書けばちょうどその四巻分だけうしろに押しもどされたことになるのです――それは私の生涯の毎日毎日がもしもこの日のように忙しい日ばかりというのならですが――そうでないという保証はどこにもありますまい――また、それをいちいち記録して意見まで述べてゆくのには、何しろ今の調子ですと私のペンの速さの三百六十四倍の速度で私は生活してゆくわけですから、まさにそれに匹敵するだけの記述は必要になる理窟ですし――それを短く切り詰めてよいという理由はどこにもないでしょう?――そこで必然的に結論できることは、諸賢のおゆるしをいただいて申してしまえば、私が書き進めば書き進むほど、書かねばならぬことはそれだけふえてゆくということ――また当然諸賢のほうは、読み進めば読み進むほど、読まねばならぬことがそれだけふえてゆくということになります。
(中巻 pp.68-9[原著の第4巻第13章])
|
『トリストラム・シャンディ』の原著は最初のうち、毎年二巻ずつ新しい巻が出版されました。これは二年目に出た第四巻に出てくる文章です。同時代の読者の中には、トリストラムの言葉を真に受けて気が遠くなった人もいたかもしれません。
[10]
|
さてこのあたりからいよいよ話の本筋にはいってゆくわけですが、……これからは私の叔父トウビーの物語を、ついでに私自身の物語も、かなり直線に近い形で進められることを私は信じて疑いません。ふりかえって見ますと、
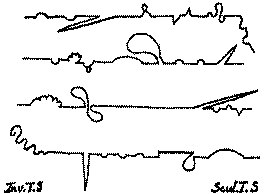
これがこの本の第一巻、第二巻、第三巻、第四巻でそれぞれ私が動いてきた線でした。――第五巻はたいへんうまく行って、――あそこで私がたどった線は、まさに次のようなものでした。
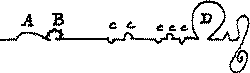
……この調子で私が進歩してゆくならば……今後はつぎのような模範的な進み方に到達することさえ、決して不可能ではありません。
これは私があるお習字の先生のものさしを借りて(わざわざこのために借りたのですが)、右にも左にもそれないように、できるかぎりまっすぐに引いてみた線です。
(中巻 pp.348-51[原著の第6巻第40章])
|
夏目漱石が『トリストラム、シヤンデー』(明治30年[1897年])という評論でこの作品を日本に初めて紹介したとき、わざわざ模写して引用した曲線です。
さて、果たしてトリストラムはこのあと本当に「直線に近い形で」話を進めることができるのか、そして彼は自分の半生の物語と叔父トウビーの物語を語り終えることができるのか――その答えはぜひ、公共図書館に入っていることの多い『筑摩世界文学大系・リチャードソン/スターン』または岩波文庫版に収められている、朱牟田夏雄さんの名訳でお確かめください。
(c) Masaru Uchida
2002
『電脳空間のローレンス・スターン』に戻る