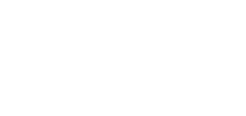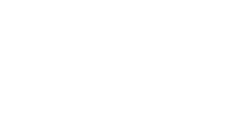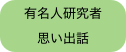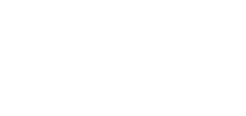植物分子生理学研究室
Lab for Plant Molecular Physiology, Fac Appl Biol Sci, Gifu University
機能を推定する1
1.ある状況下でのみ機能するもの

上の写真は北海道のどこかの国道。街灯のようでいてただの下向きの矢印が妙である。道が地図から外れてしまわないように押さえつけているようにも見える。
実はこの矢印は冬に活躍する。冬になると何もかもが雪に埋もれてしまう(ガードレールも)。上の場所は平坦な雪原に変わる。そのときこの矢印は、除雪車が「どこまでが道路か」を知るのに役に立つ。これがないと除雪車はガードレールにぶつかって破損事故を起こす。ガードレールのない道だと路肩から落ちてしまう。
ということなのであるが、「北海道の積雪はすごいなあ」という話をしたかったのではなくて、夏にこの矢印を見かけたとしてその機能を推測できるか?という問題を提示したかったのであった。今からバイオ研究における機能推定の話をしてみたい。
一見機能していないモノが、別の状況下では活躍しているというのはそれほど珍しい話ではない。北海道の矢印は1年の4分の1は機能しているのでわかりにくいというほどのことではないかも知れない。植物科学の例で言えば「夜間のみ機能する遺伝子」は多数あり、そのことが研究上の死角になったりはしない。ところが、これが「月夜のみ」とか、「大潮の夜のみ」、「2/29の夜のみ」となってくるとなかなか難しい。

(銀閣寺の庭、月夜のみ機能する)
植物遺伝子の機能を調べようとすると、標的とする遺伝子の破壊株を作出して、野生型で見られる生理応答のどれに不具合があるかを調べるのが定石である。まずは普通に栽培してライフサイクル(発芽から成長、開花、種子形成まで)がちゃんと回るかどうかを観察するのであるが、そこで異常が見らなかった場合、「この遺伝子は機能していない」と考えるのではなく、「この遺伝子が機能する場面を捉えられていないのかも」、と考えてもうひと工夫してみる。よくやるのはストレスをかけてみてストレス耐性に異常がないかを見る、というアプローチである。ストレス応答系はある意味おまけの成分なので異常があってもライフサイクルはちゃんと回る。植物へのストレスの基本形としてはそんなに種類がない(生物ストレス+環境ストレスで〜20種類)のでひとつづつ調べることは可能である。それでも異常が捕まらない場合は困ってしまう。いろいろ考えてかなり特殊な状況を用意したりもする(例えば、栽培時の光強度を10倍に上げたりもとに戻したりを10分ごとに一日中繰り返す、とか)。特殊な状況は無数にあるので、調べている遺伝子の情報から「機能していそうな状況」を推定して絞り込み、検定する。

ということで、いろいろ修行を積むと上の景色から春の桜満開の情景を想像できるようになるという話でした(違うかな)。
(なかなか話は盛り上がらない、つかみはよかったのに、、、つづく)
2020. 5. 15
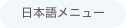
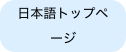
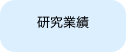
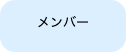
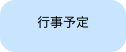
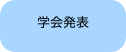
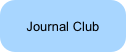
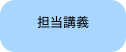
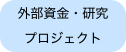
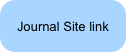

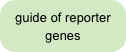
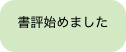


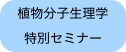
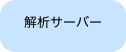

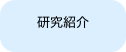
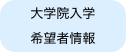
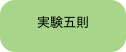
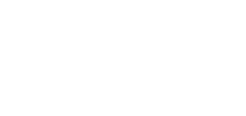
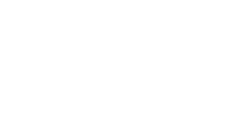
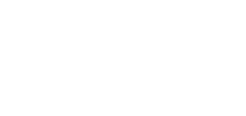
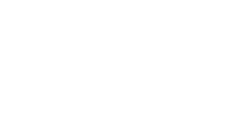
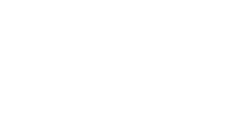
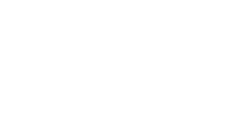
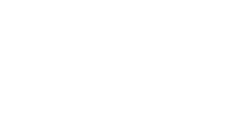
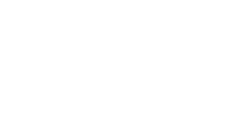
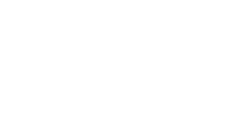
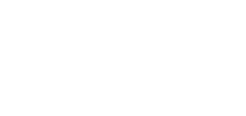
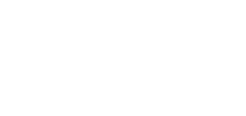
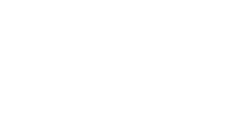
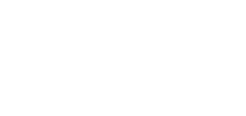
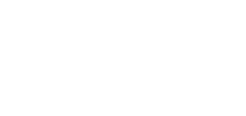
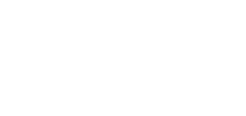
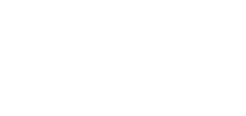
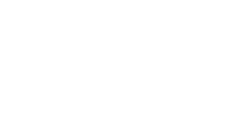
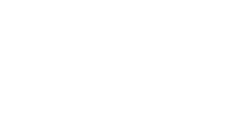
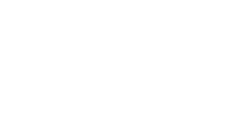
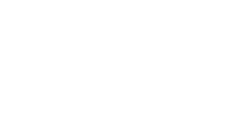

Highly Cited Researchers of Gifu University