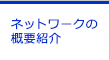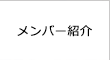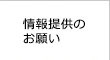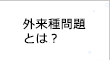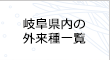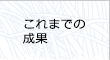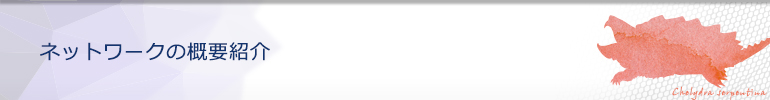
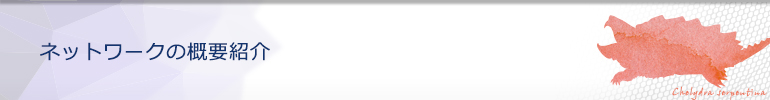
 外来種が生態系に与える影響は、世界中で問題になっています。身近な環境でも、外国から多くの動植物が持ち込まれたり、あるいは日本の地域間を人の手によって持ち運ばれたものが野外に放されています。その中には、ブラックバスのような淡水魚、アメリカザリガニのような甲殻類、アライグマやヌートリアなどの哺乳類、オオキンケイギクのような植物など、さまざまな動植物がいて、日本のもともとの自然環境を変化させたり、在来の動植物の棲み場所を減らしています。 外来種が生態系に与える影響は、世界中で問題になっています。身近な環境でも、外国から多くの動植物が持ち込まれたり、あるいは日本の地域間を人の手によって持ち運ばれたものが野外に放されています。その中には、ブラックバスのような淡水魚、アメリカザリガニのような甲殻類、アライグマやヌートリアなどの哺乳類、オオキンケイギクのような植物など、さまざまな動植物がいて、日本のもともとの自然環境を変化させたり、在来の動植物の棲み場所を減らしています。 すでに日本中に広がってしまった外来種の中で、特に生態系への影響の大きなものは「侵略的外来種」と呼ばれ、駆除が進められています。しかし、日本中に広がってしまったものへの対策は大変な労力がかかりますし、駆除される動植物の個体数も莫大な数になるため倫理的な問題も生じます。したがって、外来種対策は侵入や定着の未然防止が最も重要ということになります。  そこで、岐阜大学では、野生生物の研究者の有志による「ぎふ生物多様性情報収集ネットワーク」を結成し、外来種の早期発見と対策のための活動を始めました。 そこで、岐阜大学では、野生生物の研究者の有志による「ぎふ生物多様性情報収集ネットワーク」を結成し、外来種の早期発見と対策のための活動を始めました。 外来種の侵入にいち早く気付くのは、釣り人や漁師、自然観察のガイド、農家の方など野外で活動している人たちです。しかし、変わった魚が釣れた、見たことないような動物がいる、などの話は、仲間内での単なる話題で終わってしまったり、あるいは行政機関に相談しても、担当者がどのように対応すれば良いか分からずに情報がうやむやになっているのが現状です。 そこで、「ぎふ生物多様性情報収集ネットワーク」は、そうした情報の受け皿となり、発見した動植物の種を正確に同定し、外来種の侵入情報を取りまとめて公表することで、早期に対策を進められるように手助けすることを目的としています。また、県や市町村の行政機関、博物館、水族館などに市民から情報が寄せられた場合も、「ぎふ生物多様性情報収集ネットワーク」へご連絡いただければ、助言や調査をおこないます。 外来種が増加する前に対策を取ることで、地域の自然を守り、被害を最小限に抑えるために、どうかご協力いただければ幸いです。 「ぎふ生物多様性情報収集ネットワーク」の発足にあたっては、平成26年度岐阜大学COC「地域志向学プロジェクト」の助成を受けました。 |