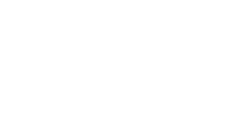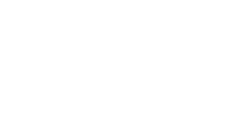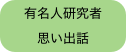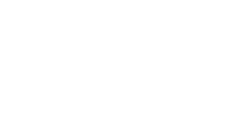植物分子生理学研究室
Lab for Plant Molecular Physiology, Fac Appl Biol Sci, Gifu University
私の学術的達成あれこれ
Peter H Quail博士に"my scientific grandson"と紹介された
Quail博士といえば泣く子も黙るフィトクロム研究の大御所である。余談になるが、昔私の論文の覆面審査員の一人から「この光強度ではもやしの長さがこのようになるはずがない」という評を頂いたことがあった。詳しくは覚えていないが例えば私のデータでは長さ8mmとなっているがこの波長・光強度であれば正しく実験を行えば6mm程度になるはずだ、というようなことである(もやしが少し伸びた理由は把握していたがここでは割愛)。世界広しといえども、そして年配の植物生理学者というものがいかに筋っぽいといえどもこんなことを言うのはかのQuail博士以外にはいないだろうと私は今でも思っている。というような評判のヒトである。その厳格な性格など想像して頂けると思う。
私は彼のところで学位研究を行ったXing-Wang Deng博士の下で研究をしていたが、学会のついでに寄った米カリフォルニア州バークレーのQuail博士のところでセミナーを行った際、タイトルにある御言葉を我が学術的祖父(scientific grandfatherのことである)から頂いてしまった。セミナーの雰囲気を盛り立てようとして言ったジョークであるという説が有力であるが、内心とても恐縮したのを覚えている。
Achim Trebst博士にDBMIB(光合成阻害剤)の作用機作を説明した
Trebst博士といえば泣く子も黙る光合成阻害剤研究の大御所である。除草剤を用いて光合成の研究をするという時代を作った人であり、彼が1980年に書いた光合成阻害剤の作用機作に関するレビューは30年弱を経た今でもなお広く引用されている。
ドイツのボーフム大学で植物の光ストレス応答についてのセミナーをしたときのことである。紹介したデータのなかにDCMUとDBMIB(いずれも光合成阻害剤)を用いたものがあった。データは光ストレス応答とステートトランジションが同じような特徴を持つことを示唆していた(つまりはちょっとしっくりこないデータであった)。
セミナー後の質問タイムで聴衆の一人がDBMIB処理で光ストレス応答が活性化されるのはどういうことか、カロテノイド合成阻害剤と同じ効果を与えているようだが、という質問をした。私の答えは「DBMIBは光合成のこれこれのところの反応を止めるので、DCMUの結果と合わせて型どおりの解釈をするならばこれこれということになる。ちょっと腑に落ちないのですけどね。カロテノイドについては、、、」とフランクなものであった(いつもこんなんです)。
質問タイムが終わると先ほどの質問者(6~70代くらいの小柄な人)がつかつかと私のところへやってきて、ちょっと自分の研究室へ来るといい、と言うのである。すたすたと先導する老人について大学内をしばらく歩くと彼は立ち止まって、「ここが私の部屋だ」と部屋の入り口のネームプレートを指さした。指の先には何と"Prof. Dr. Achim Trebst"と書いてあるではないか!私は知らなかったがTrebst先生はまだ現役だったのである。突然の大先生の出現に私は少々動揺してしまった。
つまり、Trebst先生は客の驚く顔が見たくてそれまで自己紹介もせずに学内を連れ回してきたのである。そして、仰々しく自分の名前を指し示したのである。口頭で自分の名前を言うより活字を見せた方がビッグサプライズであると見当をつけていたのである。とても初犯とは思えない手際のよさである。
そのあと親切にいろいろとお話しして頂いたので、バツの悪さは薄らぎはしたものの、、、、、、ま、Trebst大先生に向かってDBMIBの説明をしたのは世界広しといえども私くらいのものだと思う。昔から言われているように「無知は力なり」である。
その後ドイツの別の大学に行ったときにTrebst先生に師事したことがあるという先生とお会いした。上記のエピソードは格好の酒の肴になったので、個人的には「モトは取った」ということにしている。
ドイツ話おまけ
ちなみにボーフム大では私のホストのLink先生は急遽入院中で、(おそらく)私が見舞いに来ないように入院先をラボの学生にも隠したまま、しかしその不明の入院先から電話で学生に客の世話を細かく指示してくるのであった。後で聞けば本人は心臓発作で入院して手術の予定がたっていた、という本来なら客どころではない状況だったらしい。後日先生の論文の別刷を頂いた。署名とコメントがあったが、別刷に直接書かれておらずに挟んだしおりに記入されている、という繊細な気配りが現れていたのであった。
ドイツ話おまけ2
ボーフムの次に行ったドイツのJena大学のOelmuller研究室では、講座の歴代教授の肖像画が並べて飾ってあった。そのうちのひとつはかのゲーテである。ドイツ恐るべし。
辻英夫先生と同じ着想を得た
辻先生と言えば、整理された考えを的確な言葉使いで表現するという点において人並み外れた能力をお持ちになる植物生理学者であり、大変スマートな尊敬すべきお方である。
私が大学4年生になって(いつの時代の話やら)研究室配属が決まり、新歓パーティーが開かれたときのことである。会場は日高敏隆宅で、バーベキューが行われたと記憶している。日高家では猫を飼っており、その猫が外でうんちをすると、それが日高宅の玄関先にこっそり届けられることがある、という話が家の主人から披露された。おそらくは近隣の匿名有志の行いである。私は(律儀な人がいるもんだ)と内心思っていたら、かの辻先生が「それは律儀な方がおられるのですね」と上品に軽口を繰り出してこられるではないか!私が辻先生と同じ着想を得たとすれば、これはもう大したものである。上品かつ明晰な世界への切符を頂いたようなものである(そうなのか?)。
猫のおみやげの話に戻るが、京都にはそんな隠れた有志はたくさんいる。しかもしてくれるのは「配達」に限らず多岐にわたっている。ただぶらぶらと町中を散歩しているように見える婆さん達を決して甘く見てはいけない。組織的な自警団の必要が無い町である。京都恐るべし。
そのほかのことなど
と、一時は才能のきらめき(猫の話である)を見せはしたものの、意に反してその後は冬の時代が来てしまった。 才能と思っていたのは何か別のものだったのかも知れない。
学会や講演会などで自分の研究成果を発表する機会に時折冗談を紛れ込ませるのであるが、聴衆の反応を見ると散々なものである。私が冗談であると思っているところのもの、を述べるとすると、「...ん? 今のはジョーク?ジョークだった?あらあら壇上の人は何だかレスポンスを待ってるみたいだなあ、、、、笑ってあげないと」というようなばらけた反応が会場の前側四分の一程度のエリアから、かつそのあたりの密度でいうと20%程度の割合で漏れてくるのである(とすると会場全体からみると反応があったのは5%、という計算になる。残りは95%である。言うまでもないことではあるが)。初めの「...」は約1.5秒から2秒程度である。とりあえずこの間(ま)が私にとっては辛い時間なのであった。
学会というのは講演中の出入りは可能であり(褒められはしないが)、また、次の講演がお目当てで来ているので今講演中のは興味がないから聞き流す、という人も少なくない。そういう雰囲気でいうと会場の前側1/4というのはなんとか講演者の問いかけが届く範囲である(講演にもよる)。講演者が「あなた」と呼びかけると「私のことか」と思える範囲である。講演者のプレッシャーが届く範囲であると言ってもよいかもしれない。
ということを勘案すると私のやってきたのは、「礼儀正しい学会関係者に笑いを強要したところ、約2割の人達がしぶしぶ反応した」ということになるのであろうか。冬の時代である。果たして春は来るのか?来ないのか???
(つづく)
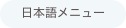
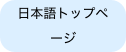
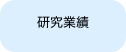
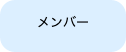
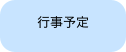
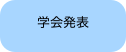
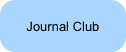
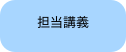
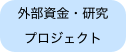





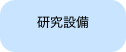
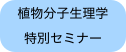
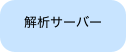

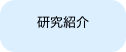
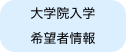

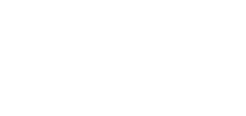
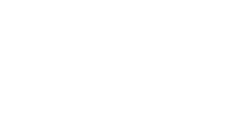
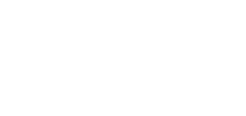
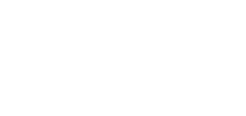
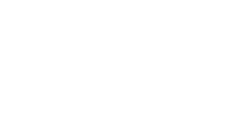
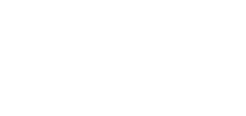
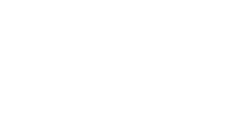
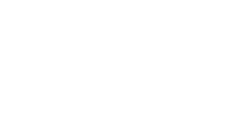
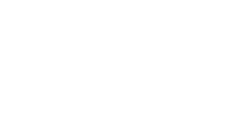
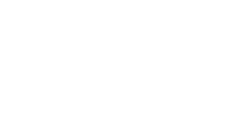
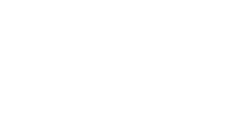
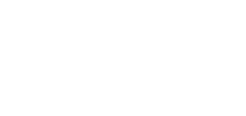
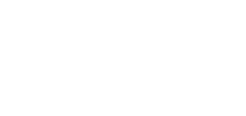
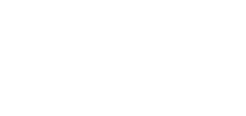
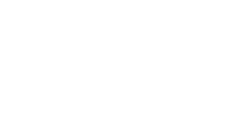
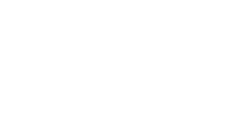
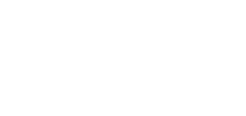
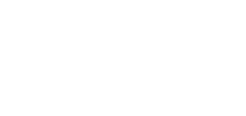
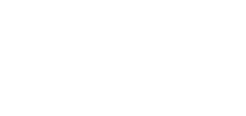
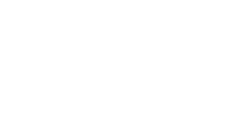

Highly Cited Researchers of Gifu University