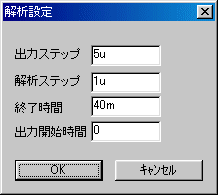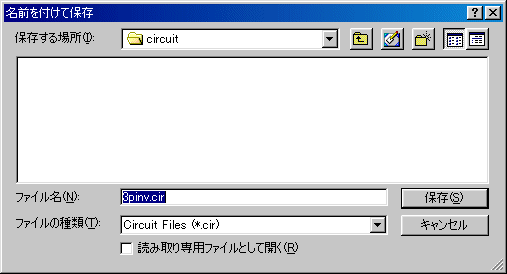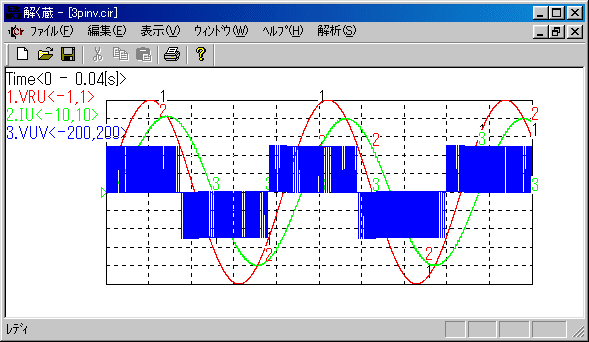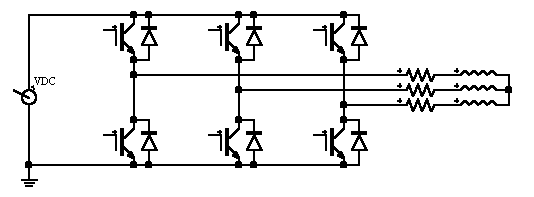
3相インバータ回路の解析例
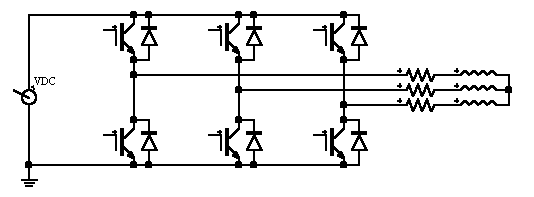
| 主回路の入力 | |
| 回路部品パラメータの入力 | |
| 制御回路の入力 | |
| 制御部品パラメータの入力 | |
| 波形出力部品の入力 | |
| 出力部品パラメータの入力 | |
| ノードの自動割付処理 | |
| 保存 |
| ネットリストの出力 | |
| 回路シミュレータの起動 | |
| 解析結果 |
○主回路の入力
図面設定
先ず、見やすいように図面の大きさと、その表示の大きさの設定を行います。
メニューから図面設定を選択して、ダイアログを表示して設定します。
ここでは、表示倍率を変更します。
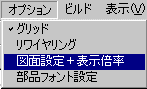
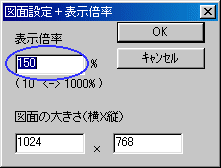
主電源の配置
ツールバーからVsを選択します。
この状態で、パーツの配置モードになり、クリックした場所に配置することができます。
配置したら、右クリックで配置モードから選択モードに移ります。
さらに、素子ををダブルクリックすると素子設定ダイアログを表示することができます。
書式欄にパラメータの書式が表示されます。
ここでは、直流100Vですから、書式の1番目を用います。
パラメータ欄には、「DC 100」と入力します。
「OK」ボタンで確定します。
シート上の何も無いところをクリックすると、デフォルトモードに戻ります。

トランジスタ・ダイオードの配置
同様にツールバーからTrとDioを選択して、適当なところに配置します。
左クリックを連続で行うことで複数の素子を配置も可能です。
ダイオードはデフォルトで水平向きですので、垂直に回転させます。
選択している状態(黄色に反転)で、メニューの回転を選択します。
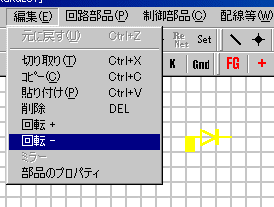
同様に、抵抗とインダクタを配置して素子値を入力します。
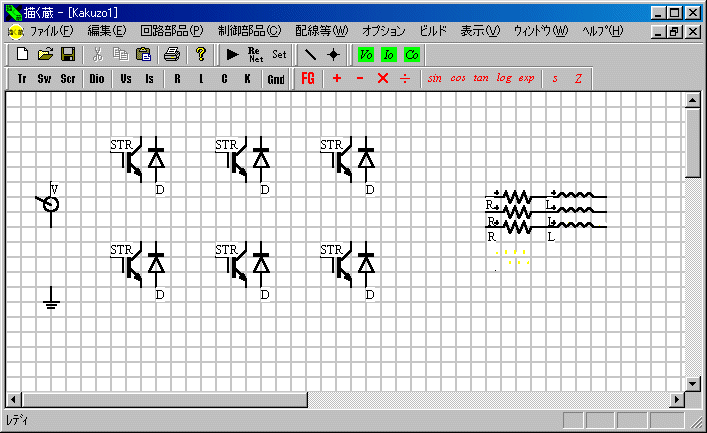
配線
ツールバーから
![]()
を選択すると、ポインタが変わり配線モードになります。
左クリックで端点を配置します。もう一度左クリックすることで配線を行います。
右クリックで、配線開始状態に戻り、さらにもう一度右クリックでデフォルトモードに戻ります。
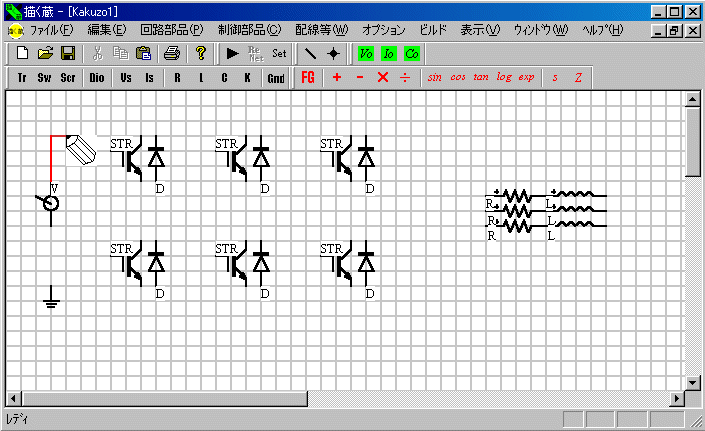
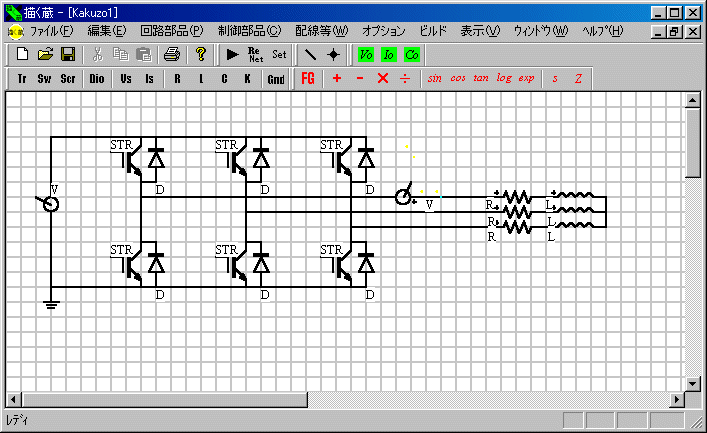
制御回路の入力
この例では、三角波比較法によるPWM制御を行います。
まず、リファレンスの正弦波(Vref)とキャリアの三角波(Vc)を作成します。
つぎに、(Vref-Vc),(Vc-Vref)を行いゲート信号を作ります。
本シミュレータのトランジスタは、ゲート信号が正のときONとなりゼロ以下のときにOFFとなるスイッチです。
そのため、先につくったゲート信号を直接トランジスタのゲートピンに結線して構いません。
○制御回路の入力
信号発生器FGを用いて、リファレンスとキャリアを発生させます。3相リファレンス用+キャリア信号用の4個を配置します
また、比較のための差分器を各トランジスタ分だけ6つ配置します。
つぎに、各ブロックの結線を行います。
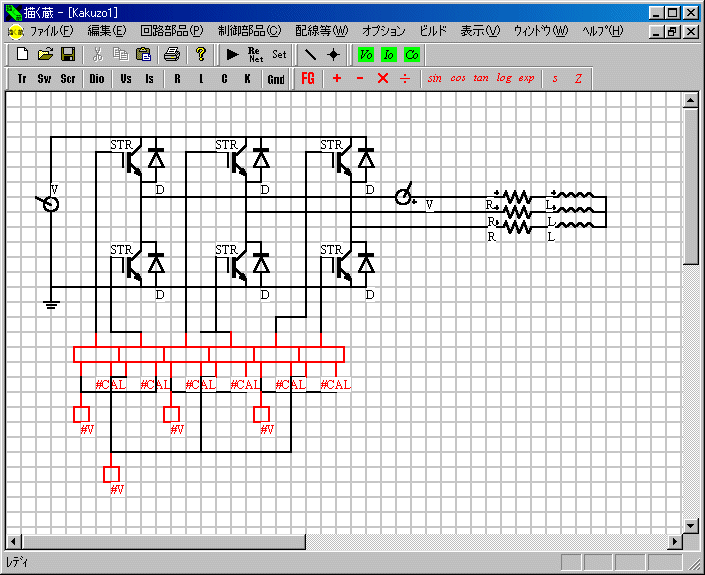
○制御部品のパラメータ入力
リファレンスの入力
u相リファレンスの信号発生器をダブルクリックしてプロパティダイアログを表示します。
書式2を用いて正弦波を発生させます。
ここでは、(オフセット:0) 振幅:1
周波数:60Hz (位相:0)を作りますので、図のようにパラメータ欄に
SIN 0 1 60 0
と入力します。
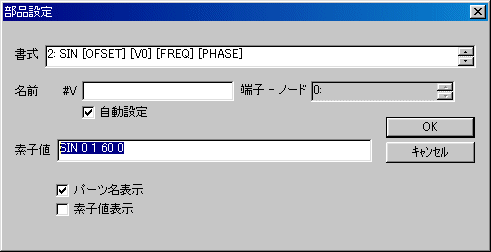
同様にv相・w相についても
SIN 0 1 60 -120
SIN 0 1 60 0 120
とします。
プロパティの素子の名前の自動設定のチェックボックスのチェックをはずせば、素子に任意の名前をつけられますので、それぞれ、Vru,Vrv,Vrwとしていくと分かりやすいかも。ただし、コピー・ペーストをすると属性もコピーされるので、同じ名前の部品になってしまいます。ご注意ください。
キャリア信号(三角波)の入力
信号発生器の書式3を用いてパルス幅ゼロのパルス波形として三角波を発生させます。
ここでは、振幅:1 周波数:5kHzの三角波なので、
パルス波形のパラメータは、最小値:-1 最大値:1 遅れ時間:0 立上がり:0.1ms 立下り:0.1ms パルス幅:0 周期:0.2ms となる。
パラメータ欄には
PULSE -1 1 0 0.1m 0.1m 0 0.2m
と、入力します。
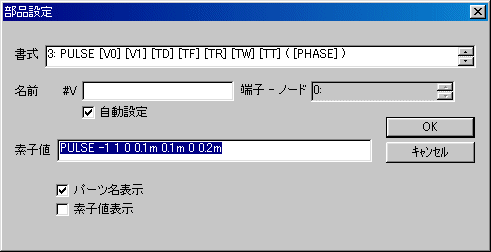
u相リファレンス Vru = sin( 2・PI・f )
v相リファレンス Vrv = sin( 2・PI・f − 120)
w相リファレンス Vrw = sin( 2・PI・f + 120 )
○波形出力部品の入力
uv相の線間電圧と、u相の線電流およびu相のリファレンスの表示を行います。
電圧の出力
電圧の観測には、電圧出力部品を用います。この部品の端子を測定したい個所のノードと接続します。
パラメータ欄には、表示グラフの最小値・最大値および表示名称を記述します。
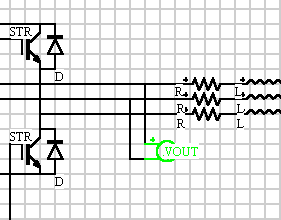
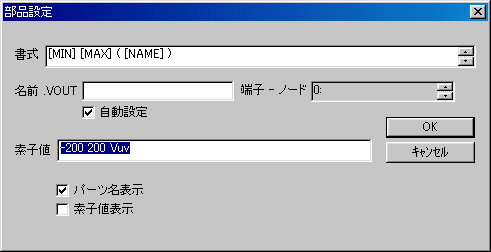
電流の出力
本シミュレータでは電流の観測は、電流出力部品だけでは行うことができません。電流出力付き電圧源の電流出力ピンと合わせて可能となります。
そのため、電流の観測したい個所に、電圧源が無くてはいけません。無い場合は、「電流出力付の電圧源」もしくは「電流センサ」を接続して、そこから電流値を出力します。
電流出力ピンに接続できるのは,「電流出力」と「電流入力インターフェース」部品のみです。
ここでは、線電流を観測するために、電圧源V(DC 0V)を置き、それに電流出力部品を接続しています。
パラメータ欄には、表示グラフの最小値・最大値および表示名称を記述します。
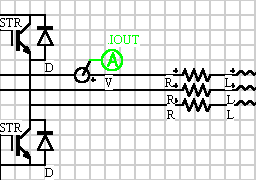
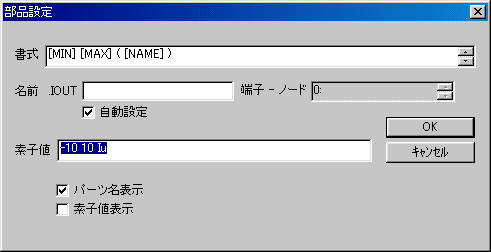
制御ノードの出力
制御の観測には、制御出力部品を用います。
測定したいノードに、制御出力部品の端子を接続します。
パラメータ欄には、表示グラフの最小値・最大値および表示名称を記述します。
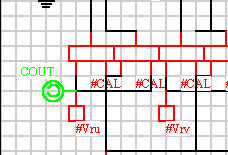
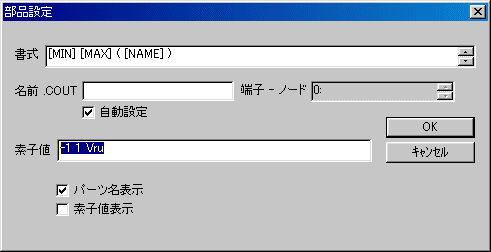
解析の実行
解析は、ネットリストの出力
![]()
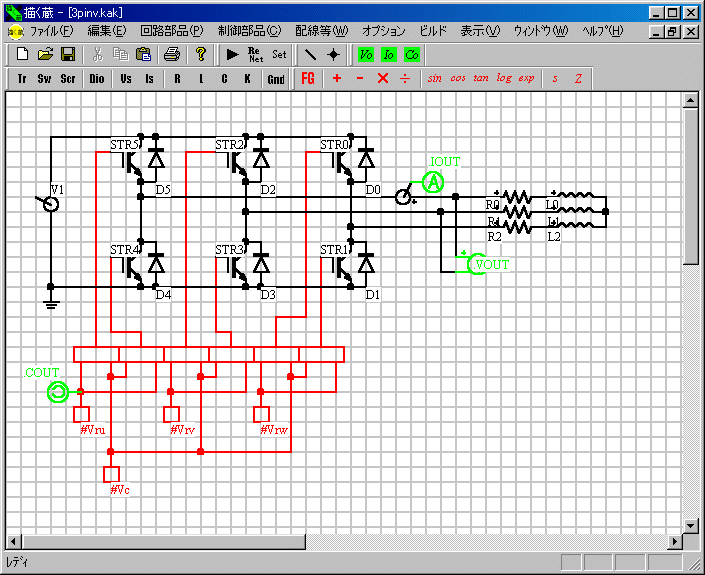
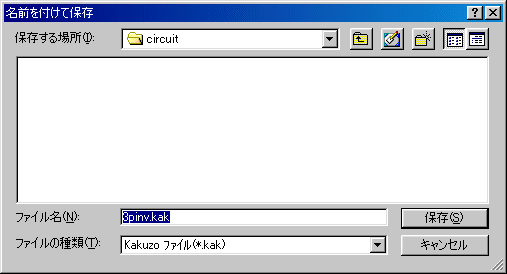
![]()